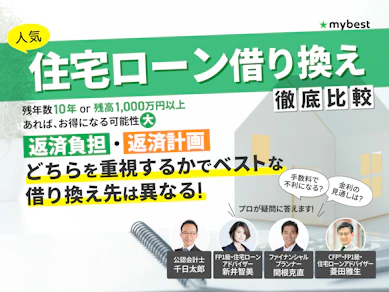
【2026年2月】住宅ローン借り換えのおすすめ人気ランキング【手数料・金利を徹底比較】
住宅ローンの借り換えは、「毎月の返済額を抑えたい」「将来の金利変動に備えたい」といった悩みがある人におすすめ。しかし、今後の金利の見通しや、変動金利・固定金利どちらを選べばいいのか、手数料で不利にならないのかと悩む人も多いはず。
今回は、人気の借り換えができる住宅ローン15商品を、3個のポイントで比較して徹底検証。選び方とともに、おすすめの借り換えができる住宅ローンをランキング形式でご紹介します。
マイベストが定義するベストな借り換えができる住宅ローンは「金利だけでなく、がん団信の上乗せ金利・手数料を含め支払い負担が軽い住宅ローン」。徹底検証してわかった借り換え住宅ローンの本当の選び方も解説しますので、ぜひ住宅ローン契約の際の参考にしてください。

1972年生まれ兵庫県出身の公認会計士、オフィス千日合同会社代表社員。監査法人時代に資格を伏せて開始した「千日のブログ」がきっかけとなり、住宅ローン不動産分野の専門家として「日本経済新聞」、「WBS(テレビ東京)」ほか多数メディアで活躍。著書は「家を買うときに「お金で損したくない人」が読む本」、「住宅ローンで「絶対に損したくない人」が読む本」(それぞれ日本実業出版社)、「50歳からの賢い住宅購入」(同文館)ほか多数。その豊富な相談事例とロジックをAIに応用させたスマートフォンアプリの「AI住宅ローンシミュレーター」は、ファイナンシャル・プランナーのみならず住宅購入希望者必携のアプリとなっている。

コンサルタントとしての個人向け家計、運用、住宅、年金、相続などの相談や、NISA・iDeCoをはじめとした運用にまつわるセミナー講師を行う。また、多くの金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間600本以上の執筆・監修をこなしており、これまでの実績は3,000本を超える。

株式会社投資用マンションSOS 代表取締役。ライフプラン作成、保険見直し、住宅ローン提案、投資用不動産計算など、年間300件ほどの面談依頼を受けている。住宅ローン分野では新規での借入以外にも、借り換え・団信など幅広くアドバイスを提供している。YouTubeチャンネル「住宅FP関根」では住宅ローン・不動産投資などを分かりやすく解説しており、10万人を超えるチャンネル登録者がいる。著書に『ワンルームマンション投資で騙されない!』がある。

CFP®・1級FP技能士・住宅ローンアドバイザー。1993年、早稲田大学法学部卒業後、山一証券に入社し営業業務に携わる。山一証券自主廃業後、金融商品や保険商品は一切売らない独立系FPに。以後約28年間、講演や執筆を中心に活動。講演回数4,800回超、コラム執筆3,500本超。リクルート「SUUMO」コラム連載17年目。「住宅ローンアドバイザー通信」連載18年目。近著は、「お金のトリセツ100」(経済法令)、「日経マネーと正直FPが教える一生迷わないお金の選択」(日経BP)ほか。YouTube「正直FPヒッシー先生のお金の教室」、Voicy「正直度100%お金のラジオ」でも情報発信中。

大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
検証のポイント
- 金利の低さ1
金利が低い借り換え住宅ローンとしてユーザーがとても満足できる基準を「検証した借り換え住宅ローンのなかで最も金利が低い商品」とし、以下の方法で各商品の検証を行いました。なお、デフォルトで表示される「おすすめ順」のランキングは、変動金利タイプにおける金利の低さで作成しています。2026年2月2日時点の情報をもとに検証を行なっています。
- がん団信の上乗せ金利の低さ2
がん団信の上乗せ金利が低い商品として、ユーザーがとても満足できる基準を「検証した住宅ローンのなかで最もがん団信の上乗せ金利が低い商品」とし、以下の方法で各商品の検証を行いました。2026年2月2日時点の情報をもとに検証を行なっています。
- 事務手数料の低さ3
事務手数料が低い商品として、ユーザーがとても満足できる基準を「検証した住宅ローンのなかで最も事務手数料が低い商品」とし、以下の方法で各商品の検証を行いました。2026年2月2日時点の情報をもとに検証を行なっています。
すべての検証は
マイベストが行っています

監修者は「選び方」についてのみ監修をおこなっており、掲載している商品・サービスは監修者が選定したものではありません。マイベストが独自に検証を行ったうえで、ランキング化しています。
更新 ランキングを更新しました。
住宅ローンは借り換えるべき?返済額はどれだけ変わるの?

結論、返済年数が10年・返済額が1,000万円以上残っているなら、返済負担が減る可能性が高いと言えます。住宅ローンの手数料は借入額によりますが、基本的に高額。しかし、借り換えによって低い金利が長期間適用されると、結果的に返済額を抑えることが可能です。この手数料と金利差の損益分岐点の目安が、返済年数10年・返済額1,000万円となります。
また、残りの返済期間が長く、借入残高が多いほど借り換えの効果が出やすくなります。たとえば、フラット35から別のフラット35に借り換えをした場合で見てみましょう。
2011年に最も高い金利でフラット35の買取型を借りると年2.63%、2024年11月時点で最も低いフラット35の買取型に借り換えると年1.84%が適用されます。現時点のローン残高が2,500万円の場合、借り換えの効果は以下のとおりです。
- 借り換えをしなかった場合に完済まで支払う金額:約3,218万円
- 借り換えした場合に完済まで払う金額:約3,060万円(約2,990万円(金利負担)+約70万円(手数料負担))
手数料は数十万円かかりますが、それでもトータルの返済額は150万円近く安くなります。とはいえ、借り換えで返済額が安くなるかどうかは人によって変わります。借り換えたい住宅ローンが決まったら、最後に必ずシミュレーションをしましょう。全国銀行協会のシミュレーターでは、今借りている住宅ローンと借り換えたい住宅ローンの金利や返済期間を入力すると、借り換えて損をしないか確認できますよ。

ネットでは、セオリーとして「残りの返済期間が10年以上・返済残高が1,000万円以上」というのが借り換えの目安として紹介されています。
しかし、必ずしもこの目安に当てはまらないと借り換えの効果が出ないというわけではありません。残りの返済期間や返済残高にかかわらず、シミュレーションをして返済負担が減るかどうかを確かめることが大切です。

ローン残高が1,000万円以上、返済期間が10年以上、金利差が0.5%以上であれば、借り換えることがおすすめです。とはいえ、この3つに当てはまらなくても効果はあがる可能性があります。借り換えの際は、複数の金融機関で見積もりを取り、手数料や総返済額を含めて比較しましょう。
住宅ローンの金利は今後上がる?下がる?

住宅ローンの金利は、現段階では上がっていく見通しです。日銀が2024年7月31日の会合で追加利上げを行うことを決定したため、政策金利と密接に関係している変動金利は上がる可能性が高いと言えるでしょう。
これまで日銀は長期金利を低く抑えるために、大規模な日本国債の借入をして金融緩和を行ってきました。しかし、2024年3月に金融緩和政策が修正され、実質的に短期金利の目標をマイナス金利からゼロ金利に変更すると決定。同年7月31日には変動金利に影響する短期金利の誘導目標が0.15%引き上げられ、さらに0.25%へ追加利上げを行うと決定されました。
固定金利に影響する長期金利も上昇する見込みです。これまで日本国債の大規模買い入れで金利上昇を抑えていましたが、今後は徐々に減額すると決定しました。今後は緩やかに長期金利が上昇すると考えられるため、固定金利も上がるでしょう。

金利が上がる局面になると変動金利から固定金利へと借り換えを検討する人も多いですが、繰り上げ返済も視野に入れるのがおすすめです。繰り上げ返済により残りの返済年数を減らすことで、将来大きく金利が上がる前に完済できる可能性が高まります。
固定金利は将来の金利上昇に備えられる点が魅力ですが、変動金利と比較すると金利は高めの設定です。そのため変動金利で借りていたときよりも月々の返済額が上がり、家計が圧迫されるリスクもあることは覚えておきましょう。

変動金利が上昇していくことは間違いないと言えるでしょう。
理由の一つは、日銀の植田総裁が今後政策金利を中立金利まで引き上げることを明言しているためです。いきなり大幅な利上げをすることは考えづらいですが、物価上昇や株価の変動などを踏まえて、段階的に1%程度まで引き上げることが予想されます。そのため、政策金利と密接に関連する変動金利もゆるやかに上昇していくといってよいでしょう。

変動金利は、金利の動きを継続して確認でき、資産運用などで備えられる人に向いています。あわせて、返済額が月2〜3万円増えても家計を維持できるかどうかも確認しておきましょう。これらの備えが難しい場合は、金利変動の影響を受けにくい固定金利を選ぶのがおすすめです。
借り換え住宅ローンの選び方
借り換え住宅ローンを選ぶ際に必ずチェックしておきたい「3つのポイント」をご紹介します。
まずは金利タイプを選ぶ。金利変動リスクと総返済額で考えよう

まずは金利タイプを選びましょう。変動金利・固定期間選択型・全期間固定(フラット35)がありますが、一概にどれがいいとは言えません。選ぶ金利タイプによって返済額が約500万円近く変わることもあるので、金利上昇のリスクもふまえて選んでくださいね。
低金利を重視するなら変動金利がおすすめ。ただし、リスクは最も高い

金利を下げたい人は、変動金利を選ぶのがおすすめです。2024年10月1日時点の変動金利の相場を見てみると、全期間固定金利と比較すると、変動金利を選ぶことで1~2%は金利が低くなります。
ただし、今後大幅な金利上昇が起きた場合、固定金利を上回る可能性も0ではありません。日本は1995年以降、基準金利が年2.0%程度で推移していますが、1990年頃の住宅ローン金利は年8.0%以上でした。20年後や30年後といった遠い将来については、上がるとも下がるとも予測できません。
急激な返済額の増加が心配なら、5年ルール・125%ルールがある住宅ローンを選ぶのがおすすめ。金利が上昇したタイミングから5年間は毎月の返済額が変わらず、6年目以降も毎月の返済額は前月の125%以上増やすことができません。ただし、総返済額は金利に応じて変わる点に注意しておきましょう。

変動金利を選ぶ場合は、リスクを理解したうえで判断することが重要。5年ルールや125%ルールによって返済額の急な上昇は抑えられますが、元本の減り方や総返済額の増え方には影響があります。
金利が1〜2%あがった場合の総返済額もあらかじめ試算し、家計への影響を把握しておくことが必要です。また、資産運用でローンの利回りを上回るような準備もあれば、変動金利の選択肢を検討しやすくなります。
返済額は抑えたいけど、金利変動のリスクに備えたいなら、固定金利選択型を選ぼう

変動のリスクに備えつつ金利を抑えたいなら、固定金利選択型を選びましょう。指定した期間金利が固定されるため、ライフプランにあわせて返済額を固定することができます。
金利は全期間固定より低く、変動金利より高め。ライフプランにあわせて返済計画を立てやすい全期間固定金利のメリットと、金利の低さが魅力の変動金利のメリットのいいとこ取りができます。
ただし、固定期間終了後は金利変動の影響を受けます。固定期間終了後は変動金利にするか再度固定金利にするかを選ぶことができますが、適用されるのは固定期間終了時の金利である点に注意しましょう。
固定される期間の選択肢は、2年・3年・5年・7年・10年・15年とさまざまです。パートナーが職場復帰する、車のローン返済が終わるなど、ライフプランにあわせて期間を選びましょう。

固定金利を選ぶなら、全期間固定がおすすめです。固定金利の大きなメリットである返済額の安定性を活かせるため、長期の返済計画も立てやすくなります。
ただし、40〜50歳でローン残年数が短い場合は10年固定、返済期間を短縮できる場合はフラット20も選択肢になります。変動と固定を組み合わせたMIXプランも理論上は有効ですが、無理に選ぶ必要はありません。固定期間を決める際は、金融機関のキャンペーンや短期的な金利だけで判断せず、自分のライフプランに合った期間を意識しましょう。
金利上昇が不安なら、全期間固定金利を。特にフラット35がおすすめ

金利変動のリスクに備えるなら、全期間金利が一定の全期間固定金利を選びましょう。返済金額が変わらないため、変動・固定と比較して金利変動のリスクが少ないですよ。
ただし、金利の相場は最も高く設定されています。変動金利タイプの相場が0.4%台であるのに対し、全期間固定の相場は2%台。総返済額に500万円近い差が出る可能性もあります。余剰資金が出たら繰り上げ返済をして返済年数を縮め、総返済額を減らすとよいでしょう。
金利をなるべく抑えたいなら、フラット35も候補としてください。民間の銀行が提供する全期間固定ローンは金利が年2.0%以上であることが多いのに対し、フラット35は年1.8%台と低めです。
残債2500万円・残り返済年数20年の場合を考えると、金利が0.2%違うだけで返済額で50万円以上の違いが生まれます。全期間固定金利を選ぶ際は、とくに金利差に注目しましょう。

団信は備えたいリスクに合わせて選ぼう。加入するならがん団信がおすすめ

どの団信に入ろうか迷っているなら、がん団信に申し込むのがおすすめです。理由は大きく分けて、以下の3つです。
- 一般団信は保障内容が不十分
- 三大・八大疾病だと上乗せ金利が高い
- 三大・八大疾病は保障の適用条件が厳しい
今やがんは2人に1人がかかる(※1)とされていますが、一般団信では100%の保障がつかないことがほとんど。さらに一般団信は保障される金額が返済額の50%と少ないのも難点です。がんになった際に返済が滞ってしまうリスクを考えると、がん団信には加入したほうがいいと言えるでしょう。
また、三大疾病・八大疾病は保障内容が充実しますが、上乗せ金利が年0.3%と高い傾向があります。返済が50〜60代前半で完了する場合は、返済中に心疾患や脳血管疾患で亡くなるリスクは、がんで亡くなるリスクと比較するとそこまで高くありません(※2)。がん団信でカバーできない範囲は、民間の保険で補うとよいでしょう。
さらに、がん団信は「診断時」に保障が適用されるのに対して、三大疾病・八大疾病は入院60〜180日と条件が厳しいのも特徴。たとえば心疾患の平均入院日数は24.6日(※3)で、発症しても保障を受けられない可能性もあります。
ただし、自分の身に何が起こるかはわかりません。「親族に過去大病を患った人がいる」など、健康リスクが高めだと感じている人は、三大疾病・八大疾病も視野に入れてくださいね。
1:国立がん研究センター「最新がん統計」
2:厚生労働省「令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況」
3:厚生労働省「令和2年(2020年)患者調査の概況」

団信のなかには、「50歳未満」などと年齢制限が設けられているものもあります。事前に保障対象の条件を確認するようにしましょう。とくに年齢を重ねてからのタイミングで借り換えをしようとしている人は注意してください。

金利の低さに加え、団信の条件面でもネット銀行が優れている傾向にあります。たとえば「auじぶん銀行」は上乗せ金利のないがん50%保障団信でも、脳卒中など5つの重大疾病について50%保障が付帯します。がん100%保障団信も上乗せ金利が0.05%と低く、少ない経済負担で充実した保障内容となっています。

団信の金利上乗せは0.1〜0.3%と小さく見えますが、借入額や返済期間によっては、総支払額で数百万円変わることもあります。例えば、3,000万円を35年で借りた場合、0.3%の上乗せは総額で200〜300万円程度の負担増につながるケースもあります。
重要なのは、その保障がないと家計が成り立たなくなるかどうかです。貯蓄や配偶者の収入、民間保険のカバー範囲を整理し、団信で上乗せすべき保障かどうかを判断しましょう。保障を手厚くすること自体は悪くありませんが、そのコストに見合うリスクかを数字で確認することが大切です。
手数料は気にせず選んで大丈夫。基本的にどの住宅ローンも変わらない

銀行ごとに手数料に大きな差はないので、気にしすぎる必要はありません。手数料の低さではなく、金利・団信の上乗せ金利から優先的に確認しましょう。
手数料定率型の場合、ほとんどの銀行で「(借入金額)×2.2%」と設定されていました。2,500万円を借り入れると想定して2.2%を掛けると、手数料は55万円です。
銀行によっては手数料が数万円異なる場合がありますが、金利差を考えると大きな差ではありません。最も高いりそな銀行でも、2.2%分に加えて保証会社事務取扱手数料が55,000円プラスされるだけです。残りの返済金額が高くない場合を除けば、それほど気にしなくてよいでしょう。
借り換え住宅ローン全15選
おすすめ人気ランキング
商品 | 画像 | おすすめ スコア | リンク | ポイント | おすすめスコア | こだわりスコア | 詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金利の低さ(変動) | がん団信の上乗せ金利の低さ | 事務手数料の低さ | 金利の低さ(固定10年) | 金利の低さ(35年・全期間固定) | 手数料 | 年収条件 | 勤続年数の条件 | 借り換え金利(変動) | 借り換え金利(固定10年) | 借り換え金利(35年・全期間固定) | 最長借り入れ期間 | 5年ルール/125%ルールあり | 団信の基本保障 | 団信の特約 | がん団信の上乗せ金利 | 繰り上げ返済の手数料 | ||||||
1 | auじぶん銀行 住宅ローン |  | 4.70 | 団信のコスパの充実度も重視するならコレ。保障が手厚い | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 2.20%(*3) | 前年度年収が200万円以上(自営業の場合は申告所得) | 年0.679%(*1) | 年1.595% | 年4.940% | 50年以内 | 死亡・高度障害保障、5つの重大疾病保障、全疾病入院保障、住宅ローン残高50%保障 | 住宅ローン残高100%保障 | 年0.05%(*2) | 無料 | |||
2 | PayPay銀行 住宅ローン |  | 4.54 | がん団信の上乗せ金利が低い。金利を抑えてがんに備えたい人に | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.48 | 4.15 | 2.20% | 前年度年収が200万円以上 | 年0.630% | 年2.270% | 年3.200% | 50年以内 | 死亡・高度障害保障、リビングニーズ保障、重度がん保障特約 | がん50%保障団信:死亡・高度障害保障、リビングニーズ保障、重度がん保障、がん保障(がん診断保障、がん先進医療特約)、全疾病保障(入院限定)、失業保障、自然災害保障/がん100%保障団信:死亡・高度障害保障、リビングニーズ保障、がん保障(がん診断保障、がん先進医療特約、がん診断時一時金保障)、全疾病保障(入院限定)、失業保障、自然災害保障 | 年0.15% | 一部繰上返済:無料(オンライン)、5,500円(電話)、 全額繰上返済:33,000円(電話) | |||
3 | SBI新生銀行 住宅ローン |  | 4.38 | がん団信を付帯して変動金利を検討中の人におすすめ。適用金利が低い | 4.32 | 4.34 | 5.00 | 4.30 | 4.00 | 2.20% | 前年度税込年収が300万円以上 | 自営業:業歴2年以上 | 年0.730%(*1) | 年2.500% | 年3.400% | 変動金利:50年(35年超は新規のみ選択でき、年0.1%金利上乗せ)、固定金利:35年 | 死亡・高度障害保障 | がん保障、リビング・ニーズ保障 | 年0.10% | 無料 | ||
4 | りそな銀行 りそな住宅ローン |  | 4.36 | 変動金利の低さを重視するなら。借り換えを対面で相談できる | 4.94 | 4.34 | 3.00 | 3.65 | 3.00 | 借入金額×2.2%、保証会社事務取扱手数料 55,000円 | 前年の税込年収が100万円以上 | 給与所得者の場合:1年以上/給与所得者以外の場合:3年以上 | 年0.640%(*1) | 年3.165% | 40年以内 | 死亡・高度障害保障 | がん保障特約:がん保障、死亡・高度障害保障/三大疾病保障特約:三大疾病、死亡・高度障害保障/団信革命:三大疾病、死亡・高度障害保障、病気・ケガの保障、所定の要介護状態保障 | 年0.10% | 一部繰上返済:無料(オンライン)、5,500円(窓口) 全額繰上返済:11,000円(窓口) | |||
5 | 住信SBIネット銀行 Web申込コース |  | 4.30 | 金利の低さと団信の充実度が強み。3大疾病に備えられる | 4.87 | 3.67 | 5.00 | 4.34 | 4.18 | 2.20% | 年0.650% | 年2.449% | 年3.159% | 50年以内 | 3大疾病保障、全疾病保障、死亡保障、高度障害保障、リビングニーズ特約、就業不能状態を保障、重度ガン保険金前払特約、先進医療特約(50歳以下のみ) | 住宅ローン残高100%保障 | 年0.20% | 無料 | ||||
6 | イオン銀行 住宅ローン(手数料定率型) |  | 4.20 | イオングループでの買い物がお得に。がん団信の金利は年0.1% | 3.98 | 4.34 | 5.00 | 4.06 | 3.00 | 借入金額×2.2%(最低取扱手数料220,000円) | 前年度年収100万円以上 | 年0.780% | 年2.800% | 50年以内 | 死亡・高度障害保障、病気、ケガ | がん保障、8大疾病保障 | 年0.10% | 一部繰上返済:無料 全額繰上返済:55,000円 | ||||
7 | みずほ銀行 住宅ローン |  | 4.05 | 全期間固定金利・10年固定金利はやや高め。がん団信の金利はお得 | 4.00 | 4.34 | 3.40 | 4.10 | 4.05 | 借入金額×2.2%、事務手数料 33,000円 | 年0.775% | 年2.750% | 年3.340% | 35年以内 | 死亡・高度障害保障 | がん保障、7大疾病保障、8大疾病保障、その他のケガ・病気 | 年0.10% | 一部繰上返済:無料(オンライン)、33,000円(窓口) 全額繰上返済:33,000円(窓口) | ||||
8 | 横浜銀行 住宅ローン |  | 3.87 | 金利は高め。神奈川県・東京都在住なら検討の価値あり | 4.18 | 3.67 | 3.40 | 4.00 | 3.88 | 借入金額×2.2%、不動産担保取扱手数料 33,000円 | 年0.750% | 年2.875% | 年3.600% | 35年以内 | 死亡・高度障害保障、残債一括返済保証、ご遺族・ご家族サポート | がん保障特約付き団信:がん保障、月額返済支援保障、一時金保障/3⼤疾病保障特約付き:がん保障、三大疾病保障、ご遺族・ご家族サポート | 年0.20% | 一部繰上返済:無料(オンライン)、44,000円(窓口)、 全額繰上返済:無料(オンライン)、44,000円(窓口) | ||||
9 | 住信SBIネット銀行 フラット35(保証型) |  | 3.62 | がん団信の上乗せ金利がかからない。全期間固定を検討しているなら | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.88 | 融資金額×2.2%(最低額:110,000円) | 年間返済額の年収に占める割合が30%以下の場合:年収400万円未満/年間返済額の年収に占める割合が35%以下の場合:年収400万円以上 | 年2.230% | 35年 | 死亡・高度障害保障、リビング・ニーズ特約、がん保障(無担保住宅ローンの場合)、先進医療、全疾病 | 一部繰上返済:無料、全額繰上返済:33,000円 | |||||||
10 | ソニー銀行 住宅ローン |  | 3.60 | どのタイプも金利が高め。5年ルール・125%ルールもない | 3.12 | 4.34 | 5.00 | 3.47 | 3.33 | 2.20% | 前年度の年収が400万円以上(自営業者の場合、前年度の申告所得もしくは直近3期分の平均申告所得のいずれか低い所得が400万円以上) | 年0.997%(*1) | 年3.318%(*2) | 年4.435% | 35年以内 | がん保障、給付金、死亡保障、高度障害保障、リビング・ニーズ保障 | 3大疾病団信:急性心筋梗塞・脳卒中保障/生活習慣病団信:生活習慣病長期入院時保障 | 年0.10% | 無料 | |||
auじぶん銀行住宅ローン

| 借り換え金利(変動) | 年0.679%(*1) |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | 年1.595% |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | 年4.940% |
| がん団信の上乗せ金利 | 年0.05%(*2) |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 無料
団信のコスパの充実度も重視するならコレ。保障が手厚い
auじぶん銀行の「auじぶん銀行 住宅ローン」は、がん団信の保障が充実しているものがよい人におすすめです。
変動金利は年0.679%と、平均よりやや低めでした。金利が上昇しても5年間は金利が変わらない5年ルールや、6年目以降も元の返済額の125%までしか返済額が増えることがない125%ルールも備わっています。10年固定金利は年1.595%と、比較した商品のなかでは最も低い数値でした。
加えて、がん団信の上乗せ金利の低さ・団信保障の充実度も大きなメリット。「がん100%保障団信」に加入すると、わずか年0.05%の上乗せ金利でがんに備えられます。加えて、団信の基本保障に死亡・高度障害・リビングニーズ特約がついているのが特徴的。リビングニーズ特約によって、万が一余命6か月と診断された場合は住宅ローン残高が0円になります。
ただし全期間固定金利は年4.940%と高めな点には要注意。契約時に返済額を確定して返済計画を立てたいと考える人には不向きでしょう。
また、事務手数料は借入金額の2.2%で算出され、比較した大半の商品と同程度です。全期間固定金利は高めでしたが、一方で変動金利・10年固定金利は検証したなかで低めの金利だったので、変動金利・固定金利でコスパの充実度も重視して検討するなら選択肢に入る住宅ローンです。
良い
- がん団信の上乗せ金利が年0.05%と低い
- 10年固定金利が年1.595%と比較したなかでも最も低い
- 変動金利が年0.679%と平均よりやや低め
気になる
- 全期間固定35年の金利が年4.940%と高め
| 手数料 | 2.20%(*3) |
|---|---|
| 年収条件 | 前年度年収が200万円以上(自営業の場合は申告所得) |
| 勤続年数の条件 | |
| 最長借り入れ期間 | 50年以内 |
| 団信の基本保障 | 死亡・高度障害保障、5つの重大疾病保障、全疾病入院保障、住宅ローン残高50%保障 |
| 団信の特約 | 住宅ローン残高100%保障 |
本注釈においては事業者からの情報提供を含みます
PayPay銀行住宅ローン

| 借り換え金利(変動) | 年0.630% |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | 年2.270% |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | 年3.200% |
| がん団信の上乗せ金利 | 年0.15% |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 一部繰上返済:無料(オンライン)、5,500円(電話)、 全額繰上返済:33,000円(電話)
がん団信の上乗せ金利が低い。金利を抑えてがんに備えたい人に
PayPay銀行の住宅ローンは、金利を抑えてがん団信に加入できる住宅ローンを探している人におすすめです。
「がん100%保障団信」の上乗せ金利は年0.15%と、比較した商品のなかでは低め。返済の負担は少ないながらも、しっかりがんに備えられます。
また、10年固定金利は年2.270%と、比較したなかでも低めでした。全期間固定は年3.200%で、比較したなかでは若干低めです。短期間の固定金利で支払いペースを安定させたい人にとっては魅力的な住宅ローンといえます。
さらに、変動金利も年0.630%と比較したなかでも最も低金利でした。一方で、金利が上昇した際の5年ルール・125%ルールがない点には注意しましょう。
事務手数料は借入金額×2.2%で算出され、標準的な水準といえます。変動金利も固定金利も検証したなかで低めの金利だったので、どんな人にも借り換えを検討して欲しい住宅ローンといえます。
良い
- がん団信の上乗せ金利が年0.15%と低め
- 変動金利・10年固定・全期間固定金利ともに低めの水準
気になる
- 変動金利に5年ルール・125%ルールがついていない
| 手数料 | 2.20% |
|---|---|
| 年収条件 | 前年度年収が200万円以上 |
| 勤続年数の条件 | |
| 最長借り入れ期間 | 50年以内 |
| 団信の基本保障 | 死亡・高度障害保障、リビングニーズ保障、重度がん保障特約 |
| 団信の特約 | がん50%保障団信:死亡・高度障害保障、リビングニーズ保障、重度がん保障、がん保障(がん診断保障、がん先進医療特約)、全疾病保障(入院限定)、失業保障、自然災害保障/がん100%保障団信:死亡・高度障害保障、リビングニーズ保障、がん保障(がん診断保障、がん先進医療特約、がん診断時一時金保障)、全疾病保障(入院限定)、失業保障、自然災害保障 |
SBI新生銀行住宅ローン

| 借り換え金利(変動) | 年0.730%(*1) |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | 年2.500% |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | 年3.400% |
| がん団信の上乗せ金利 | 年0.10% |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 無料
がん団信を付帯して変動金利を検討中の人におすすめ。適用金利が低い
SBI新生銀行の住宅ローンは、がん団信を付帯した変動金利を検討中の人におすすめです。
変動金利は年0.730%と、比較したなかではやや低め。「がん団信」の上乗せ金利も年0.1%と低めです。万が一がんになった際は住宅ローン残高が100%保障されるため、収入減による負担を抑えられます。ただし、金利が上がった際に負担を抑えられる5年ルール・125%ルールはありません。
固定金利10年も年2.500%と低めの水準でした。事務手数料も他社と大差はなく、借入金額の2.2%を支払う形式です。
全期間固定金利は年3.400%と平均より高いですが、10年先のライフプランを考慮するなら、有力な候補となるでしょう。
良い
- 10年固定金利が年2.500%と、比較した平均より低い
- がん団信の上乗せ金利が年0.1%と低く、リスクに備えられる
気になる
- 5年ルール・125%ルールがないため、金利上昇時の返済負担が大きくなる可能性がある
| 手数料 | 2.20% |
|---|---|
| 年収条件 | 前年度税込年収が300万円以上 |
| 勤続年数の条件 | 自営業:業歴2年以上 |
| 最長借り入れ期間 | 変動金利:50年(35年超は新規のみ選択でき、年0.1%金利上乗せ)、固定金利:35年 |
| 団信の基本保障 | 死亡・高度障害保障 |
| 団信の特約 | がん保障、リビング・ニーズ保障 |
本注釈においては事業者からの情報提供を含みます
りそな銀行りそな住宅ローン

| 借り換え金利(変動) | 年0.640%(*1) |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | 年3.165% |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | |
| がん団信の上乗せ金利 | 年0.10% |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 一部繰上返済:無料(オンライン)、5,500円(窓口) 全額繰上返済:11,000円(窓口)
変動金利の低さを重視するなら。借り換えを対面で相談できる
りそな銀行の「りそな住宅ローン」は、変動金利の低さを重視しつつ、店舗で直接相談しながら住宅ローンに借り換えたい人におすすめです。
変動金利は年0.640%と、平均より低めの金利でした。その上、5年ルール・125%ルールが設けられているため、金利が急上昇したとしても返済額をある程度抑えられますよ。また、がんになった際に住宅ローン残高がすべて保障される「がん保障特約」の上乗せ金利が年0.1%と低いのもポイントです。
一方、10年固定金利は年3.165%と比較したなかではやや高めです。固定金利を希望する人にはあまり向きません。
事務手数料としては、融資手数料の「借入金額×2.2%」に加え、保証会社事務取扱手数料として55,000円がかかる形式。検証した15社のなかではやや高めの水準でした。しかし全国各地に店舗を設けており、対面で相談できるため不安点を解消しやすいのは強み。納得して借り換えを進めたい人にとっては、有力な候補となるでしょう。
良い
- 変動金利の金利が低め
- がん保障特約の上乗せ金利が年0.1%と低い
- 全国各地に店舗があり、対面相談が可能
気になる
- 10年固定金利が高め
- 事務手数料がやや高め
| 手数料 | 借入金額×2.2%、保証会社事務取扱手数料 55,000円 |
|---|---|
| 年収条件 | 前年の税込年収が100万円以上 |
| 勤続年数の条件 | 給与所得者の場合:1年以上/給与所得者以外の場合:3年以上 |
| 最長借り入れ期間 | 40年以内 |
| 団信の基本保障 | 死亡・高度障害保障 |
| 団信の特約 | がん保障特約:がん保障、死亡・高度障害保障/三大疾病保障特約:三大疾病、死亡・高度障害保障/団信革命:三大疾病、死亡・高度障害保障、病気・ケガの保障、所定の要介護状態保障 |

りそな銀行 りそな住宅ローン(変動金利)の口コミ・評判は?金利や手数料を調査してよい点気になる点を解説!
本注釈においては事業者からの情報提供を含みます
住信SBIネット銀行Web申込コース

| 借り換え金利(変動) | 年0.650% |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | 年2.449% |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | 年3.159% |
| がん団信の上乗せ金利 | 年0.20% |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 無料
金利の低さと団信の充実度が強み。3大疾病に備えられる
住信SBIネット銀行のWeb申込コースは、金利の低さと団信の手厚さを重視する人におすすめです。
変動金利は年0.650%と、比較したなかでは低め。5年ルール・125%ルールがついているため、金利が上昇した際の負担を軽減できるのもメリットです。
10年固定金利は年2.449%・全期間固定金利は年3.159%。とくに10年固定金利は、比較した商品のなかでも低めに設定されています。固定金利はどのプランであっても低金利なので、幅広い借り換えニーズに応えてくれる住宅ローンといえます。
事務手数料は借入金額の2.2%と、高くも安くもない水準。また、がんになった際に住宅ローン残高が100%免除される「3大疾病100プラン」は、上乗せ金利が年0.2%とやや高めです。ただし保障範囲は広く、がんに加えて脳卒中・急性心筋梗塞にも対応しています。幅広いリスクに備えたい人には選択肢となるでしょう。
良い
- どの金利タイプも金利が低く、お得に借り換えられる
- 充実の保障で、がん・脳卒中・急性心筋梗塞の3大疾病に備えられる
気になる
- がん団信の上乗せ金利が年0.2%と高め
| 手数料 | 2.20% |
|---|---|
| 年収条件 | |
| 勤続年数の条件 | |
| 最長借り入れ期間 | 50年以内 |
| 団信の基本保障 | 3大疾病保障、全疾病保障、死亡保障、高度障害保障、リビングニーズ特約、就業不能状態を保障、重度ガン保険金前払特約、先進医療特約(50歳以下のみ) |
| 団信の特約 | 住宅ローン残高100%保障 |
イオン銀行住宅ローン(手数料定率型)

| 借り換え金利(変動) | 年0.780% |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | 年2.800% |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | |
| がん団信の上乗せ金利 | 年0.10% |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 一部繰上返済:無料 全額繰上返済:55,000円
イオングループでの買い物がお得に。がん団信の金利は年0.1%
イオン銀行の「イオン銀行 住宅ローン(手数料定率型)」は、日常的にイオンでお買い物をする人におすすめです。
変動金利は年0.780%と、比較したなかでも平均よりやや高めに設定されています。金利上昇時の負担を抑える5年ルール・125%ルールは設けられていないので、急激な金利変動の影響は緩和できない点にも注意が必要です。「イオンセレクトクラブ」の特典として、住宅ローンを完済するまでイオングループでの買い物が5%引きになります。
「がん保障付住宅ローン(がん団信)」の上乗せ金利は年0.1%。比較した商品内でも軽めの負担でがんに備えられます。また、10年固定金利は年2.800%と高めの水準で、全期間固定金利の取り扱いがない点には注意が必要です。
事務手数料は取引金額×2.2%で求める形式と、比較した大半の商品と同じで、特別デメリットにはなりません。日常的にイオンで買い物をする人にとっては候補となる住宅ローンです。
良い
- がん団信の上乗せ金利が年0.1%と低負担
- イオングループでの買い物が5%引きになる
気になる
- 全期間固定金利の取り扱いがない
- 変動金利に5年ルール・125%ルールがなく、金利上昇時には負担が多くなる可能性がある
- 変動金利が年0.780%と平均より若干高め
| 手数料 | 借入金額×2.2%(最低取扱手数料220,000円) |
|---|---|
| 年収条件 | 前年度年収100万円以上 |
| 勤続年数の条件 | |
| 最長借り入れ期間 | 50年以内 |
| 団信の基本保障 | 死亡・高度障害保障、病気、ケガ |
| 団信の特約 | がん保障、8大疾病保障 |
みずほ銀行住宅ローン

| 借り換え金利(変動) | 年0.775% |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | 年2.750% |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | 年3.340% |
| がん団信の上乗せ金利 | 年0.10% |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 一部繰上返済:無料(オンライン)、33,000円(窓口) 全額繰上返済:33,000円(窓口)
全期間固定金利・10年固定金利はやや高め。がん団信の金利はお得
みずほ銀行の住宅ローンは、変動金利タイプでの借り換えを検討している人におすすめです。
全期間固定金利は年3.340%・10年固定金利も2.750%で、平均よりやや高めの水準に設定されていました。
変動金利も年0.775%と平均より若干高めの水準である一方、がん団信の上乗せ金利は年0.1%と比較した商品のなかでは低いほうでした。5年ルール・125%ルールがついているため毎月の返済額が急激に変動することはありませんが、合計の返済額は金利が変動した分多くなります。
事務手数料は、借入金額の2.2%に加え事務手数料33,000円が設定されています。変動金利での契約を考えている人にとっては候補のひとつとなるでしょう。
良い
- がん団信の上乗せ金利が年0.1%と高くない
気になる
- 全期間固定金利は年3.340%・10年固定金利も2.750%で、平均よりやや高め
| 手数料 | 借入金額×2.2%、事務手数料 33,000円 |
|---|---|
| 年収条件 | |
| 勤続年数の条件 | |
| 最長借り入れ期間 | 35年以内 |
| 団信の基本保障 | 死亡・高度障害保障 |
| 団信の特約 | がん保障、7大疾病保障、8大疾病保障、その他のケガ・病気 |
横浜銀行住宅ローン

| 借り換え金利(変動) | 年0.750% |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | 年2.875% |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | 年3.600% |
| がん団信の上乗せ金利 | 年0.20% |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 一部繰上返済:無料(オンライン)、44,000円(窓口)、 全額繰上返済:無料(オンライン)、44,000円(窓口)
金利は高め。神奈川県・東京都在住なら検討の価値あり
横浜銀行の「横浜銀行 住宅ローン(融資手数料型)」は、神奈川県・東京都エリアに住んでいる人におすすめです。
変動金利は年0.750%と平均より低いうえ、5年ルール・125%ルールがついているため万が一急激な金利上昇が起きても負担を抑えられます。とはいえ、10年固定金利は年2.875%・全期間固定金利も年3.600%と、比較したなかでは高めの水準です。
また、がんになった際に住宅ローン残高を100%保障されるためには「ガン保障特約付き団体信用生命保険」に加入する必要があり、上乗せ金利が年0.2%とやや高めなのもネックです。手数料には借入金額の2.2%に加え、不動産担保取扱手数料33,000円が設定されています。
とはいえ、地方銀行のなかでは変動金利・全期間固定金利が低く設定されているため、横浜銀行が店舗を展開する神奈川県・東京都エリア在住ならぜひ候補に入れて検討してみてください。
良い
- 特になし
気になる
- がんになった際に住宅ローン残高の100%保障を受けるには、上乗せ金利年0.2%が必要
- 10年固定・全期間固定金利ともに高めの水準
| 手数料 | 借入金額×2.2%、不動産担保取扱手数料 33,000円 |
|---|---|
| 年収条件 | |
| 勤続年数の条件 | |
| 最長借り入れ期間 | 35年以内 |
| 団信の基本保障 | 死亡・高度障害保障、残債一括返済保証、ご遺族・ご家族サポート |
| 団信の特約 | がん保障特約付き団信:がん保障、月額返済支援保障、一時金保障/3⼤疾病保障特約付き:がん保障、三大疾病保障、ご遺族・ご家族サポート |
住信SBIネット銀行フラット35(保証型)

| 借り換え金利(変動) | |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | 年2.230% |
| がん団信の上乗せ金利 |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 一部繰上返済:無料、全額繰上返済:33,000円
がん団信の上乗せ金利がかからない。全期間固定を検討しているなら
住信SBIネット銀行の「住信SBIネット銀行 フラット35(保証型)」は、返済負担の軽いフラット35を探している人におすすめ。
がん団信の上乗せ金利は年0%と、今回検証した商品のなかでは圧倒的な低さでした。負担がかからない点が最大の魅力です。金利は年2.230%と、フラット35のなかでは低めの設定です。団信と金利の合計コストの安さから、全期間固定を検討している人にとっては第一候補となる住宅ローンです。
事務手数料は借入金額の2.2%を支払う形式。ほかの銀行と比較すると高くも安くもない水準です。
金利と団信の上乗せ金利を合わせた際の返済負担の少なさが強みなので、フラット35を検討している人だけでなく、民間の全期間固定住宅ローンで悩んでいる人にとっても十分選択肢になる住宅ローンです。
良い
- 団信の上乗せ金利が年0%と、負担がかからない
気になる
- 特になし
| 手数料 | 融資金額×2.2%(最低額:110,000円) |
|---|---|
| 年収条件 | 年間返済額の年収に占める割合が30%以下の場合:年収400万円未満/年間返済額の年収に占める割合が35%以下の場合:年収400万円以上 |
| 勤続年数の条件 | |
| 最長借り入れ期間 | 35年 |
| 団信の基本保障 | 死亡・高度障害保障、リビング・ニーズ特約、がん保障(無担保住宅ローンの場合)、先進医療、全疾病 |
| 団信の特約 |
ソニー銀行住宅ローン

| 借り換え金利(変動) | 年0.997%(*1) |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | 年3.318%(*2) |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | 年4.435% |
| がん団信の上乗せ金利 | 年0.10% |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 無料
どのタイプも金利が高め。5年ルール・125%ルールもない
ソニー銀行の住宅ローンは、固定金利の高さがネックです。
がんになった際に住宅ローン残高が100%保障される「がん団信100」の上乗せ金利が年0.1%と低いのは利点といえます。事務手数料は融資金額の2.2%と設定されており、標準的。他社と比べても特別高くはありませんでした。
一方、変動・固定金利の高さが気になるポイントでした。変動金利は年0.997%と検証した15商品のなかでも高めの水準で、金利が上がった際の返済負担を一時的に和らげる5年ルール・125%ルールもありません。10年固定金利は年3.318%・全期間固定金利は年4.435%と、いずれの金利も比較した商品のなかでは高めの設定なので、返済負担を軽くするための借り換え先としてはおすすめできません。
がん団信のお得感はあるものの、総合的に見ると返済額を減らせない可能性が高いでしょう。
良い
- がん団信の上乗せ金利が年0.1%と低い
気になる
- 変動金利・10年固定金利・全期間固定のいずれも金利が高い
| 手数料 | 2.20% |
|---|---|
| 年収条件 | 前年度の年収が400万円以上(自営業者の場合、前年度の申告所得もしくは直近3期分の平均申告所得のいずれか低い所得が400万円以上) |
| 勤続年数の条件 | |
| 最長借り入れ期間 | 35年以内 |
| 団信の基本保障 | がん保障、給付金、死亡保障、高度障害保障、リビング・ニーズ保障 |
| 団信の特約 | 3大疾病団信:急性心筋梗塞・脳卒中保障/生活習慣病団信:生活習慣病長期入院時保障 |
本注釈においては事業者からの情報提供を含みます
三菱UFJ銀行住宅ローン

| 借り換え金利(変動) | 年0.745% |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | 年2.750% |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | 年3.460% |
| がん団信の上乗せ金利 | 年0.30% |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 一部繰上返済:無料(オンライン)、16,500円(窓口)、 全額繰上返済:16,500円(オンライン)、33,000円(窓口)
変動金利の低さが魅力。がん保障はやや高め
三菱UFJ銀行の「三菱UFJ銀行 住宅ローン」は、変動金利での借り換えを検討している人におすすめ。
10年固定金利が年2.750%・35年全期間固定金利が年3.460%と比較したなかでは高めでした。
変動金利プランの金利は年0.745%とやや低めで、金利が上がった場合でも負担を抑えられる5年ルール・125%ルールつき。どのタイプであっても、借り換えによる満足度が高いといえます。事務手数料は借入金額の2.2%と、他社と比べても標準的な設定なので、とくに不満はないでしょう。
ただし、がんと診断された際に手厚い保障を受けるには「7大疾病100%」プランや「全疾病100%」プランへの加入が必要で、上乗せ金利は7大疾病100%プランでも年0.3%と高いのがネックです。保障は充実していますが、合計金利はしっかりチェックしましょう。
良い
- 変動金利が低めの設定でお得に借り換えられる
気になる
- がん100%保障を受けるためには、上乗せ金利が年0.3%と高め
| 手数料 | 2.20%(*1) |
|---|---|
| 年収条件 | 200万円以上 |
| 勤続年数の条件 | 満1年以上 |
| 最長借り入れ期間 | 35年以内 |
| 団信の基本保障 | 死亡・高度障害保障 |
| 団信の特約 | 3大疾病保障:住宅ローン残高50%保障/7大疾病保障:住宅ローン残高100%保障/全疾病保障:住宅ローン残高100%保障/保険料支払型:全疾病保障(住宅ローン残高100%保障)、総合先進医療特約、女性疾病特約(オプション) |
本注釈においては事業者からの情報提供を含みます
ARUHI 住宅ローンスーパーフラット(保証型)

| 借り換え金利(変動) | |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | 年2.060%(*1) |
| がん団信の上乗せ金利 | 年0.15% |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 一部繰上返済:無料(オンライン)、11,000円(電話・期間短縮型) 全額繰上返済:55,000円(窓口)
金利の低いフラット35を探している人なら候補になる
ARUHIの「スーパーフラット」は、保証型のフラット35で全期間固定金利の住宅ローン。
事務手数料は借入金額×2.2%と設定されており、今回検証したほかの多くの住宅ローンと同じ水準です。「がん団信プラス」の上乗せ金利は年0.15%と、比較したなかでは高くも安くもありません。しかしがんと診断された際に住宅ローン残高が全額保障されるメリットは大きく、許容範囲といえます。
全期間固定金利の低さも強みです。年2.060%と、全期間固定タイプで比較したなかで最も低い金利です。フラット35への借り換えを検討中なら、候補のひとつになります。
良い
- 金利が年2.060%と低め
- がん団信プラスの上乗せ金利が年0.15%と高くはない
気になる
- 特になし
| 手数料 | 融資金額×2.2%(最低額:220,000円) |
|---|---|
| 年収条件 | 総返済負担率20%以下の場合:年収400万円未満・年収400万円以上 |
| 勤続年数の条件 | |
| 最長借り入れ期間 | 15年 |
| 団信の基本保障 | 死亡・高度障害保障,リビングニーズ(余命宣告) |
| 団信の特約 | 一般団信:死亡・高度障害保障、リビング・ニーズ保障/がん団信:死亡・高度障害保障、リビング・ニーズ保障、がん保障(ローン残高50%保障)/がん団信プラス:死亡・高度障害保障、リビング・ニーズ保障、がん保障(ローン残高100%保障、診断給付金)/生活習慣団信:死亡・高度障害保障、リビング・ニーズ保障、がん保障(ローン残高100%保障、診断給付金)、病気・ケガによる入院 |
本注釈においては事業者からの情報提供を含みます
住信SBIネット銀行フラット35(買取型)

| 借り換え金利(変動) | |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | 年2.370% |
| がん団信の上乗せ金利 | 年0.24% |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 無料
がん団信の上乗せ金利・事務手数料のいずれも安くはない
住信SBIネット銀行の「住信SBIネット銀行 フラット35(買取型)」は、借り換えの決め手に欠けます。
金利は年2.370%と、比較したフラット35のなかでは若干高めの設定。がんに備えるためには「新3大疾病付機構団信」に加入する必要があり、上乗せ金利は年0.24%と比較したなかでは高めでした。団信の上乗せ金利を含めて合計で考えると、低金利とはいえません。
事務手数料は借入金額の2.2%と標準的。金利・がん団信の上乗せ金利・事務手数料の3つの点で強みはありませんでした。フラット35へと借り換えしたいなら、ほかの商品を検討したほうがよいでしょう。
良い
- 特になし
気になる
- がん団信の上乗せ金利が年0.24%とやや高め
| 手数料 | 融資金額×2.2%(最低額:110,000円) |
|---|---|
| 年収条件 | 年間返済額の年収に占める割合が30%以下の場合:年収400万円未満/年間返済額の年収に占める割合が35%以下の場合:年収400万円以上 |
| 勤続年数の条件 | |
| 最長借り入れ期間 | 35年 |
| 団信の基本保障 | 新機構団信:死亡・身体障害 |
| 団信の特約 | 新3大疾病付 機構団信:死亡・身体障害・3大疾病・要介護状態 |
ARUHI 住宅ローンフラット35(買取型)

| 借り換え金利(変動) | |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | 年2.370%(*1) |
| がん団信の上乗せ金利 | 年0.24% |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 無料
事務手数料は平均的。初期費用を抑えたいなら
ARUHIの「フラット35」は、全期間固定金利における金利の低さを重視する人におすすめです。
事務手数料は借入金額の2.2%で、他行と同等の初期費用がかかります。金利は年2.370%で比較した全期間固定金利のなかでは低金利ですが、フラット35としてはやや高めです。
がんになった際にローン残高の100%を保障する「新3大疾病付機構団信」の上乗せ金利は年0.24%と、やや高めの設定でした。ただしがんだけでなく、3大疾病まで保障される点は魅力といえます。
どうしても金利を抑えたいニーズがある人にとっては、選択肢になる住宅ローンといえます。
良い
- 全期間固定金利のなかでは金利年2.370%と低い
気になる
- がん100%保障を受けるためには、上乗せ金利が高め
| 手数料 | 融資金額×2.2%(最低額:220,000円) |
|---|---|
| 年収条件 | 総返済負担率30%以下の場合:年収400万円未満/総返済負担率35%以下の場合:年収400万円以上 |
| 勤続年数の条件 | |
| 最長借り入れ期間 | 35年 |
| 団信の基本保障 | 死亡保障・身体障害保障 |
| 団信の特約 | 死亡保障、身体障害保障、3大疾病保障、介護保障 |
本注釈においては事業者からの情報提供を含みます
三井住友銀行住宅ローン

| 借り換え金利(変動) | 年1.025% |
|---|---|
| 借り換え金利(固定10年) | 年3.700% |
| 借り換え金利(35年・全期間固定) | 年4.080% |
| がん団信の上乗せ金利 | 年0.30% |
- 5年ルール/125%ルールあり
- 繰り上げ返済の手数料
- 一部繰上返済:無料(オンライン)、16,500円(窓口)、 全額繰上返済:無料(オンライン)、33,000円(窓口)
保障の手厚さは魅力だが、団信の上乗せ金利を含むと高金利
変動金利タイプには金利上昇時の負担を抑える5年ルール・125%ルールがついているものの、金利は年1.025%と比較したなかでも最も高い結果に。10年固定金利は年3.700%・全期間固定金利は年4.080%と、いずれも比較した商品の平均を上回りました。
「8大疾病保障付住宅ローン」に加入することで、がんになった際に住宅ローン残高が100%保障されます。ただし、上乗せ金利は年0.3%と高めなので、住宅ローン金利がやや高めであることを踏まえると、返済負担が重くなる可能性が高いといえるでしょう。
事務手数料としてかかる費用は取引金額の2.2%と標準的。金利の低さを求めるなら向いていませんが、幅広い保障を求めるなら、一考してもよい住宅ローンといえます。
良い
- 8大疾病保障付住宅ローンに加入すると幅広い保障を受けられる
気になる
- 変動金利・10年固定金利・全期間固定金利はいずれも高めの金利設定
- 8大疾病保障付加入時の上乗せ金利が年0.3%と高い
| 手数料 | 2.20% |
|---|---|
| 年収条件 | |
| 勤続年数の条件 | |
| 最長借り入れ期間 | 35年以内 |
| 団信の基本保障 | 死亡・高度障害保障 |
| 団信の特約 | 8大疾病保障、日常のケガ・病気保障、自然災害保障(web申し込み専用) |
人気の借り換え住宅ローン15商品を徹底比較!

そんなベストな借り換え住宅ローンを探すために、人気の借り換え住宅ローン15商品を集め、以下3つのポイントから徹底検証しました。
検証①:金利の低さ
検証②:がん団信の上乗せ金利の低さ
検証③:事務手数料の低さ
今回検証した商品
- ARUHI 住宅ローン|フラット35(買取型)
- ARUHI 住宅ローン|スーパーフラット(保証型)
- PayPay銀行|住宅ローン
- SBI新生銀行|住宅ローン
- auじぶん銀行|住宅ローン
- みずほ銀行|住宅ローン
- りそな銀行|りそな住宅ローン
- イオン銀行|住宅ローン(手数料定率型)
- ソニー銀行|住宅ローン
- 三井住友銀行|住宅ローン
- 三菱UFJ銀行|住宅ローン
- 住信SBIネット銀行|Web申込コース
- 住信SBIネット銀行|フラット35(保証型)
- 住信SBIネット銀行|フラット35(買取型)
- 横浜銀行|住宅ローン
金利の低さ

なお、デフォルトで表示される「おすすめ順」のランキングは、変動金利タイプにおける金利の低さで作成しています。
2026年2月2日時点の情報をもとに検証を行なっています。
スコアリング方法
変動金利タイプ・固定10年タイプ・全期間固定タイプの借り換え住宅ローンについて、金利を公式サイトで調査。調査した金利を低いものほど高評価として点数付けを行いました。
検証条件
- 最大限金利が割引されたときの数値を採用
- フラット35は全期間固定タイプとして金利の低さを検証
- 融資手数料型を採用
- 固定金利は当初引き下げ型を採用
がん団信の上乗せ金利の低さ

2026年2月2日時点の情報をもとに検証を行なっています。
スコアリング方法
検証条件
- がんになった際に、住宅ローンの返済負担が100%保障される団信が対象
- 「がん団信」の単独の取扱がない場合は、がんになった際に100%住宅ローンが保障される団信のなかで最も上乗せ金利の低いものを採用
事務手数料の低さ

2026年2月2日時点の情報をもとに検証を行なっています。
スコアリング方法
検証条件
- 借入金額の一定の割合を手数料として支払う「手数料定率型」にて算出
- 申込金額:2,500万円
住宅ローンを借り換えるのにおすすめの銀行は?

住宅ローンを借り換えるなら、金利が低い傾向にあるネット銀行がおすすめです。団信の保障内容も充実している傾向があり、高すぎない上乗せ金利で万が一の事態に備えられます。
ネット銀行であれば手続きをインターネットで完結させられることが多く、利便性も高いですよ。
住宅ローンの借り換えはいつから可能?

住宅ローンを借りた後は、どのタイミングでも借り換えが可能です。制限はないので、借りてからすぐに借り換えをしても問題ありません。
住宅ローンの借り換えを同じ銀行でするのは大丈夫?

銀行を変えずに返済負担を軽減する方法は、下記コンテンツで確認してみてくださいね。
住宅ローンを借り換えるメリット・デメリットは?

ただし、シミュレーションをせずに金利の低さにつられて借り換えをすると、損をするリスクがあります。とくに残りの返済年数が少ない人は、借り換えの効果が出にくいでしょう。借り換えには手数料などの諸費用もかかるため、金利が低い住宅ローンを借り換えてもトータルの返済負担が増える場合もあります。
詳しいメリット・デメリットや具体的な借り換えの方法は、下記コンテンツをチェックしてみてくださいね。
住宅ローンにかかる手数料は?

借り換えの手続きでは保証料や事務手数料、契約中の住宅ローンを完済するための全額繰上返済手数料・保証会社事務手数料などの支払いが発生します。登記の手続きも必要になるため、抵当権抹消費用・抵当権設定費用を負担しなければなりません。
それぞれの内容や金額は、下記コンテンツで確認してみてくださいね。
借り換え後も住宅ローン控除は受けられる?

借り換えをしても、条件を満たせば住宅ローン控除を受けられます。詳しい条件については、下記コンテンツを確認してみてください。
住宅ローンの借り換えの手続き方法は?

住宅ローンの借り換え手続きの手順は以下のとおりです。
<手順>
- ①申し込み
- ②仮審査
- ③本審査
- ④借入中の金融機関に全額繰上返済を申請
- ⑤契約
- ⑥融資実行
- ⑦抵当権の設定
審査の基準は金融機関によって異なるため、借り換えを検討する際は候補を複数挙げておきましょう。
住宅ローンを借り換えるときの審査ってどんな風に進むの?

住宅ローンを借り換える際の審査は、基本的に通常の住宅ローンを契約するのと大きく変わりません。基本的に住宅ローンの審査は「仮審査」と「本審査」の2段階に分かれています。
仮審査では、申告された年収や資産状況といった情報をもとに、大まかに審査が行われます。この段階では書類の提出不要で、Webで必要情報を入力するだけでいいという銀行も多くあります。最短で即日~1週間ほどで仮審査の結果が出ます。
本審査では、必要書類の提出が必要になります。間取り図などの物件の資料・本人確認資料をもとに、厳密に審査が行われます。
通過した後は、契約書類への記入を経て口座に融資金が振り込まれます。融資の実行までには、仮審査の申し込みからおよそ1か月~2か月を要するイメージを持っておきましょう。
おすすめの借り換え住宅ローンランキングTOP5
1位: auじぶん銀行|住宅ローン
2位: PayPay銀行|住宅ローン
3位: SBI新生銀行|住宅ローン
4位: りそな銀行|りそな住宅ローン
5位: 住信SBIネット銀行|Web申込コース
ランキングはこちら本サイトは情報提供が目的であり、個別の金融商品に関する契約締結の代理や媒介、斡旋、推奨、勧誘を行うものではありません。本サイト掲載の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いません。
人気住宅ローン関連のお役立ちコンテンツ
2000万円の住宅ローンはきついの?年収の目安や月々の返済額を解説!
マイホーム購入の際に利用する、住宅ローン。いざローンを組むとなると、どのくらいの年収が必要なのか、月々の返済額はいくらが妥当なのかなど気になる人も少なくないはずです。そこで今回は、2,000万円の住宅ローンを組む際の年収の目安や返済額を解説します。さらに年収別・年齢別の返済シミュレーションや住...
住宅ローン
住宅ローンが払えなくなったら?対処法や避けるべき行動を解説!
新築や中古のマンション、一戸建ての建築などで金融機関からの融資を受けられる住宅ローン。審査には通ったけど支払いが大変、払えなくなったらどうすればよいのかなど、悩んでいる人もいるでしょう。そこで本記事では、住宅ローンを滞納するとどうなるか、滞納する可能性が高い人の特徴、払えないときの対応方法を解...
住宅ローン
年収800万で組める住宅ローンはいくら?返済計画はどうする?
住宅の購入時に多くの人が借りている、住宅ローン。年収800万円でいくらまで借りられるのか、返済負担率はどれくらいにすべきか気になっている人も多いでしょう。今回は、年収800万円で組める住宅ローンがいくらなのか、目安や平均の借入金額を紹介します。実際に住宅ローンを借り入れたときのプランシミュレー...
住宅ローン
住宅ローンを返済中でも追加融資を受けるには?注意点や代替案も詳しく解説
住宅購入のために多額の資金を借り入れる住宅ローン。リフォームや増築のために住宅ローンの増額を考えている人もいるでしょう。本記事では、住宅ローンを返済中でも追加融資はできるのか、追加融資以外にもお金を借りる方法があるのかについて解説します。借り換えを行うときのメリットや注意点なども紹介するので、...
住宅ローン
40歳からでも住宅ローンは申し込める?借入額の目安や注意点も解説!
住宅ローンは借入れする金額が大きく、返済期間も長いので、40歳からでも住宅ローンを組めるのか不安な人もいるでしょう。そこで本記事では、40歳で住宅ローンを申し込む場合の資金状況や、申し込み時に気をつけることを解説します。住宅ローンを組むのにおすすめな金融機関も紹介するので、ぜひ参考にしてみてく...
住宅ローン
新着住宅ローン関連のお役立ちコンテンツ
年収450万で組める住宅ローンの借入額は?無理なく返せる金額はいくら?
住宅を購入する際、多くの人が利用する住宅ローン。年収450万円の場合いくらまで借入れが可能か、月々の返済額はどのくらいか気になる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、年収450万円の場合の住宅ローンの借入額や、無理なく返せる金額を解説します。年収450万円の場合の借入プランシミュレーショ...
住宅ローン
年収400万で住宅ローンはどのくらい借りられる?無理なく返済できる金額を解説!
住宅を購入する際、多くの人が利用する住宅ローン。年収400万円の場合いくらまで借りられるか、月々の返済額はいくらくらいか気になる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、年収400万円の場合の住宅ローンの借入額や無理なく返済できる金額を解説します。年収400万円の場合の借入プランシミュレーシ...
住宅ローン
住宅ローンの本審査!仮審査との違いや落ちる理由も徹底解説!
住宅ローンを借りるときに避けられない本審査。ローンの申し込みの流れや、借り入れできる条件がわからず、自分にできるか心配な人も多いでしょう。そこで今回は、ローンの申し込みの流れや本審査に落ちる原因を徹底的に解説します。審査にとおりやすくなるコツや、おすすめの住宅ローンも紹介しているので、ぜひ参考...
住宅ローン
住宅ローンの申し込みに必要な書類は?審査の流れもあわせて解説!
住宅ローンを組むときにそろえなければいけない必要書類。住宅ローンに新規で申し込みするときや借り換えをするときなどにどんな書類があるか、また、どうやって取りそろえるのか知りたい人もいるでしょう。そこで今回は、住宅ローンに必要な書類を新規や借り換えなど状況に合わせて解説します。また必要書類のチェッ...
住宅ローン
住宅ローンは多めに借りられる?オーバーローンの使い道やメリット・デメリットも解説!
購入した住宅を担保として金融機関から融資を受けられる住宅ローン。本来は住宅購入額にあわせて融資額が確定しますが、ほかの支払いに充てるための資金として多めに借りられるのか、疑問に思う人もいるかもしれません。そこで今回は、借り入れ額を多く借りる方法やオーバーローンを詳しく解説します。おすすめの住宅...
住宅ローン
ネット銀行の住宅ローンはおすすめ?メリット・デメリットも合わせて解説!
お得な金利で住宅ローンの借り入れができるネット銀行(ネットバンク)。ネット銀行で住宅ローンの借り入れや借り換えを検討しているものの、どれくらい金利が低いのか、どのようなメリット・デメリットがあるのか知りたい人もいるでしょう。本コンテンツでは、ネット銀行の住宅ローンの概要やメリット・デメリットを...
住宅ローン
フラット35はやめたほうがいい?デメリットやメリットを徹底解説!
フラット35は住宅購入の際に利用できる住宅ローンです。数ある住宅ローンのなかからフラット35を選ぶメリットがわからず、利用を迷っている人も多いのではないでしょうか。「フラット35はやばい」「やめたほうがいい」などの口コミをみると、不安に感じてしまいますよね。そこで今回は、フラット35のメリット...
住宅ローン
60歳から住宅ローンは組める?気をつけたい点やデメリットも解説!
退職後に家がほしい、年齢にあった家作りをしたいと考えている人も多いのではないでしょうか。住宅ローンは借り入れする金額が高く返済期間が長いため、年齢を重ねるごとに審査のハードルが上がってきます。定年を迎えた60歳からでも住宅ローンを借りられるのか気になりますよね。そこで今回は、60歳から住宅ロー...
住宅ローン
ブラックリストでも住宅ローンは組める?審査に通過するにはどうする?
クレジットカードやローンの滞納・債務整理が原因で登録されるブラックリスト。一度リストに載ると住宅ローンが組めないのではと不安な人もいるでしょう。本コンテンツでは、自分がブラックリストに記載されているか確認する方法や、ブラックリスト掲載者の住宅ローンの審査対策、審査に落ちたときの対応などを解説し...
住宅ローン
4500万円の住宅ローンを組むには?年収や月々の返済額の目安を解説!
マイホーム購入の際に多くの人が活用している住宅ローン。利用を検討しているものの、月々の返済額やどのくらいの年収が必要になるのかがわからず、借入額を決められずに困っている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は4,500万円の住宅ローンを借りるために必要な年収や、返済シミュレーションによる返済...
住宅ローン
カテゴリから探す
 家電掃除機、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機
家電掃除機、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機 パソコン・周辺機器デスクトップパソコン、Macデスクトップ、ノートパソコン
パソコン・周辺機器デスクトップパソコン、Macデスクトップ、ノートパソコン コスメ・化粧品日焼け止め・UVケア、レディース化粧水、乳液
コスメ・化粧品日焼け止め・UVケア、レディース化粧水、乳液 ビューティー・ヘルス香水・フレグランス、健康アクセサリー、健康グッズ
ビューティー・ヘルス香水・フレグランス、健康アクセサリー、健康グッズ 生活雑貨文房具・文具、旅行用品、筆記具・ペン
生活雑貨文房具・文具、旅行用品、筆記具・ペン キッチン用品食器・カトラリー、包丁、キッチン雑貨・消耗品
キッチン用品食器・カトラリー、包丁、キッチン雑貨・消耗品 格安SIM音声通話SIM、データSIM、プリペイドSIM
格安SIM音声通話SIM、データSIM、プリペイドSIM インターネット回線ポケット型WiFi・モバイルルーター、ホームルーター、国内レンタルWi-Fi
インターネット回線ポケット型WiFi・モバイルルーター、ホームルーター、国内レンタルWi-Fi クレジットカード・キャッシュレス決済プリペイドカード、クレジットカード、スマホ決済
クレジットカード・キャッシュレス決済プリペイドカード、クレジットカード、スマホ決済 ローン・借入カードローン、自動車ローン、住宅ローン
ローン・借入カードローン、自動車ローン、住宅ローン 脱毛脱毛サロン、メンズ医療脱毛、メンズ脱毛サロン
脱毛脱毛サロン、メンズ医療脱毛、メンズ脱毛サロン サービスネットスーパー・食材宅配サービス、資格スクール、レンタル・リース
サービスネットスーパー・食材宅配サービス、資格スクール、レンタル・リース 就職・転職転職サイト・エージェント、就活サイト・エージェント、バイト求人
就職・転職転職サイト・エージェント、就活サイト・エージェント、バイト求人 投資・資産運用FX、投資信託、証券会社
投資・資産運用FX、投資信託、証券会社 保険生命保険、医療保険、がん保険
保険生命保険、医療保険、がん保険 ウォーターサーバー宅配水ウォーターサーバー、浄水型ウォーターサーバー、ペットボトルウォーターサーバー
ウォーターサーバー宅配水ウォーターサーバー、浄水型ウォーターサーバー、ペットボトルウォーターサーバー ベビー・キッズ・マタニティおむつ・トイレ用品、おしりふき、粉ミルク・液体ミルク
ベビー・キッズ・マタニティおむつ・トイレ用品、おしりふき、粉ミルク・液体ミルク 食品菓子・スイーツ、パン・ジャム、製菓・製パン材料
食品菓子・スイーツ、パン・ジャム、製菓・製パン材料 ドリンク・お酒ビール・発泡酒、カクテル・チューハイ(サワー)、ワイン
ドリンク・お酒ビール・発泡酒、カクテル・チューハイ(サワー)、ワイン アウトドア・キャンプ燃料・ガスボンベ・炭、キャンプ用品、キャンプ用ベッド・コット
アウトドア・キャンプ燃料・ガスボンベ・炭、キャンプ用品、キャンプ用ベッド・コット DIY・工具・エクステリア電動工具、工具、計測用具
DIY・工具・エクステリア電動工具、工具、計測用具 住宅設備・リフォームテレビドアホン・インターホン、火災警報器、ガスコンロ
住宅設備・リフォームテレビドアホン・インターホン、火災警報器、ガスコンロ インテリア・家具布団・寝具、クッション・座布団、収納家具・収納用品
インテリア・家具布団・寝具、クッション・座布団、収納家具・収納用品 ペットフード ・ ペット用品犬・猫共通用品、犬用品、猫用品
ペットフード ・ ペット用品犬・猫共通用品、犬用品、猫用品 カメラデジタル一眼カメラ、デジタルカメラ、天体望遠鏡
カメラデジタル一眼カメラ、デジタルカメラ、天体望遠鏡 スマホ・携帯電話・モバイル端末携帯電話・スマホアクセサリ、au携帯電話、docomo携帯電話
スマホ・携帯電話・モバイル端末携帯電話・スマホアクセサリ、au携帯電話、docomo携帯電話 車・バイク自動車、カーナビ、カー用品
車・バイク自動車、カーナビ、カー用品 釣具・釣り用品ルアー、釣り針、釣り糸・ライン
釣具・釣り用品ルアー、釣り針、釣り糸・ライン スポーツ用品サッカー・フットサル用品、野球用品、ソフトボール用品
スポーツ用品サッカー・フットサル用品、野球用品、ソフトボール用品 趣味・ホビー楽器、おもちゃ、模型・プラモデル
趣味・ホビー楽器、おもちゃ、模型・プラモデル アプリゲームアプリ、ライフスタイルアプリ、ビジネスアプリ
アプリゲームアプリ、ライフスタイルアプリ、ビジネスアプリ テレビゲーム・周辺機器ゲーム機本体、プレイステーション4(PS4)ソフト、プレイステーション3(PS3)ソフト
テレビゲーム・周辺機器ゲーム機本体、プレイステーション4(PS4)ソフト、プレイステーション3(PS3)ソフト 本・音楽・動画動画・映像作品、本・雑誌、楽曲・音楽
本・音楽・動画動画・映像作品、本・雑誌、楽曲・音楽 ファッションレディーストップス、レディースジャケット・アウター、レディースボトムス
ファッションレディーストップス、レディースジャケット・アウター、レディースボトムス 靴・シューズサンダル、レディース靴、メンズ靴
靴・シューズサンダル、レディース靴、メンズ靴 コンタクトレンズコンタクトレンズ1day、コンタクトレンズ1week、コンタクトレンズ2week
コンタクトレンズコンタクトレンズ1day、コンタクトレンズ1week、コンタクトレンズ2week 腕時計・アクセサリー腕時計、アクセサリー・ジュエリー、ワインディングマシーン
腕時計・アクセサリー腕時計、アクセサリー・ジュエリー、ワインディングマシーン ギフト・プレゼント誕生日祝いのギフト、結婚祝いのギフト、仕事のギフト
ギフト・プレゼント誕生日祝いのギフト、結婚祝いのギフト、仕事のギフト 旅行・宿泊北海道のホテル・宿、東北のホテル・宿、関東のホテル・宿
旅行・宿泊北海道のホテル・宿、東北のホテル・宿、関東のホテル・宿 セール・キャンペーン情報Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング
セール・キャンペーン情報Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング その他アダルトグッズ
その他アダルトグッズ
