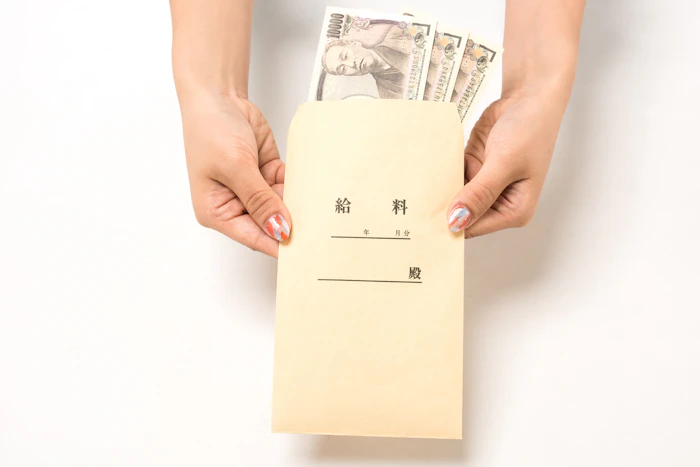
21歳の平均年収はいくら?給与アップの方法とあわせて解説
高校・短大・専門学校などを出たばかりの21歳の平均年収は、ほかの年齢層に比べると低い傾向にあります。その事実をふまえて自分の年収がどのくらいなのか、気になっている人も多いのではないでしょうか。
本記事では21歳の年収の平均や中央値を紹介するとともに、男女別・学歴別・業種別などの条件別の平均年収や収入アップの方法も解説します。自分の年収と平均年収を比較し、自分に合った年収アップの方法を取り入れたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
21歳の平均年収は267万円

厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」によると、20~24歳の平均月収は21万8,500円。12か月に換算すると年収は262万2,000円になるので、dodaのデータとほぼ同じだとわかります。
21歳は高卒だと入社3年目、短大・専門学校卒だと入社1年目の時期です。今は年収が低いと感じていても、努力次第で今後の年収アップも期待できるでしょう。
21歳の年収の中央値も確認しておこう

21歳の人がどれくらいの年収をもらっているのか知るには、中央値も確認しておきましょう。中央値とは、データを小さい数から並べたときにちょうど真ん中になる数値のこと。中央値は平均値のように極端に大きい数字や小さい数字に引っ張られることがないため、より実態に近い結果がわかります。
同じくdodaの調査によると、21歳の年収の中央値は250万円でした(参照:doda)。21歳男性の年収の中央値は250万円、女性の場合は240万円と、大きな開きはありません。21歳は社会に出て数年しか経過していないので、個々人で大きな差はまだ出てないことがわかります。
21歳の男女別・学歴別・業種別の平均年収の違いは?
21歳の平均年収は、男女・学歴・業種などの条件によっても異なります。ここからは、各条件別の平均年収の違いも確認しましょう。
男女別では男性のほうが30万円ほど高い

男女別で年収に差がある理由は、業務の難易度の差や性別によって任せられる業務の違いなどが考えられるでしょう。男性はリーダー的な業務、女性はサポート的な業務をするとの意識が根強く、業務内容が賃金にも反映されているのが現状です。
dodaの調査によると21歳男性の平均年収は286万円で女性の平均年収は252万円と、男性のほうが34万円高いとの結果が出ていました(参照:doda)。
男女別の年収は、年齢を重ねるほど男性のほうが高くなる傾向にあります。女性でより高年収を狙いたいなら、今の会社自体に満足していればより年収の高い部署への異動を希望する、昇進や手当につながる資格を取得するなどキャリアプランをしっかり考えておくとよいでしょう。
学歴別では専門学校・高専・短大卒が高卒より高い

厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査の概況」によると、20~24歳の高卒の平均年収は246万2,400円、高専・短大卒の平均年収は258万7,200円、専門卒の平均年収は264万3,600円でした。21歳では大学は卒業できないので掲載していませんが、20~24歳の大卒の平均年収は280万3,200円と、高卒と比較すると34万800円の開きがあります。
ただし、学歴による差はこのまま続くわけではありません。実力やスキルを評価されやすいIT業界や、歩合制の報酬制度を採用しているる営業職では、学歴よりも結果が重視される傾向があります。学歴に頼らず年収アップを目指すなら、実力主義の企業へ転職するのも方法のひとつだといえるでしょう。
業種別では不動産業・物品賃貸業がトップ

一方で、接客などの専門性が低い仕事は年収が低くなりやすいのが特徴です。上記の厚生労働省の調査によると、20~24歳の平均年収が高いのは以下の3つの業種でした。
- 不動産業・物品賃貸業:280万3,200円
- 学術研究・専門・技術・サービス業:279万7,200円
- 情報通信業:277万9,200円
反対に、以下3つの業種は平均年種が低い傾向にあります。
- 製造業:244万800円
- 宿泊業・飲食サービス業:240万8,400円
- 複合サービス事業:237万1,200円
年収アップを目指すなら上記で紹介した平均年収が高い業種に転職するために、どのようなスキルや知識を身につければいいのか考えて実際に行動するのも選択肢のひとつといえるでしょう。
企業規模別では大企業が最も年収が高い

20~24歳の大企業の平均年収は272万6,400円、中企業の平均年収は260万400円、小企業の平均年収は251万6,400円でした。厚生労働省では従業員1,000人以上を大企業、100~999人を中企業、10~99人を小企業と定義しています。
企業規模が大きいと昇給の可能性も高く、今は収入が低くても長期間勤務を続けることで将来的に高収入を得られる可能性があることも理解しておきましょう。
雇用形態別では正社員のほうが年収が高い

上記と同様の調査から平均年収を雇用形態別で見ると、正社員が最も高い結果になりました。
正社員は正社員以外と比べて収入が安定しているため、年収が高い傾向にあると考えられます。正社員は賞与が出たり、昇給・昇格などキャリアアップのチャンスがあったりすることも年収が高くなる理由です。
具体的にいうと20~24歳の正社員の平均年収は265万2,000円、正社員以外の平均年収は235万4,400円。アルバイト・契約社員・派遣社員などが正社員以外に含まれます。
近年、国は「同一労働同一賃金」の導入を推奨して正社員と非正社員の賃金格差をなくすことを目指していますが、まだ格差が存在するのが現状です。
21歳の人が年収をアップさせる方法
21歳の人が今後年収を上げるには何をすればいいのか、昇進・副業・転職の観点から解説します。自分に合う方法を選んで、年収アップに役立ててくださいね。
昇進・昇格のためにスキルを磨く

例えば、営業成績でトップをとるなど結果を数字で出せるように営業力を上げたり、一定の人数を有するチームを率いてプロジェクトを成功させるなどマネジメント能力を高めたりすることが考えられるでしょう。
ただし、昇進・昇格は年に数回しかチャンスがないケースが多く、すぐに年収がアップする方法ではありません。人事評価のタイミングや昇給の条件などを上司に聞いたり、就業規則で確認したりして長期的なキャリアプランを立てることが重要です。
資格を取得して資格手当をもらう

業種・職種などによって違うものの、日商簿記2級なら毎月1,000~7,000円程度の資格手当を支給しているケースがあります。ファイナンシャルプランナーなら毎月1~2万円程度の資格手当を期待できるでしょう。宅地建物取引士なら、毎月5,000~3万円程度の資格手当を支給してくれる企業もあります。
ただし資格手当の有無や金額は企業によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。また毎月の支給ではなく、祝い金として一時金が支給されることもあります。
資格の取得は昇進昇格と同様、すぐに年収がアップする方法ではありません。資格手当はもらえるのか、資格を活かしてより収入の高い仕事へ転職できる可能性はあるかを確認しておきましょう。
以下の記事では、転職に有利な資格と資格取得に役立つ通信講座を紹介しています。より高収入を目指せる資格を知り、働きながらでも効率的に資格取得を目指せる通信講座やスクールを活用してみましょう。
本業に近い副業で効率よく収入を得る

例えばプログラマーならプログラミング、普段から文章を書く機会が多い仕事ならライティングなどがあります。Webデザインを制作しているなら、そのスキルをブログやWebサイト運営に活かしてアフィリエイト収入を得るのもいいでしょう。
ただし会社によっては副業を禁止しているケースもあるため、事前に就業規則を確認してみてくださいね。また副業による収入が年間20万円を超えると、会社員でも自分で確定申告を行う必要があります。
同じ職種や業種の企業に転職して年収をあげる

例えば、営業職を経験している場合は同じ業種の営業職だけでなく、別の業種の営業職に挑戦するのも選択肢のひとつ。以前よりも給与水準が高い企業や、業界自体の景気が上向きな業種に転職できれば、待遇がよくなる可能性も十分あります。
転職活動を始める際は、20代向けの転職サイトや転職エージェントを活用しましょう。20代向けに特化した転職サイトを使えば、より自分に合う求人を見つけやすくなります。転職エージェントは、転職活動中の書類作成・スケジュール調整・面接対策などのサポートを受けられる点が魅力です。
以下の記事では、転職に役立つ転職サイトや転職エージェントを、公開求人数の数やサイトの使いやすさなどから比較検証しました。転職による収入アップを目指している人は、自分に合う転職サイトや転職エージェント探しの参考にしてみてください。
マイベストは有料職業紹介事業の許認可を受けています。(13-ユ-315911)
人気転職サイト・エージェント関連のお役立ちコンテンツ
20代の転職に有利な資格は?男女別・業界別に紹介
現在の会社に不満がある、キャリアアップしたいなど、さまざまな理由で20代で転職を考える人は多いでしょう。特に未経験の業種へ転職を考える場合は、どのような資格が役立つのか気になりますよね。そこで今回は、男女別や業界別に20代の転職に役立つ資格を紹介します。20代の転職に資格は必須かや、資格なしで...
転職サイト・エージェント
33歳の平均年収はいくら?業種や性別による違いも解説
同年代の人はどのくらい稼いでいるのか、気になりますよね。そんなときにチェックしたいのが平均年収です。社会人生活が10年以上になる人も多い33歳の平均年収は、どれくらいなのでしょうか。そこで今回は、33歳の平均年収について解説します。年収が変化する条件や年収アップのためにできることも紹介するので...
転職サイト・エージェント
転職してすぐ転職しても大丈夫?入社後すぐ退職したいときの判断基準を紹介
雇用期間の定めがなければ、転職したあとにすぐ退職しても問題ありません。しかし実際に転職するかを判断する基準はあるのか、退職する際にやるべきことは何なのかがわからず、なかなか一歩を踏み出せない人も多いのではないでしょうか。本記事では転職後にすぐ退職したいと思ったときの判断基準や、退職する際の手続...
転職サイト・エージェント
30代女性の転職は厳しいの?未経験やスキルなしでも成功するコツを解説
30代女性は生活とキャリアの両立が難しくなる年代でもあり、なかには転職をする人もいます。しかし、30代からの転職はときに厳しいといわれることもあるため、転職活動をはじめてもよいのか不安を感じる女性も多いでしょう。そこで今回は、資格やスキルなしの30代女性が転職を成功させるポイントを解説します。...
転職サイト・エージェント
手取り40万円の年収は?生活レベルや目指せる仕事を紹介
手取り40万円を、収入のひとつの目標にしている人は多いのではないでしょうか。40万円あると、具体的にどんな生活ができるのか気になりますよね。そこで今回は、手取り40万円の生活レベルを世帯の人数別に解説します。目指せる職業も紹介するので、年収アップを狙っている人はぜひ参考にしてください。
転職サイト・エージェント
新着転職サイト・エージェント関連のお役立ちコンテンツ
未経験エンジニアはやめとけといわれる理由は?実態と心構えを紹介
身につけた技術によって稼ぐことができるエンジニア。未経験からエンジニアを目指している人も多いでしょう。しかし、まわりから「やめとけ」といわれ、迷っている人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、未経験からエンジニアを目指すのはやめとけといわれる理由を紹介します。それでもエンジニアになりたい人...
IT向け転職サイト
1か月前に退職を伝えるのは非常識?適切な時期や退職までのスケジュールも解説
今の会社を退職したいと考えた場合、いつ頃までに伝えるべきか悩ましいですよね。1か月後を目安に退職したいけど、非常識だと思われないか不安になる人もいるでしょう。そこで今回は、1か月前に意思を伝えても、退職は可能なのか解説します。退職日までのスケジュールの目安や、会社に認めてもらえなかった場合の対...
転職サイト・エージェント
35歳の平均年収はいくらくらい?男女別・業種別平均も紹介
35歳は、社会人経験が10年を超える人も多い年齢です。今後のキャリアを考えるなかで、35歳の平均年収を知りたいと思っている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、35歳の平均年収を紹介します。35歳から年収をアップする方法も紹介しているので、今後のキャリアプランを考える際の参考にしてみてく...
転職サイト・エージェント
国民健康保険と任意継続はどっちが安い?収入別の比較や手続き方法を解説
会社を退職した際に利用できるのが、健康保険の任意継続制度。国民健康保険とどちらの保険料が安いかは、退職時の収入や世帯人数によって異なります。どちらを選ぶべきかわからず、悩んでしまう人も多いでしょう。そこで今回は、国民健康保険と任意継続ではどちらが安いのかを条件別に解説します。それぞれの特徴や手...
転職サイト・エージェント
退職後の手続きと順番は?会社を辞めたあとの対応を徹底解説
健康保険と年金の切り替え、失業保険の申請、住民税の支払い方法の変更など、退職後には多くの手続きが必要です。具体的な手続きの内容や順番がわからず、困っている人も多いのではないでしょうか。本記事では退職後の公的な手続きの内容や順番、必要書類などの準備するものを解説します。退職後の手続きを期日までに...
転職サイト・エージェント
派遣会社に複数登録しても良いの?メリットと注意点を解説
派遣会社を利用する際、複数の派遣会社に登録してよいか気になるところでしょう。興味のある派遣会社が複数あっても、念のため1社だけの登録にとどめている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、派遣会社に複数登録しても問題ないか解説します。派遣会社に複数登録するメリットも紹介しているので、派遣会社...
転職サイト・エージェント
薬剤師の免許更新・届け出方法は?忘れたらどうなる?
医療系の国家資格である薬剤師。薬剤師の資格を持つ人のなかには、免許の更新が必要なのかわからない人もいるのではないでしょうか。今回は薬剤師免許の更新の有無を解説します。免許保有者の義務である届け出のやり方や、届け出を忘れたときの対処法も紹介するので、薬剤師免許を保有する人は参考にしてみてください。
薬剤師向け転職サイト・エージェント
年収400万の手取り額は?生活レベルの実態を解説
日本で働く正社員の平均年収に近い年収400万円。年収400万の手取り額はいくらになるのか、一人暮らしではどれくらいの生活レベルを送れるのか、と不安を抱えている人も数多くいるのではないでしょうか。ここでは、年収400万円の手取り額や引かれる税金、年収アップを目指す方法を詳しく解説します。具体的な...
転職サイト・エージェント
月給24万円の手取り額はいくら?生活水準や収入アップの方法を紹介
収入アップを考えるとき、チェックすべき手取り額。月給24万円もらった場合は、手取り額がいくらになるか気になる人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、月給24万円の手取り額や生活レベルについて解説します。月給24万円から収入を増やす方法も紹介するので、参考にしてくださいね。
転職サイト・エージェント
手取り15万の生活レベルは?一人暮らしの貯金や家賃の目安を紹介
就職や転職を考えるときに、気になるのが給料。手取り15万円だと生活レベルはどのくらいなのか、一人暮らしや貯金はできるのかなど、気になる人もいるのではないでしょうかそこで今回は、手取り15万円での生活について詳しく解説します。一人暮らしが可能かや適切な家賃の目安のほか、理想的な貯金額も紹介するの...
転職サイト・エージェント
