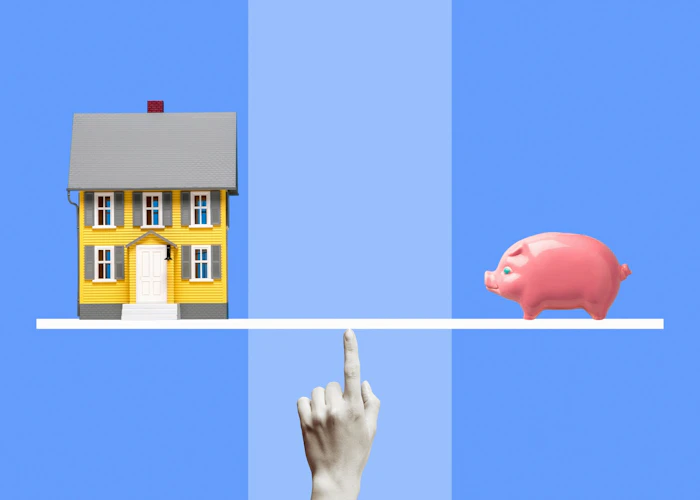
住宅ローン返済額の平均は?頭金や借入額の目安も解説!
本記事では、住宅購入資金の平均額や借入時の頭金を解説します。借入期間の目安も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
住宅購入資金の平均は4,000万円。新築は中古の1.5倍以上

世帯主の年齢を見ると新築住宅を購入しているのは30代が多い結果でした。また、中古住宅の購入は40代が多いことがわかります。
住宅ローン借入時に関する平均値
住宅購入資金のうち、住宅ローンの借入時のデータはどうなっているのでしょうか。平均世帯年収や、頭金、平均借入額の平均値を紹介します。
住宅ローン平均借入金額は2,000万円。新築住宅は3,000万円越え

住宅購入時の頭金は平均1,400万円。住宅価格の10〜40%が目安

自己資金比率は住宅価格の20~45%を目安にするとよいといわれており、住宅ローンのなかには住宅価格の10%以上頭金を入れることで金利の優遇を受けられるものも。頭金の平均が約1,400万円だったのは、こうした金利優遇を受けることが目的と考えられるでしょう。
また、頭金を多く入れると、月々の返済にかかる負担を軽くできるほか、返済負担率を目安の25%以内に収められる可能性があります。 自己資本比率とは、住宅ローンを返済しながら無理なく生活するための指標のことです。
住宅購入した人のデータでは自己資金比率がほぼ20~45%以内に収まっていることからも、頭金は少なくとも住宅価格の10~40%を目安にしておきましょう。
平均世帯年収は740万円。共働き世帯はペアローンを利用できる

「令和3年度住宅市場動向調査報告書」によると、建物に問わず住宅ローン借入時の平均世帯年収は約740万円でした。住宅の区分別にみると、今回の調査で最も高かったのは、新築の分譲マンションを購入している層で、平均年収は912万円です。
最近は共働き世帯が増えている影響もあり、住宅ローンを組む際にはペアローンを利用する人も増えています。ペアローンは夫婦の収入を合算して借入できるため、世帯主だけの場合に比べて借入金額を増やすことが可能です。ただし、ずっと夫婦ともに安定した収入を得られるとは限りません。
育児や介護、さまざまな事情により収入が減る可能性があるため、借入する際は慎重に検討することが大切です。ペアローンを組む際は、夫婦の収入を合算した額の7~8割を目安にするとよいでしょう。
住宅ローンの返済に関する平均値
住宅ローンの平均返済額は年間110万円。月に10万円くらい

ただし、これはあくまでも平均的な数値です。例えば分譲マンションだけで見ると年間返済額は150万円ほどで、月に約12万5,000円返済していることがわかります。また、注文住宅も年間返済額は約139万円、月に11万6,000円ほどを返済しており、建物を問わず平均化した年間返済額よりも高めです。
また、中古・分譲に限らず戸建てよりマンションのほうが平均返済額は高いことがわかります。
住宅ローンの平均返済期間は32年。新築住宅のほうが長い

購入価格は高くても返済金額を長く設定するほど毎月の返済額は安くなり、返済負担率を抑えることが可能です。しかし、一方で返済期間が長引けばその分支払う利息も多くなり、総支払額が増えるというデメリットが存在します。
また、40歳以上の場合、30年以上のローンを組むと70歳を超えても返済しなければなりません。定年後は収入が減ることを考えると、老後に返済ができなくなるリスクがあるほか、審査に通りにくい可能性があります。
住宅ローンの返済負担比率は年収の20%が目安

返済負担比率は金融機関の審査に通る範囲の借入かを判断する指標にもなっているため、年収に対し無理のない返済計画を立てることが重要。実際、国土交通省の「令和3年度住宅市場動向調査報告書」では、最も年間返済額の高い分譲マンション世帯で返済負担率は18.1%と新築注文住宅と同じ数字です。
最も返済負担非率の高い分譲戸建て住宅でも19.8%と、目安である20%以下。ちなみに返済負担比率の求め方は以下のとおりです。
- 年間のローン返済額÷年収の100倍=返済比率(%)
返済負担比率は年間のローン返済額によって金額が左右します。返済負担比率が高ければ、年収に対し無理があると判断され、金融機関の審査がとおりにくいだけでなく、借入後の生活にも影響を及ぼすこともあるでしょう。住宅ローンを組む際は、年収に見合った適正な返済負担比率に抑えることが大切です。
住宅を購入する予定の人はおすすめの住宅ローンをチェック

また、頭金を多く入れることで毎月の返済額を抑えることもできるため、返済負担比率が20%を超える場合は、自己資金比率を上げるのもおすすめです。ほかにも、住宅ローンは条件によっても、毎月の返済額は変わります。
どこの住宅ローンを選べばよいのか悩んでいる人は、こちらの記事も参考にしてみてください。
本サイトは情報提供が目的であり、個別の金融商品に関する契約締結の代理や媒介、斡旋、推奨、勧誘を行うものではありません。本サイト掲載の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いません。
人気住宅ローン関連のお役立ちコンテンツ
転職してすぐでも住宅ローンは組める?審査に影響するって本当?
審査のときに在職期間が問題になる住宅ローン。転職したあとに組めるのか、ローンを返しているときに転職した場合には問題ないかといった点に悩む人もいるでしょう。本記事では、転職後すぐに住宅ローンを組めるかや、組む際の気をつけたいことについて解説します。住宅ローン返済中に転職をするときの注意点なども紹...
住宅ローン
住宅ローンは同じ銀行で借り換えできる?理由や代替案を紹介!
返済期間が長期にわたる住宅ローン。少しでも返済額を抑えるために、借り換えを検討している人も多いのではないでしょうか。本記事では、同じ銀行で借り換えができるのか、もしくはほかの銀行に借り換えたほうがメリットが大きいのかについて解説します。借り換えをしなくても負担を減らせる方法も紹介しているので、...
住宅ローン
夫婦で住宅ローンを組む方法はどれがおすすめ?条件やメリット・デメリットを解説!
住宅の購入を検討しているものの、世帯の収入状況などを考えると夫婦で分担して返済を進めたいと考えている人は多いのではないでしょうか。しかし、夫婦で住宅ローンを組むにもどのように申し込めばよいのか分からない人や、どんな落とし穴があるのかと悩んでいる人もいるでしょう。本記事では、夫婦で住宅ローンを組...
住宅ローン
住宅ローン返済比率の理想は20%?無理のない借入額はどのくらい?
年収に対する住宅ローンの年間返済額の割合を示す返済比率。一般的に20%が理想といわれていますが、実際は何%になればよいのか知りたい人もいるでしょう。 本コンテンツでは、住宅ローンの返済比率の目安から計算方法、注意点まで解説します。返済比率を抑える方法や借入金額ごとのシミュレーションなども紹介す...
住宅ローン
住宅ローンの審査に落ちたら?落ちる理由やその後の対処法について解説!
住宅ローンを組む際に、返済能力を確かめる目的で必ず行われる審査。マイホーム購入を検討している人のなかには、ローンの審査に落ちる可能性はあるのか、落ちたらどうすればよいのかと不安を抱えている人もいるでしょう。本記事では、住宅ローンの事前審査や本審査に落ちたときに考えられる理由を解説します。住宅ロ...
住宅ローン
新着住宅ローン関連のお役立ちコンテンツ
年収450万で組める住宅ローンの借入額は?無理なく返せる金額はいくら?
住宅を購入する際、多くの人が利用する住宅ローン。年収450万円の場合いくらまで借入れが可能か、月々の返済額はどのくらいか気になる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、年収450万円の場合の住宅ローンの借入額や、無理なく返せる金額を解説します。年収450万円の場合の借入プランシミュレーショ...
住宅ローン
年収400万で住宅ローンはどのくらい借りられる?無理なく返済できる金額を解説!
住宅を購入する際、多くの人が利用する住宅ローン。年収400万円の場合いくらまで借りられるか、月々の返済額はいくらくらいか気になる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、年収400万円の場合の住宅ローンの借入額や無理なく返済できる金額を解説します。年収400万円の場合の借入プランシミュレーシ...
住宅ローン
住宅ローンの本審査!仮審査との違いや落ちる理由も徹底解説!
住宅ローンを借りるときに避けられない本審査。ローンの申し込みの流れや、借り入れできる条件がわからず、自分にできるか心配な人も多いでしょう。そこで今回は、ローンの申し込みの流れや本審査に落ちる原因を徹底的に解説します。審査にとおりやすくなるコツや、おすすめの住宅ローンも紹介しているので、ぜひ参考...
住宅ローン
住宅ローンの申し込みに必要な書類は?審査の流れもあわせて解説!
住宅ローンを組むときにそろえなければいけない必要書類。住宅ローンに新規で申し込みするときや借り換えをするときなどにどんな書類があるか、また、どうやって取りそろえるのか知りたい人もいるでしょう。そこで今回は、住宅ローンに必要な書類を新規や借り換えなど状況に合わせて解説します。また必要書類のチェッ...
住宅ローン
住宅ローンは多めに借りられる?オーバーローンの使い道やメリット・デメリットも解説!
購入した住宅を担保として金融機関から融資を受けられる住宅ローン。本来は住宅購入額にあわせて融資額が確定しますが、ほかの支払いに充てるための資金として多めに借りられるのか、疑問に思う人もいるかもしれません。そこで今回は、借り入れ額を多く借りる方法やオーバーローンを詳しく解説します。おすすめの住宅...
住宅ローン
ネット銀行の住宅ローンはおすすめ?メリット・デメリットも合わせて解説!
お得な金利で住宅ローンの借り入れができるネット銀行(ネットバンク)。ネット銀行で住宅ローンの借り入れや借り換えを検討しているものの、どれくらい金利が低いのか、どのようなメリット・デメリットがあるのか知りたい人もいるでしょう。本コンテンツでは、ネット銀行の住宅ローンの概要やメリット・デメリットを...
住宅ローン
フラット35はやめたほうがいい?デメリットやメリットを徹底解説!
フラット35は住宅購入の際に利用できる住宅ローンです。数ある住宅ローンのなかからフラット35を選ぶメリットがわからず、利用を迷っている人も多いのではないでしょうか。「フラット35はやばい」「やめたほうがいい」などの口コミをみると、不安に感じてしまいますよね。そこで今回は、フラット35のメリット...
住宅ローン
60歳から住宅ローンは組める?気をつけたい点やデメリットも解説!
退職後に家がほしい、年齢にあった家作りをしたいと考えている人も多いのではないでしょうか。住宅ローンは借り入れする金額が高く返済期間が長いため、年齢を重ねるごとに審査のハードルが上がってきます。定年を迎えた60歳からでも住宅ローンを借りられるのか気になりますよね。そこで今回は、60歳から住宅ロー...
住宅ローン
ブラックリストでも住宅ローンは組める?審査に通過するにはどうする?
クレジットカードやローンの滞納・債務整理が原因で登録されるブラックリスト。一度リストに載ると住宅ローンが組めないのではと不安な人もいるでしょう。本コンテンツでは、自分がブラックリストに記載されているか確認する方法や、ブラックリスト掲載者の住宅ローンの審査対策、審査に落ちたときの対応などを解説し...
住宅ローン
2000万円の住宅ローンはきついの?年収の目安や月々の返済額を解説!
マイホーム購入の際に利用する、住宅ローン。いざローンを組むとなると、どのくらいの年収が必要なのか、月々の返済額はいくらが妥当なのかなど気になる人も少なくないはずです。そこで今回は、2,000万円の住宅ローンを組む際の年収の目安や返済額を解説します。さらに年収別・年齢別の返済シミュレーションや住...
住宅ローン
