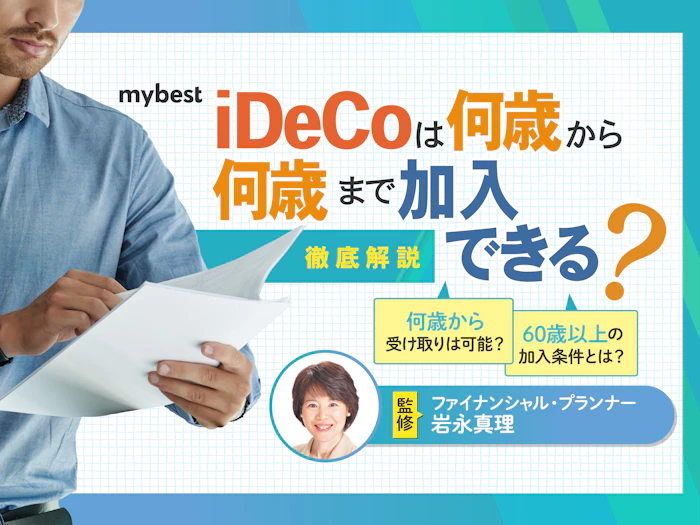
iDeCoは何歳から何歳まで加入できる?50・60代から始めても遅くないのかも解説
そこで今回は、iDeCoに加入できる年齢の条件についてわかりやすく解説します。何歳からいつまでに加入すればメリットがあるのか、受け取れる年齢はいつかについても解説するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

大手金融機関に入行後、海外赴任を含め10年以上勤務。その後、2009年8月にファイナンシャル・プランナー資格取得。現在は、独立系FPとして契約者の立場に立って真剣に対応することをモットーに、個人相談やセミナー講師、執筆活動を行っている。

大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
iDeCoは何歳まで加入できる?
はじめに、iDeCoに加入できる年齢の条件を確認しましょう。
iDeCoに加入できるのは原則65歳まで

1つ目は、60歳以降も厚生年金に加入したまま勤務を続ける、会社員や公務員です。
2つ目は、自営業者・専業主婦・定年退職した元会社員で、60歳以降も国民年金に加入する人。基本的に60歳になると国民年金から外れますが、40年間(480か月)国民年金に入っていない場合は、任意加入という形で国民年金を継続できます。
3つ目は、海外に住んでいて国民年金に入っている人です。日本に住所がなければ国民年金の加入義務はありませんが、任意加入はできます。
なお、2024年12月に厚生労働省が加入年齢の上限を65歳未満から70歳未満に引き上げる方針を示しました。具体的な引き上げの時期は決定していませんが、最新の情報を確認しておくようにしましょう。
60歳からでもiDeCoに加入できる人とできない人がいる

60歳以降の人は、iDeCoへ加入ができる場合もあれば、加入資格がないケースもあります。
iDeCoを以前から利用していて、法改正前に60歳を迎えた人の場合、国民年金に加入していること、公的年金やiDeCoを受け取っていないことの2つの条件を満たしたうえで、加入手続きをすればiDeCoに再加入することが可能です。
以前からiDeCoを利用していて、法改正後に60歳になった場合は、公務員と会社員であれば手続きをすることなくそのままiDeCoの継続ができます。自営業や専業主婦の人は、事前に継続加入手続きを行う必要があるため注意しましょう。
法改正後に60歳を迎えてから新規加入したい場合は、通常のルールどおりiDeCoの基本的な加入条件を満たしていれば加入できます。
iDeCoは何歳から受け取れる?
次に、iDeCoを受け取れる年齢や、受け取り開始時期の上限について紹介します。
受け取りが可能な年齢はiDeCoの加入期間によって異なる

iDeCoをいつから受け取れるかは、60歳までにiDeCoにどのくらい加入していたかによって異なります。60歳までに10年以上加入した場合は、60歳から受け取りが可能です。iDeCoの加入期間が10年未満だと、加入期間が少なくなるにつれて受け取り開始年齢も上がるので注意してください。
例えば、加入期間が8年以上10年未満なら、受け取り開始年齢は61歳。加入期間が6年以上8年未満なら、受け取り開始年齢は62歳と、加入期間が2年減るごとに受け取れる年齢が1歳ずつ先延ばしになります。
法改正された2022年5月以降に60歳以上の人がiDeCoに加入した場合は、加入してから5年後に受け取りが可能です。iDeCoの加入期間が10年を越えるまで待つ必要はありません。どの時点でiDeCoへ加入するにせよ、できるだけ早めに受け取りたいなら、準備が整った時点で速やかに積み立てを始めるのがおすすめです。

iDeCoは運用益が非課税になり、長期運用をするほど複利効果が大きくなるため、早めに利用したい制度です。
1年あたりの拠出額に限度があり、一般的には5年以上の加入期間があると望ましいと考えられます。そのため、55歳までに加入できるとよいでしょう。
今回の改正で60歳以降も加入要件を満たす人は、65歳までの拠出も可能な場合があるので、検討してみてもよいですね。
受け取り開始年齢の上限は75歳!すぐに受け取らなくてもOK

iDeCoの受け取り開始年齢の上限はこれまで70歳でしたが、法改正により75歳までに拡大されました。75歳まで拡大されたことにより、60歳以降でiDeCoを開始しても、長期運用で資産形成がしやすくなったのが魅力です。
また、iDeCoはすぐに受け取らなくてもよいため、自分のタイミングにあわせて75歳までに受け取ることができます。ほかの公的年金や会社の退職金を受け取るタイミングとあわせて考慮し、老後の暮らしに有意義に使えるように工夫したり、税金の負担が減るようにしたりすることが重要です。
iDeCoへの加入は50代や60代でも遅くない!その理由は?
年金制度改正法が改正された現在では、50・60代でもiDeCoに入るメリットは十分あるといえます。以下で理由を確認しましょう。
掛金が全額所得控除され節税できる

iDeCoの掛金は全額所得控除されるため、所得税と住民税が少なくなることで節税効果が期待できます。
所得控除とは、決められた金額を年間の課税所得から差し引くことです。所得税と住民税は、所得控除した金額に税率をかけて算出するので、iDeCoを積立金額に税率をかけた分だけ税金を節約できるのは大きなメリットといえます。
例えば、年収500万円の会社員が、55歳でiDeCoに加入して65歳まで積み立てた場合を考えてみましょう。毎月2万円を積み⽴てると、1年間で所得税(税率10%)および住民税(税率10%)それぞれ2万4000円ずつ、合計4万8000円が節税できる計算になります。
節税した分は確定申告や年末調整で還付してもらえるので、忘れずに手続きを行いましょう。

50~60代は、運用できる年数も短くなってくるため、許容できるリスクもだんだん少なくなってくるでしょう。そのため、リスク資産の割合を年代とともに減らしていく方法が有効です。
運用益が出ている商品があれば、売却して利益を確定して元本保証の商品へ切り替えたり、リスクの比較的低い債券へ投資する投資信託での運用へ徐々にシフトしていくことも可能です。
受け取りのタイミングを税金の控除額を考慮しながら調整するとよいでしょう。
75歳まで非課税で運用が可能

iDeCoは運用益が非課税になるため、50・60代から加入して75歳まで運用したときに運用益が満額受け取れるのもメリットです。株や投資信託などの運用益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoだと非課税になります。
例えば、60歳の会社員がDeCoに加入し、毎月23,000円の掛金を積み立てて利回り3%で運用した場合を考えてみましょう。65歳までの5年間積み立てた場合は、運用益105,362円に対する税金21,404円が非課税になります。
同じ条件で加入年齢を55歳にした場合も、同じように計算してみましょう。65歳までの10年間積み立てた場合は、運用益447,303円に対する税金90,869円が非課税になります。50代や60代からの加入でも十分に恩恵が受けられるため、ぜひiDeCoの利用を検討してみてください。
iDeCoは受け取り方次第で税金がかからない

iDeCoを一時金として一括で受け取ると退職所得控除、年金として受け取ると公的年金等控除ができるので、受け取り金額によっては全額非課税にすることもできます。
退職所得控除の計算方法は、iDeCoの加入年数が20年以下なら40万円×加入年数で、計算して80万円未満になったら80万円です。例えば加入年数が10年だと、40万円×10年なので400万円まで控除できます。
また、加入年数が20年以上の計算方法は、800万円+70万円×(加入年数-20年)です。例えば25年加入すると、1,150万円まで控除が可能になります。
年金として受け取ると、公的年金と合わせた年間収入が65歳未満だと60万円、65歳以上は110万円までなら税金がかかりません。一般的には、一時金として受け取るほうが税制上のメリットが大きいといわれています。
自分の状況にあわせ、最も税負担が少ない方法を選ぶことを検討してみるとよいでしょう。

一括で受け取る場合の退職所得控除は、会社の退職金などと合算した控除に。
退職所得控除は控除額が大きい一方で、既に退職金などの大きな金額に対してこの控除を使う予定がある人は、iDeCoに適用できる退職所得控除枠に余裕がないことも考えられます。
その際は、公的年金をもらう65歳より前の「60歳から65歳までの公的年金控除」を使えば、毎年60万円までは非課税で受給できますよ。
法改正により50代からスタートするデメリットが少なくなった

法改正により、iDeCoを50代以降に始めたときのデメリットが少なくなったのも理由のひとつです。法改正以前は、iDeCoの加入期間が10年未満の場合、60歳を過ぎてから受け取れるまでの間に積み立てができない空白期間がありました。
掛金を所得控除できるメリットが受けられない状態で、毎月の口座管理手数料だけがかかって運用益が少なくなるケースもあったのが特徴です。法改正によって、50代からでもiDeCoを利用して老後の資金作りをしやすくなったといえます。

2024年12月から、企業型DCと確定給付型に加入している人のiDeCoの拠出限度額が、月1.2万円から2万円に引き上げられます。
ただし、企業型DCと確定給付型などの掛金額と合算して月5万5千円を超えることはできません。
iDeCoの商品・金融機関のランキングはこちら
以下の記事では、iDecoのおすすめの金融機関・商品や選び方を紹介しています。iDecoについて理解が深まったものの、実際にどの金融機関でどの商品を運用したらよいのかわからないという人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
本サイトは情報提供が目的であり、個別の金融商品に関する契約締結の代理や媒介、斡旋、推奨、勧誘を行うものではありません。本サイト掲載の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いません。
人気ideco関連のお役立ちコンテンツ
iDeCoと小規模企業共済はどっちがいい?違いや併用のメリットについて解説
資産形成を行うための積み立て制度である、iDeCoと小規模企業共済。どちらも個人事業主などが老後に備えるために活用できますが、違いがよくわからない人やどちらを利用すればいいのか疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、iDeCoと小規模企業共済のどちらに加入するべきかについて...
ideco
iDeCoと国民年金基金はどっちがいい?併用は可能?個人事業主向けの年金について解説
個人事業主が老後資金を貯めるときに、選択肢に挙がるのがiDeCoと国民年金基金。しかし、違いがよくわからず、どちらで積み立てるべきか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、個人事業主の資産形成にあたって、iDeCoと国民年金基金のどちらを選べばよいかについて解説します。それぞれの...
ideco
iDeCoは本当にデメリットしかない?入るべき理由やメリット、注意点を解説
長期的に積み立てて老後の生活資金にできる、確定拠出年金のiDeCo(イデコ)。入らないほうがいいなどのウワサを聞いていて、実際のところはどうなのか、入ったほうがいいのか気になっている人も少なくないはずです。そこで今回は、iDeCoのデメリットやメリットについてわかりやすく解説します。iDeCo...
ideco
iDeCoは年末調整・確定申告が必要?所得控除でいくら戻るのか解説
必要に応じて年末調整が必要なiDeCo。iDeCoに税制優遇があると知って始めてみたものの、年末調整や確定申告を行う必要はあるのか、どのくらい税金が戻ってくるのかなど、さまざまな疑問を感じている人も多いのではないでしょうか。本記事では、iDeCoの年末調整や確定申告の必要性を解説します。減税額...
ideco
iDeCoの始め方は?加入条件や必要書類、始めるタイミングを解説
税制優遇でお得に資産運用ができる個人型確定拠出年金「iDeCo」。iDeCoへの加入を検討しているものの、そもそもどうやって始めるのかわからない、加入資格がわからない、どの金融機関・商品を選べばいいのか知りたいなど、さまざまな悩みを抱えている人も少なくないでしょう。本記事では、iDeCoに加入...
ideco
新着ideco関連のお役立ちコンテンツ
iDeCoと個人年金保険はどっちがおすすめ?違いやメリット・デメリットを解説
将来に向けた資産形成ができる、iDeCoと個人年金保険。老後資金を確保するためにどちらかをはじめたいと考えているものの、どちらがよいかわからず申し込みに踏み切れない人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、iDeCoと個人年金保険の違いやそれぞれのメリット・デメリットについて解説します。どち...
ideco
iDeCoの年代別おすすめポートフォリオは?資産配分や商品の選び方を解説
iDeCoの運用にはポートフォリオの設定が重要だと聞いたことがあるものの、難しそうだと感じて加入をためらっている人もいるのではないでしょうか。自分に合ったポートフォリオを組まずにiDeCoの運用をはじめると、思ったように資産形成できない可能性があります。そこで今回は、年代別にiDeCoのおすす...
ideco
企業型確定拠出年金からiDeCoに移換する方法は?金融機関を変更するメリット・デメリットも解説
老後に向けた資産形成のために、加入者が増えているのが私的年金制度iDeCo。積み立てを継続しているものの、転職や退職にあたって、どのような手続きをすればよいかわからず困っている人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、企業型確定拠出年金からiDeCoに移管する方法や、その逆のケースについて解...
ideco
iDeCoの掛金の上限は?月々の掛金の平均・目安も解説
公的年金にプラスして給付を受けられるiDeCo。加入を検討しているものの、掛金の上限がわからない、掛金の目安を知りたいなど、さまざまな疑問が生じてしまい、申し込みに踏み切れない人も多いはずです。本記事では、iDeCoの掛金の上限を徹底的に解説します。掛金の平均や目安を決める方法なども紹介するの...
ideco
iDeCoは個人事業主・自営業・フリーランスにおすすめ?税制優遇など活用方法を解説
老後に向けた資産形成の重要性が高まるなか、注目が集まるiDeCo。会社員に比べて年金額が少ない個人事業主や自営業者で、加入を検討している人も多いのではないでしょうか。しかしiDeCoのメリットやデメリットがよくわからず、加入まで踏み切れないという人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、iD...
ideco
iDeCoの掛け金は月5000円では意味ない?最低金額でも得する方法や注意点を解説
毎月一定額を積み立てて老後に備える私的年金制度、iDeCo。掛け金は月々5,000円から設定できますが、最低金額で積み立てても意味がないと考えて、始めていない人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、月5,000円だけでもiDeCoに拠出する意味はあるのかについて解説します。5,000円しか...
ideco
iDeCoは元本割れのリスクがある?元本確保型と元本変動型について解説
老後の資産形成に役立つとして注目されている私的年金制度、iDeCo。節税効果の高さや投資への関心の高まりから、加入を検討している人も多いのではないでしょうか。しかしiDeCoには元本割れのリスクがあると聞き、不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、iDeCoは元本割れする可...
ideco
会社員でもiDeCoに加入したい!上限や会社に知られない方法も解説
毎月お金を積み立て、老後のための資産形成ができる私的年金制度iDeCo(イデコ)。フリーランス向けのイメージがありますが、会社員も加入できます。しかし、加入を検討しているものの、会社員が加入するための条件や方法がわからず悩んでいる人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、会社員がiDeCoに...
ideco
iDeCoと企業型確定拠出年金の違いは?併用はできる?マッチング拠出とiDeCoの違いについても解説
老後の資産形成をサポートする、私的年金制度iDeCo。勤務先で企業型確定拠出年金に加入しているが、iDeCoも気になっているという人もいるのではないでしょうか。スムーズに資産形成をするためにも、可能であれば併用したいですよね。そこで今回は、iDeCoと企業型確定拠出年金の違いや併用の可否につい...
ideco
iDeCoの運用利回りの平均は?利率や計算方法も解説
老後資金を積み立ながら節税もできる、お得な私的年金制度、iDeCo(イデコ)。始めてみようと考えているものの、運用利回りがどのくらいなのか気になっている人もいるのではないでしょうか。どの程度の運用成果が見込めるのかわからないと、なかなか手を出しにくいですよね。そこで今回は、iDeCoの運用利回...
ideco
