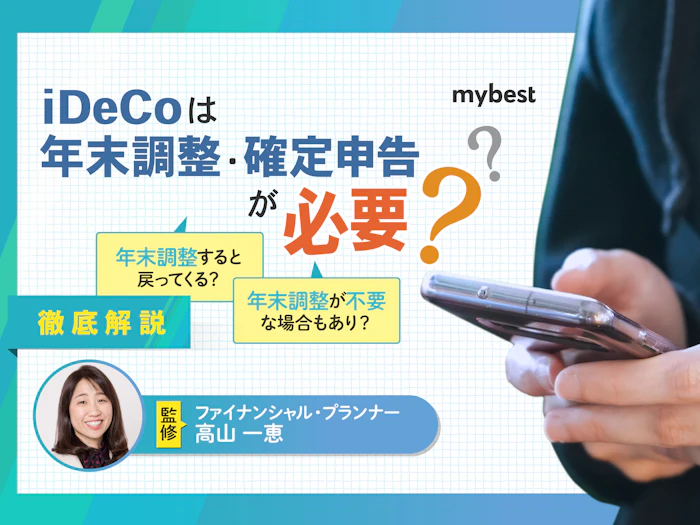
iDeCoは年末調整・確定申告が必要?所得控除でいくら戻るのか解説
必要に応じて年末調整が必要なiDeCo。iDeCoに税制優遇があると知って始めてみたものの、年末調整や確定申告を行う必要はあるのか、どのくらい税金が戻ってくるのかなど、さまざまな疑問を感じている人も多いのではないでしょうか。
本記事では、iDeCoの年末調整や確定申告の必要性を解説します。減税額のシミュレーションや年末調整が間に合わないときの対象法なども紹介するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

2005年に女性向けFPオフィス(株)エフピーウーマンを創業。10年間取締役を務めた後、現職へ。女性向けWEBメディア『FP Cafe®』や『Mocha』を運営。また、『Money&You TV』や「マネラジ。」「Voicy」などでも情報を発信しているうえに、全国での講演活動、執筆、マネー相談を通じて、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。「はじめてのNISA &iDeCo」(成美堂出版)「1日1分読むだけで身につく お金大全100」(自由国民社)」など著書多数。

大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
iDeCoで節税するには原則年末調整が必要

iDeCoで節税するには、原則年末調整を行う必要があります。iDeCoに加入しているだけでは、税制優遇を受けられません。年末調整で掛金を所得控除することで、所得税や住民税を減額できます。
会社員や公務員の場合だと、勤務先の年末調整でiDeCoの所得控除を行うケースが一般的です。確定申告も利用できますが、年末調整のほうが手続きも比較的簡単で、早い時期に税金の還付を受けられます。
なお、掛金の支払いを事業主払込に設定している場合は、年末調整の手続きは不要です。事業主払込とは、iDeCoの掛金を給与天引きで支払う方法のこと。事業主が所得控除の手続きを担ってくれるので、従業員が年末調整を行う必要はありません。
会社に属していない自営業やフリーランスなどは、そもそも年末調整の仕組み自体を利用できないので、確定申告でiDeCoの所得控除を行ってください。
年末調整・確定申告の書き方や手順を解説
次に、年末調整・確定申告の書き方や手順を詳しく解説します。基本的には自宅に届く小規模企業共済等掛金払込証明書の金額を転記し、勤め先や税務署に提出するだけなので難しく考える必要はありません。
年末調整|会社員・公務員の場合

会社員や公務員の場合は、年末調整でiDeCoの掛金を所得控除するケースが一般的です。
まず、10月以降に国民年金基金連合会から小規模企業共済等掛金払込証明書が届きます。小規模企業共済等掛金払込証明書は、iDeCoで支払った掛金額を証明する書類です。年末調整で原本を使用するので、届いたら大切に保管しておきましょう。
11月末〜12月になると、勤め先から給与所得者の保険料控除申告書が配布されます。小規模企業共済等掛金控除の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄に、小規模企業共済等掛金払込証明書の合計金額を転記しましょう。
あとは給与所得者の保険料控除申告書に小規模企業共済等掛金払込証明書を添付し、担当者に提出すれば手続きは完了です。
年末調整の細かな手順や提出期限は、会社によって異なります。手続きに不安がある場合は、担当部署に詳細を問い合わせておくとよいでしょう。

iDeCoを始めるには、金融機関に口座を開設する必要がありますが、一般的に手続き完了まで1か月半〜2か月半かかります。
小規模企業共済等掛金控除証明書の発行時期は、初回の掛金の引き落としが10月だった場合は、11月下旬ごろ。11月が初回の掛金の引き落としの場合は、12月末ごろです。引き落としが10月の場合は年末調整に間に合うものの、11月以降になると翌年の扱いになる可能性があります。
また、金融機関よっては10月引き落としでも年末に証明書を受け取れないことも。9月までに初回の掛け金の引き落としができるよう、早めに準備することが大切です。
確定申告|自営業者・フリーランスの場合

自営業やフリーランスの場合は年末調整ではなく、確定申告で所得控除の手続きを行います。
まずは、税務署や役所、国税庁の公式サイトなどから確定申告書を入手しましょう。次に、確定申告書第一表「小規模企業共済等掛金控除⑭」の欄に、小規模企業共済等掛金払込証明書の掛金合計金額を転記します。
第二表右上の「保険料等の種類」欄には「個人型確定拠出年金」と記載してください。「支払い保険料等の計」と「うち年末調整等以外」の欄はどちらも、小規模企業共済等掛金払込証明書の掛金合計金額を記入しましょう。
最後に、小規模企業共済等掛金払込証明書を台紙に貼り付け、確定申告書と合わせて税務署に提出してください。
確定申告書の受付期間は、原則毎年2月16日から3月15日です。パソコンやスマートフォンなどによる電子申請も可能なので、有効に活用しましょう。

これまでは、所得の種類など申告者の状況に応じて、確定申告書Aと確定申告書Bが使い分けられていましたが、2023年から確定申告書の様式が統一されます。
年末調整に間に合わないときは確定申告でも掛金を所得控除できる

勤め先の年末調整に間に合わないときは、確定申告でも掛金を所得控除できます。年末調整での申告を忘れていた場合や、年末調整までに小規模企業共済等掛金払込証明書が届かない場合でも、焦る必要はありません。
まずは、確定申告書第一表「小規模企業共済等掛金控除⑭」の欄に、小規模企業共済等掛金払込証明書の掛金合計金額を転記します。第二表右上の「保険料等の種類」欄には「個人型確定拠出年金」と記入し、「支払い保険料等の計」と「うち年末調整等以外」の欄は小規模企業共済等掛金払込証明書の掛金合計金額を転記してください。
最後に、確定申告書に小規模企業共済等掛金払込証明書を添付して必要書類を準備し、提出すれば手続き完了です。
確定申告に間に合わなかった場合も、所得税の還付は5年以内なら遡って申告できます。提出期限の定めはありませんが、速やかに確定申告書を作成して税務署に提出しましょう。
iDeCoの年末調整でいくら戻る?減税額をシミュレーション

年収450万円、月々の掛金を2万円と仮定した場合、iDeCoの年末調整によって所得税は1年で16,122円、住民税は24,000円の節税が可能です。仮に20歳でiDeCoに加入し、65歳までの45年間継続した場合は、所得税は合計で725,490円、住民税は1,080,000円も節税できます。
年末調整による還付額は、掛金や課税所得の金額によって変動する仕組みです。年末調整でiDeCoの掛金を所得控除すれば課税対象となる所得を減らせるため、その分払いすぎていた税金が還付されます。
なお、実際に戻ってくるのは所得税のみであり、住民税の減額は翌年6月以降の納税時に反映されるため覚えておきましょう。
ちなみに、通常投資で得た利益には約20%の税金が発生しますが、iDeCoで得た利益には税金がかからず税制優遇されるため、その分の恩恵も受けることが可能です。1年間で得られる税制優遇額は40,122円、45年間で1,805,490円にものぼります。
iDeCoでいくら税金が戻ってくるかは、iDeCoの公式サイトで簡単にシミュレーションが可能です。自分の年収や年齢にあわせ、シミュレーションを試してみてください。

iDeCoはほかの制度に比べて税制優遇が大きい制度といえます。特に掛金が全額所得控除に算入できるのは、大きなメリットといえるでしょう。
iDeCoの年末調整に関するよくある質問
最後に、iDeCoの年末調整に関してよくある質問を紹介します。同様の疑問を抱えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
税金はどのように戻ってくる?

年末調整を行った場合は、払いすぎていた所得税が12月~翌年1月ごろに還付されます。受取方法は勤務先によって異なりますが、12月の給与と合わせて振り込まれるケースが一般的です。
確定申告を利用した場合は、還付までに1か月~1か月半程度かかるので注意しましょう。オンラインで申告できるe-Taxを使えば3週間程度で処理されるので、還付を急ぐ場合は有効に活用してください。
なお、iDeCoで所得控除を行っても住民税は還付されません。減税された分は、翌年6月以降の住民税に反映されます。
小規模企業共済等掛金払込証明書はいつ届く?

小規模企業共済等掛金払込証明書の発送時期は、掛金の初回引き落としがいつかによって異なります。基本的な発送時期は10月下旬ですが、初回引き落としが10月以降になると11月から翌年1月までの各月に発送されることを覚えておきましょう。
初回の引き落としが1~9月なら、10月下旬に発送されます。10月以降に引き落としが始まる場合は、翌月の下旬が発送予定時期です。10月に初回引き落としがあると、証明書が発送されるのは11月下旬にずれ込んでしまいます。
細かな日程が金融機関の公式サイトで公開されるので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
なお、事業主払込の場合だと、証明書は発行されません。事業主払込で掛金を支払っていれば年末調整や確定申告の必要もないので、支障が生じることはないでしょう。
小規模企業共済等掛金払込証明書は再発行できる?

小規模企業共済等掛金払込証明書を誤って破棄したり、紛失してしまったりした場合は、再発行が可能です。iDeCoの口座を開設している金融機関に、小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書を提出してください。
申請書は、金融機関の公式サイトからダウンロードできることがほとんどです。再発行には2~3週間程度かかるので、早めに手続きしておくことをおすすめします。
iDeCoで資産形成するなら金融機関選びも重要!ランキングをチェック
iDeCoでお得に資産形成するなら、口座を開設する金融機関選びも重要です。それぞれ手数料や商品ラインナップなどが異なるため、自分に合った金融機関を選択する必要があります。
iDeCoの口座を開設できる金融機関は数多く存在するので、どれを選んでいいのか迷ってしまう人もいるでしょう。以下の記事では、iDeCo口座の開設におすすめの金融機関をランキング形式で紹介しています。
金融機関選びのコツなども解説しているので、これかiDeCoを始める人はぜひチェックしてみてください。
本サイトは情報提供が目的であり、個別の金融商品に関する契約締結の代理や媒介、斡旋、推奨、勧誘を行うものではありません。本サイト掲載の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いません。
人気ideco関連のお役立ちコンテンツ
iDeCoと個人年金保険はどっちがおすすめ?違いやメリット・デメリットを解説
将来に向けた資産形成ができる、iDeCoと個人年金保険。老後資金を確保するためにどちらかをはじめたいと考えているものの、どちらがよいかわからず申し込みに踏み切れない人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、iDeCoと個人年金保険の違いやそれぞれのメリット・デメリットについて解説します。どち...
ideco
iDeCoの利益確定のタイミングは?スイッチングと配分変更の違いや手数料について解説
自分で金融商品を運用して資産形成を行うiDeCo。リスクを避けて資産を確保するために、こまめに売却して利益確定をしたほうがいいのかなど、運用方法に不安を感じている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、iDeCoで利益確定をするタイミングや手段について詳しく解説します。iDeCoを運用する...
ideco
iDeCoは転職・退職したらどうなる?手続きせずに放置した場合についても解説
転職・独立・退職時に手続きが必要なiDeCo(個人型確定拠出年金)。転職したら加入中のiDeCoがどうなるのか、必要な手続きがあるのか知りたいと思っている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、転職したら今までのiDeCoがどうなるのかについてわかりやすく解説します。職場変更したときの対処...
ideco
iDeCoは元本割れのリスクがある?元本確保型と元本変動型について解説
老後の資産形成に役立つとして注目されている私的年金制度、iDeCo。節税効果の高さや投資への関心の高まりから、加入を検討している人も多いのではないでしょうか。しかしiDeCoには元本割れのリスクがあると聞き、不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、iDeCoは元本割れする可...
ideco
iDeCoの掛け金は月5000円では意味ない?最低金額でも得する方法や注意点を解説
毎月一定額を積み立てて老後に備える私的年金制度、iDeCo。掛け金は月々5,000円から設定できますが、最低金額で積み立てても意味がないと考えて、始めていない人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、月5,000円だけでもiDeCoに拠出する意味はあるのかについて解説します。5,000円しか...
ideco
新着ideco関連のお役立ちコンテンツ
iDeCoの年代別おすすめポートフォリオは?資産配分や商品の選び方を解説
iDeCoの運用にはポートフォリオの設定が重要だと聞いたことがあるものの、難しそうだと感じて加入をためらっている人もいるのではないでしょうか。自分に合ったポートフォリオを組まずにiDeCoの運用をはじめると、思ったように資産形成できない可能性があります。そこで今回は、年代別にiDeCoのおすす...
ideco
企業型確定拠出年金からiDeCoに移換する方法は?金融機関を変更するメリット・デメリットも解説
老後に向けた資産形成のために、加入者が増えているのが私的年金制度iDeCo。積み立てを継続しているものの、転職や退職にあたって、どのような手続きをすればよいかわからず困っている人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、企業型確定拠出年金からiDeCoに移管する方法や、その逆のケースについて解...
ideco
iDeCoの掛金の上限は?月々の掛金の平均・目安も解説
公的年金にプラスして給付を受けられるiDeCo。加入を検討しているものの、掛金の上限がわからない、掛金の目安を知りたいなど、さまざまな疑問が生じてしまい、申し込みに踏み切れない人も多いはずです。本記事では、iDeCoの掛金の上限を徹底的に解説します。掛金の平均や目安を決める方法なども紹介するの...
ideco
iDeCoは個人事業主・自営業・フリーランスにおすすめ?税制優遇など活用方法を解説
老後に向けた資産形成の重要性が高まるなか、注目が集まるiDeCo。会社員に比べて年金額が少ない個人事業主や自営業者で、加入を検討している人も多いのではないでしょうか。しかしiDeCoのメリットやデメリットがよくわからず、加入まで踏み切れないという人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、iD...
ideco
iDeCoは本当にデメリットしかない?入るべき理由やメリット、注意点を解説
長期的に積み立てて老後の生活資金にできる、確定拠出年金のiDeCo(イデコ)。入らないほうがいいなどのウワサを聞いていて、実際のところはどうなのか、入ったほうがいいのか気になっている人も少なくないはずです。そこで今回は、iDeCoのデメリットやメリットについてわかりやすく解説します。iDeCo...
ideco
iDeCoは何歳から何歳まで加入できる?50・60代から始めても遅くないのかも解説
年金制度改正法の改正で、老後の資産形成がよりしやすくなったiDeCo(イデコ)。入る際に年齢制限はあるのか、50・60代で加入しても遅くないのか、気になっている人も少なくないようです。そこで今回は、iDeCoに加入できる年齢の条件についてわかりやすく解説します。何歳からいつまでに加入すればメリ...
ideco
会社員でもiDeCoに加入したい!上限や会社に知られない方法も解説
毎月お金を積み立て、老後のための資産形成ができる私的年金制度iDeCo(イデコ)。フリーランス向けのイメージがありますが、会社員も加入できます。しかし、加入を検討しているものの、会社員が加入するための条件や方法がわからず悩んでいる人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、会社員がiDeCoに...
ideco
iDeCoと企業型確定拠出年金の違いは?併用はできる?マッチング拠出とiDeCoの違いについても解説
老後の資産形成をサポートする、私的年金制度iDeCo。勤務先で企業型確定拠出年金に加入しているが、iDeCoも気になっているという人もいるのではないでしょうか。スムーズに資産形成をするためにも、可能であれば併用したいですよね。そこで今回は、iDeCoと企業型確定拠出年金の違いや併用の可否につい...
ideco
iDeCoと国民年金基金はどっちがいい?併用は可能?個人事業主向けの年金について解説
個人事業主が老後資金を貯めるときに、選択肢に挙がるのがiDeCoと国民年金基金。しかし、違いがよくわからず、どちらで積み立てるべきか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、個人事業主の資産形成にあたって、iDeCoと国民年金基金のどちらを選べばよいかについて解説します。それぞれの...
ideco
iDeCoの運用利回りの平均は?利率や計算方法も解説
老後資金を積み立ながら節税もできる、お得な私的年金制度、iDeCo(イデコ)。始めてみようと考えているものの、運用利回りがどのくらいなのか気になっている人もいるのではないでしょうか。どの程度の運用成果が見込めるのかわからないと、なかなか手を出しにくいですよね。そこで今回は、iDeCoの運用利回...
ideco
