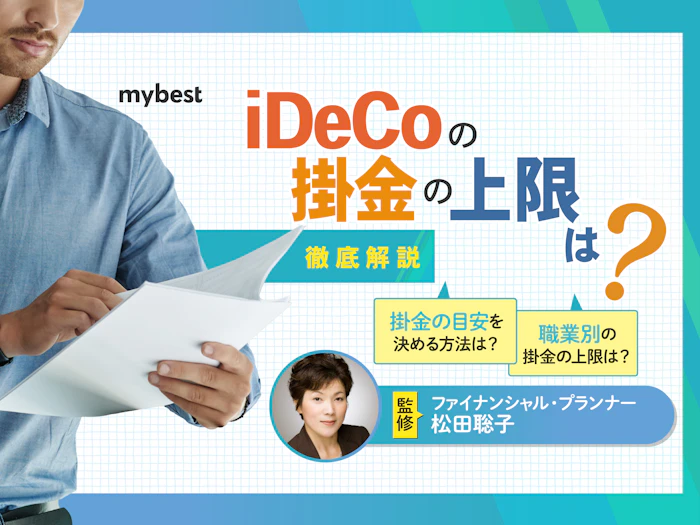
iDeCoの掛金の上限は?月々の掛金の平均・目安も解説
公的年金にプラスして給付を受けられるiDeCo。加入を検討しているものの、掛金の上限がわからない、掛金の目安を知りたいなど、さまざまな疑問が生じてしまい、申し込みに踏み切れない人も多いはずです。
本記事では、iDeCoの掛金の上限を徹底的に解説します。掛金の平均や目安を決める方法なども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

明治大学法学部卒業後、ITエンジニアとして自治体や金融機関のシステム開発に従事。その後、国内生保にて法人の福利厚生等のコンサルティング営業に転身。2009年より独立系FPとして開業し、一般的な個人向けFP相談の他、法人オーナー対象のコンサルを行っている。現在はコンサル経験を活かした金融ライターとしても活動中。

大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
iDeCoの掛金上限額はいくら?職業別に解説

iDeCoには掛金の上限額があります。職業などの加入区分によって異なるため、iDeCoをはじめるときは、まず自分の加入区分を確認したうえで掛け金の上限を把握しましょう。詳細は以下のとおりです。
- 第1号被保険者の自営業者やフリーランスなど:月68,000円(年816,000円)
- 第2号被保険者の公務員:月額20,000円(年240,000円)
- 第2号被保険者の会社員で企業年金がない人:月23,000円(年276,000円)
- 第2号被保険者の会社員で企業型確定拠出年金のみに加入している人:月20,000円(年240,000円)
- 第2号被保険者の会社員で確定給付企業年金のみに加入または確定給付企業年金と企業型確定拠出年金の両方に加入している人:月額20,000円(年240,000円)
- 第3号被保険者の専業主婦(夫):月23,000円(年276,000円)
- 国民年金の任意加入被保険者:月68,000円(年816,000円)
「国民年金の任意加入被保険者」とは、60歳以上65歳未満で、国民年金の保険を納付した期間が480か月に達していない人、20歳以上65歳未満の海外居住者で国民年金の保険を納付した期間が480か月に達していない人のうち、国民年金に任意で加入している人のことです。
なお、2024年12月1日に制度が改正され、確定給付型年金に加入している会社員や公務員は、iDeCo掛金の上限が12,000円から20,000円に引き上げられました。ただし、企業型確定拠出年金・確定給付型年金・iDeCoの掛け金額が合算して月額55,000円を超えることはできません。たとえば企業型確定拠出年金の掛金を35,000円以上に設定している会社員は、iDeCoの掛金を55,000円以上にすることができないため、20,000円を下回ります。
自分に当てはまるものがどれなのか判断するのが難しい場合は、iDeCo公式サイトの「カンタン加入診断」で確認してください。簡単な質問に答えるだけですぐに結果がでますよ。
iDeCo掛金の月額平均はどのくらい?

2022年10⽉時点、iDeCo掛⾦の⽉額は全体平均で16,201円です。
加⼊区分別の平均は、第1号被保険者が28,900円、第2号被保険者が14,534円。第2号被保険者を公務員に限定すると、11,019円です。第3号被保険者は15,474円、国⺠年⾦の任意加⼊被保険者は51,586円が平均だと「国民年金基金連合会」でデータが出ています。
第1号被保険者の自営業者などは比較的多く拠出していますが、もともと手厚い年金制度がある第2号被保険者のサラリーマンや公務員は掛金が低い傾向にあります。
第3号被保険者の専業主婦などは、半分以上が20,000円以上の掛金を設定しているのも特徴的です。国民年金の任意加入被保険者は、大半の人が上限に近い額を拠出しています。
iDeCo掛金の目安を決める方法
次に、iDeCo掛金の目安を決める方法を解説します。
ライフサイクルに合わせて決める

拠出した掛金は原則60歳になるまで引き出せないため、ライフサイクルも考慮して掛金を決めることが重要です。
今の生活に支障がない範囲で掛金を設定した場合でも、まとまったお金を要するタイミングは誰にでも訪れるため、近い将来拠出するのが難しくなる可能性は十分あります。
とくに家族がいる人は子どもの進学や住宅の購入、両親の病気や介護などに関わる大きな支出が生じる可能性も高いので、いざというときのお金は手元に残しておくのがおすすめです。まずは今後必要になるであろう支出を整理し、そのうえで無理のない範囲で掛金を決めてください。
iDeCo掛金の金額は、1年に1回だけ変更することが可能です。収入や家族構成などに変化が生じた場合は、その都度金額を見直すようにしましょう。

iDeCo加入は家計を見直すチャンスです。ムダな保険はないか、使っていない月額課金サービスはないか見直してみましょう。ここで見直した数千円が将来大きな差を生みますよ。
目標積立額や運用期間から逆算して決める

掛金を決める際には、60歳以降に受け取りたい目標積立額や、今からiDeCoを始めた場合の運用期間などをもとに逆算するのがおすすめです。シミュレーションは簡単に行えるので、パターンごとに当てはめて実施してみてください。
以下では、ろうきんのシミュレーションを用いています。自分でやってみたい人は、ろうきんのサイトからチェックしてみてください。
たとえば、30歳から60歳までの30年間を利回り3%で運用した場合は、以下のようなシミュレーションができます。
- 積立額5,000円:運用益109万3,565円、受取額289万3,565円
- 積立額10,000円:運用益218万7,130円、受取額578万7,130円
- 積立額20,000円:運用益437万4,260円、受取額1,157万4,260円
50歳から60歳までの10年間を利回り3%で運用した場合は、以下のようにシミュレーションが可能です。
- 積立額5,000円:運用益9万7,239円、受取額69万7,239円
- 積立額10,000円:運用益19万4,479円、受取額139万4,479円
- 積立額20,000円:運用益38万8,959円、受取額278万8,959円
実際にはより高い利回りで運用できる可能性もありますが、シミュレーションを行う際には控えめな3%を目安に計算しておくと安心です。

- 積立額5,000円:運用益227万6,879円、受取額407万6,879円
- 積立額10,000円:運用益455万3,759円、受取額815万3,759円
- 積立額20,000円:運用益910万7,518円、受取額1,630万7,518円
iDeCoで資産運用するうえで重要なポイント
最後に、iDeCoで資産運用するうえで重要なポイントをチェックしましょう。
掛金は定期的に見直しをする

iDeCoの掛け金は、定期的に見直しをしてください。仕事の昇進や転職、結婚などにより申し込み時点からライフサイクルが変化すると、収入に増減があったり、ローンの状況が変わったりするためです。
お金に余裕がある場合は掛金を上限額まで増額させ、税制優遇を最大限に受けられるようにしましょう。iDeCoで運用しているお金は原則60歳まで引き出せないので、その時々の収支を考慮しながら無理なく拠出できる額を設定することも大切です。
口座を開設している金融機関に加入者掛金額変更届を提出すれば、先述の通り、掛金を1年に1回だけ変更することができます。変更届はiDeCo公式サイトから入手できますが、加入区分ごとに様式が異なるので注意が必要です。
なお、2024年12月に制度改正でiDeCoの掛金を拠出できなくなった場合は、条件を満たせば脱退一時金が受給できるようになりました。受給条件は下記のとおりです。
<脱退一時金の受給条件>
- 60歳未満であること
- 企業型DCの加入者でないこと
- iDeCoに加入できない者であること
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、または個人別管理資産の額が25万円以下であること
- 最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
(引用:厚生労働省)

iDeCoの運用は基本的に老後資金準備のための長期運用です。長期運用では積極的にリスクを取っても運用期間中にリターンの振れ幅が収まり、安定する傾向があります。そのため、途中の値下がりなどは気にせずに運用するとよいとされていますよ。
しかし、iDeCoの運用には60歳というゴールがあり、受け取り時にマイナスになるのは避けるべきです。そのため、50歳以降は過度にリスクを取り過ぎずに安定運用を目指すほうがよいでしょう。つまり、運用商品の組み合わせは時期によって変更する必要があるといえます。
iDeCoでは毎月の掛金で買い付ける商品の組み合わせを変更できるだけでなく、買い付けた商品の入れ替え(スイッチング)も可能です。
たとえば、値上がりしている資産を定期預金などに入れ替えることもできます。
新しいNISAと併用して資産運用することも検討する

iDeCoは年間240,000〜816,000円までしか拠出できませんが、新しいNISAの成長投資枠は年間240万円、つみたて投資枠は年間120万円まで拠出が可能です。
新しいNISAはiDeCoと同様に運用益が非課税になるので、お金に余裕がある人は併用して資産運用することも検討してみましょう。
原則60歳まで引き出しができないiDeCoとは異なり、新しいNISAには引き出し制限もありません。冠婚葬祭や病気、介護など急にお金が必要になったときにもすぐに現金化できるので、老後資金の確保以外が目的の場合でも気軽に資産運用を始めることができます。
新しいNISAについて詳しく知りたい人は、以下の記事をチェックしてみてください。
iDeCoの商品・金融機関のランキングはこちら!
以下の記事では、iDecoのおすすめの金融機関・商品や選び方を紹介しています。iDecoについて理解が深まったものの、実際にどの金融機関でどの商品を運用したらよいのかわからないという人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
本サイトは情報提供が目的であり、個別の金融商品に関する契約締結の代理や媒介、斡旋、推奨、勧誘を行うものではありません。本サイト掲載の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いません。
人気ideco関連のお役立ちコンテンツ
iDeCoと個人年金保険はどっちがおすすめ?違いやメリット・デメリットを解説
将来に向けた資産形成ができる、iDeCoと個人年金保険。老後資金を確保するためにどちらかをはじめたいと考えているものの、どちらがよいかわからず申し込みに踏み切れない人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、iDeCoと個人年金保険の違いやそれぞれのメリット・デメリットについて解説します。どち...
ideco
iDeCoの利益確定のタイミングは?スイッチングと配分変更の違いや手数料について解説
自分で金融商品を運用して資産形成を行うiDeCo。リスクを避けて資産を確保するために、こまめに売却して利益確定をしたほうがいいのかなど、運用方法に不安を感じている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、iDeCoで利益確定をするタイミングや手段について詳しく解説します。iDeCoを運用する...
ideco
iDeCoは転職・退職したらどうなる?手続きせずに放置した場合についても解説
転職・独立・退職時に手続きが必要なiDeCo(個人型確定拠出年金)。転職したら加入中のiDeCoがどうなるのか、必要な手続きがあるのか知りたいと思っている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、転職したら今までのiDeCoがどうなるのかについてわかりやすく解説します。職場変更したときの対処...
ideco
iDeCoは元本割れのリスクがある?元本確保型と元本変動型について解説
老後の資産形成に役立つとして注目されている私的年金制度、iDeCo。節税効果の高さや投資への関心の高まりから、加入を検討している人も多いのではないでしょうか。しかしiDeCoには元本割れのリスクがあると聞き、不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、iDeCoは元本割れする可...
ideco
iDeCoの掛け金は月5000円では意味ない?最低金額でも得する方法や注意点を解説
毎月一定額を積み立てて老後に備える私的年金制度、iDeCo。掛け金は月々5,000円から設定できますが、最低金額で積み立てても意味がないと考えて、始めていない人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、月5,000円だけでもiDeCoに拠出する意味はあるのかについて解説します。5,000円しか...
ideco
新着ideco関連のお役立ちコンテンツ
iDeCoの年代別おすすめポートフォリオは?資産配分や商品の選び方を解説
iDeCoの運用にはポートフォリオの設定が重要だと聞いたことがあるものの、難しそうだと感じて加入をためらっている人もいるのではないでしょうか。自分に合ったポートフォリオを組まずにiDeCoの運用をはじめると、思ったように資産形成できない可能性があります。そこで今回は、年代別にiDeCoのおすす...
ideco
企業型確定拠出年金からiDeCoに移換する方法は?金融機関を変更するメリット・デメリットも解説
老後に向けた資産形成のために、加入者が増えているのが私的年金制度iDeCo。積み立てを継続しているものの、転職や退職にあたって、どのような手続きをすればよいかわからず困っている人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、企業型確定拠出年金からiDeCoに移管する方法や、その逆のケースについて解...
ideco
iDeCoは個人事業主・自営業・フリーランスにおすすめ?税制優遇など活用方法を解説
老後に向けた資産形成の重要性が高まるなか、注目が集まるiDeCo。会社員に比べて年金額が少ない個人事業主や自営業者で、加入を検討している人も多いのではないでしょうか。しかしiDeCoのメリットやデメリットがよくわからず、加入まで踏み切れないという人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、iD...
ideco
iDeCoは本当にデメリットしかない?入るべき理由やメリット、注意点を解説
長期的に積み立てて老後の生活資金にできる、確定拠出年金のiDeCo(イデコ)。入らないほうがいいなどのウワサを聞いていて、実際のところはどうなのか、入ったほうがいいのか気になっている人も少なくないはずです。そこで今回は、iDeCoのデメリットやメリットについてわかりやすく解説します。iDeCo...
ideco
iDeCoは何歳から何歳まで加入できる?50・60代から始めても遅くないのかも解説
年金制度改正法の改正で、老後の資産形成がよりしやすくなったiDeCo(イデコ)。入る際に年齢制限はあるのか、50・60代で加入しても遅くないのか、気になっている人も少なくないようです。そこで今回は、iDeCoに加入できる年齢の条件についてわかりやすく解説します。何歳からいつまでに加入すればメリ...
ideco
iDeCoは年末調整・確定申告が必要?所得控除でいくら戻るのか解説
必要に応じて年末調整が必要なiDeCo。iDeCoに税制優遇があると知って始めてみたものの、年末調整や確定申告を行う必要はあるのか、どのくらい税金が戻ってくるのかなど、さまざまな疑問を感じている人も多いのではないでしょうか。本記事では、iDeCoの年末調整や確定申告の必要性を解説します。減税額...
ideco
会社員でもiDeCoに加入したい!上限や会社に知られない方法も解説
毎月お金を積み立て、老後のための資産形成ができる私的年金制度iDeCo(イデコ)。フリーランス向けのイメージがありますが、会社員も加入できます。しかし、加入を検討しているものの、会社員が加入するための条件や方法がわからず悩んでいる人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、会社員がiDeCoに...
ideco
iDeCoと企業型確定拠出年金の違いは?併用はできる?マッチング拠出とiDeCoの違いについても解説
老後の資産形成をサポートする、私的年金制度iDeCo。勤務先で企業型確定拠出年金に加入しているが、iDeCoも気になっているという人もいるのではないでしょうか。スムーズに資産形成をするためにも、可能であれば併用したいですよね。そこで今回は、iDeCoと企業型確定拠出年金の違いや併用の可否につい...
ideco
iDeCoと国民年金基金はどっちがいい?併用は可能?個人事業主向けの年金について解説
個人事業主が老後資金を貯めるときに、選択肢に挙がるのがiDeCoと国民年金基金。しかし、違いがよくわからず、どちらで積み立てるべきか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、個人事業主の資産形成にあたって、iDeCoと国民年金基金のどちらを選べばよいかについて解説します。それぞれの...
ideco
iDeCoの運用利回りの平均は?利率や計算方法も解説
老後資金を積み立ながら節税もできる、お得な私的年金制度、iDeCo(イデコ)。始めてみようと考えているものの、運用利回りがどのくらいなのか気になっている人もいるのではないでしょうか。どの程度の運用成果が見込めるのかわからないと、なかなか手を出しにくいですよね。そこで今回は、iDeCoの運用利回...
ideco
