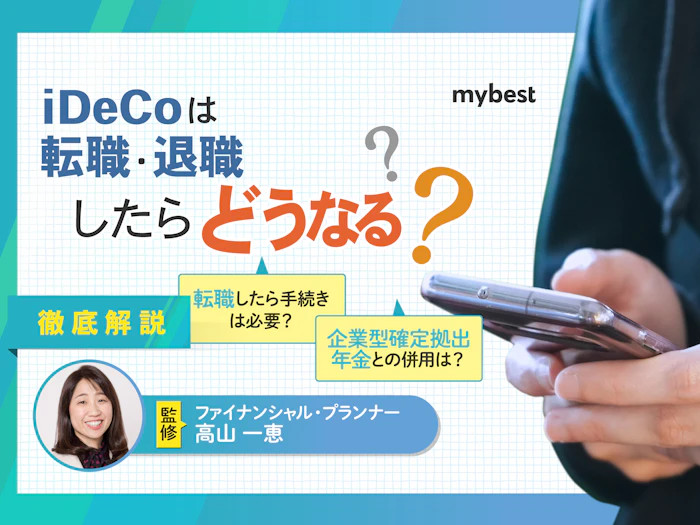
iDeCoは転職・退職したらどうなる?手続きせずに放置した場合についても解説
転職・独立・退職時に手続きが必要なiDeCo(個人型確定拠出年金)。転職したら加入中のiDeCoがどうなるのか、必要な手続きがあるのか知りたいと思っている人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、転職したら今までのiDeCoがどうなるのかについてわかりやすく解説します。職場変更したときの対処法や、手続きをせずに放置したらどうなるかについても解説するので、転職時の手続きに役立ててください。

2005年に女性向けFPオフィス(株)エフピーウーマンを創業。10年間取締役を務めた後、現職へ。女性向けWEBメディア『FP Cafe®』や『Mocha』を運営。また、『Money&You TV』や「マネラジ。」「Voicy」などでも情報を発信しているうえに、全国での講演活動、執筆、マネー相談を通じて、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。「はじめてのNISA &iDeCo」(成美堂出版)「1日1分読むだけで身につく お金大全100」(自由国民社)」など著書多数。

大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
転職したら加入中のiDeCoはどうなる?
はじめに、転職したときに現在加入しているiDeCoはどうなるのか、シチュエーションごとに解説します。
転職先に企業型確定拠出年金がある場合
転職先の企業に、企業が拠出した掛け金で金融商品を運用できる企業型確定拠出年金がある場合は、以下の4つのうちどれかを選ぶ必要があります。
iDeCoの資産を企業型確定拠出年金に移換

iDeCoへの同時加入が認められていない場合に、企業型確定拠出年金に加入するとiDeCoの加入資格を失います。iDeCoで積み立てて運用していた資産は、企業型確定拠出年金の口座に移動させて運用が可能。移換するときはiDeCoで運用していた金融商品を一度売却し、企業型確定拠出年金で設定されている商品で運用します。

2022年10月の法改正で、企業型DC加入者は、規約の定めがなくてもiDeCoとの併用が可能になりました。
ただし、併用するには、企業型DCとiDeCoの掛金額が月55,000円以下であり、掛金の拠出が各月拠出であること。加えて、企業型DCのマッチング拠出を利用していないことの3つの条件を満たす必要があります。
iDeCoと企業型確定拠出年金の両方に加入する

ただし、iDeCoと企業型確定拠出年金は、両方とも原則として60歳まで引き出すことができません。iDeCoと企業型確定拠出年金の2つだけで資産形成のすべてを行うと、突発的な出費に対応できない危険性があります。
資産形成にあてられるお金の一部をほかの方法に変えておき、急な出費が必要になった場合に支払いができるようにしておくのも選択肢の1つです。
運用指図者としてiDeCoを継続

iDeCoに加入している人が、転職先の企業で企業型確定拠出年金に加入した場合に、企業型確定拠出年金に資産を移換せず運用指図者としてiDeCoを継続することもできます。
運用指図者とは、積み立てを行わずに資産の運用だけを続ける状態のことです。金融商品の売買をしないので、別の商品に乗り換えて利益を失う機会損失の心配も少なくなります。
ただし、運用指図者になるとiDeCoの掛け金を積み立てないので、運用益が思ったほど伸びない可能性がある点には注意してください。
例えばiDeCoの資産が100万円あり、年利5%で運用している場合に、毎月2万円の掛け金を積み立てた場合と積み立てなかったケースで、1年後の運用益をそれぞれ考えてみましょう。
まず毎月2万円の掛け金を積み立てた場合は、24万円資産が増えるので、運用益は「124万円 × 年利5% = 6万2,000円」です。
一方で積み立てをしない場合だと、資産100万円を年利5%で運用するだけなので、運用益は「100万円 × 年利5% = 5万円」に。積み立てをした場合と積み立てをしなかった運用指図者を比較すると、1年間で1万円を超える差が出ます。
掛け金を積み立てて資産を増やした場合と、運用益だけで資産を増やした場合を事前に計算し、将来どの程度の資産を手に入れたいのか考え、運用指図者になるかを決めることをおすすめします。

iDeCoの運用指図者となることもできますが、運用している間は手数料がかかり続けます。加えて、掛金を拠出することはできないので、基本的に企業型DCへ移して運用したほうがよいでしょう。
確定給付企業年金への移換も可能

確定給付企業年金は、運用した成果が給付額に達していない場合は企業が負担してくれるので、従業員にとってメリットの大きい仕組みです。企業型確定拠出年金と異なり、特に投資の知識も必要ないのもポイント。実際にiDeCoから移換ができるかどうかは、転職先の職場の担当者に確認してみてください。
転職先に企業型確定拠出年金がない場合

iDeCoは老後の資産形成を行うための制度です。転職先に企業型確定拠出年金が用意されておらず、自分で老後のために資産形成をしておきたいなら、iDeCoを継続して積み立てておくといいでしょう。
会社員にならず、自営業・公務員・専業主婦・無職などになる場合も、同じようにiDeCoを続けられます。iDeCoの掛け金を拠出できる余裕があるなら、そのままiDeCoを続けて掛金を積み立てておくと老後に備えることが可能です。
転職時に必要なiDeCoの手続き
iDeCoを続けるかどうかに関わらず、転職した場合は手続きが必要です。以下では、実際に必要な手続きについて解説します。
転職で企業型確定拠出年金に加入する場合
iDeCoから企業型確定拠出年金に移換する場合

転職先の企業型確定拠出年金にiDeCoの資産を移動させる場合は、iDeCoの加入資格を失った手続きと、企業型確定拠出年金への加入手続きを行ってください。
iDeCoの加入資格を失った手続きでは、iDeCoの加入資格を失った年月日や理由などを記入した「加入者資格喪失届(K-015)」と、iDeCoの資格を失ったことを証明する「個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書(K-108)」の2つを作成する必要があります。
各書類は、iDeCoの加入手続きを行った金融機関(運営管理機関)に連絡して入手しましょう。上記2つの書類を作成する際には、記入する内容で注意する点があります。
加入者資格喪失届(K-015)に記入するiDeCoの資格喪失理由は、「04:運用指図者になるため」を選んでください。
個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書(K-108)の記入の際は、転職先の企業が厚生労働大臣から受けた承認番号が必要になります。承認番号を企業にあらかじめ確認しておきましょう。
作成した加入者資格喪失届(K-015)と個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書(K-108)は、両方とも運営管理機関に送付してください。
企業型確定拠出年金にiDeCoの資産を移動させる手続きは、各転職先で行います。企業の制度・扱っている金融商品・加入するための手続きについて通知があるので、不明な点があれば転職先の人事や労務などの担当者に尋ねましょう。
iDeCoと企業型確定拠出年金に同時加入する場合

- 会社員が別の企業に転職する場合
勤務先の変更を届け出る「加入者登録事業所変更届(K-011)」と、転職先で記入してもらう必要がある「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A)」を用意してください。
- 公務員が企業に転職する場合
加入者登録事業所変更届(K-011)に加えて、事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A)を転職先で記入してもらう必要があります。
- 自営業や専業主婦が企業に転職する場合
国民年金の被保険者の種類が変わるので「加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)(K-010B)」を作成し、転職先の企業に「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A)」を記入してもらってください。
各手続きに必要な書類は、iDeCoの加入手続きを行った金融機関(運営管理機関)に連絡して入手しましょう。作成した書類は、書類を入手した運営管理機関に送付してください。
この手続きにおいても、記入する内容で注意する点があります。
加入者登録事業所変更届(K-011)では、転職前と転職後の両方の企業の「登録事業所番号」を記載する必要があります。
加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)(K-010B) では、転職後の企業の番号が必要です。それぞれ、人事や総務などの担当者に確認しておきましょう。
iDeCoの手続きに加え、転職先の企業型確定拠出年金にも入ることになるので、企業の担当者の指示に従って加入手続きを進めましょう。
転職で企業型確定拠出年金に加入しない場合
企業確定拠出年金がある企業に勤務する場合、原則加入することになりますが、なかには選択できるケースも。転職先で、企業型確定拠出年金に加入しない場合のiDeCoの手続き方法も確認しておきましょう。
iDeCoのみ継続加入する場合

転職先の企業型確定拠出年金に入らず、iDeCoを引き続き積み立てる場合も、勤務先と国民年金の種類の変更に応じて手続きをする必要があります。
手続きをする際のポイントは、前職が会社員・公務員・自営業と専業主婦の3パターンのどれに当てはまるかで、作成する書類の内容が変わることです。自分の前職に合わせた書類を作成し、手続きをしましょう。
- 会社員が別の企業に転職する場合
勤務先の変更を届け出る「加入者登録事業所変更届(K-011)」と、転職先で記入してもらう必要がある「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A)」を用意してください。
- 公務員が企業に転職する場合
加入者登録事業所変更届(K-011)に加えて、事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 (K-101A)を転職先で記入してもらう必要があります。
- 自営業や専業主婦が企業に転職する場合
国民年金の被保険者の種類が変わるので「加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)(K-010B)」を作成し、転職先の企業に「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A)」を記入してもらってください。
各手続きに必要な書類は、iDeCoの加入手続きを行った金融機関(運営管理機関)に連絡して入手しましょう。作成した書類は、書類を入手した運営管理機関に送付してください。
ほかの手続きと同様に、加入者登録事業所変更届(K-011)では、転職前と転職後の両方の企業の「登録事業所番号」を記載する必要があります。
加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)(K010B号) では、転職後の企業の番号が必要です。それぞれ、人事や総務などの担当者に確認しておきましょう。
独立や退職で国民年金の被保険者種別が変わった場合

作成する書類は、自営業・学生・無職になった場合と、専業主婦になった場合で異なるので、自分の属性に合った書類で手続きを行いましょう。
自営業・学生・無職になった場合は、「加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)(K-010A)」を作成してください。
専業主婦になった場合は、「加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)(K-010C) 」を作成します。
上記書類も、iDeCoの加入手続きを行った金融機関(運営管理機関)に連絡して手に入れ、記入が終わったら運営管理機関に送付してください。
ただし、公務員で共済組合に加入している人が独立や退職をした場合は、手続きの方法が異なる可能性があるので注意しましょう。運営管理機関に問い合わせて確認しておいてください。
iDeCoと転職先の企業型確定拠出年金はどっちを選ぶべき?
iDeCoと企業型確定拠出年金には、メリットとデメリットがあります。自分に合っているほうを選ぶことが大切です。
幅広い商品から選んで自由に運用したいならiDeCoがおすすめ

一方で企業型確定拠出年金では、会社から依頼された運営管理機関が選定した金融商品の、1~3商品から選ばないといけない場合も少なくありません。投資の知識がすでにある人や投資したい金融商品が決まっている人には、窮屈に感じる可能性があります。
また、企業型確定拠出年金に資産を移すときは一度売却する必要があり、状況によっては損をしてしまう危険性もあるので注意が必要です。
iDeCoで運用する投資信託などの金融商品は、売却のタイミングで資産額が異なるため、iDeCo開始当初より資産が減ってしまう危険性も。iDeCoから移管する際に、資産を管理している金融機関に手数料を払わなければいけない場合もあります。
売却したときの資産額や手数料などを総合的に考えて、損をしてしまうならiDeCoを継続するのも方法の1つです。
投資に慣れていない人は企業型確定拠出年金がおすすめ

企業型確定拠出年金は、従業員に対して投資教育をすることが企業の努力義務として決まっているので、投資の知識をつけて老後の資産を形成することが可能です。企業型確定拠出年金で選べる金融商品も、iDeCoほど多くないので迷うことが少ないといえます。
企業型確定拠出年金では、掛け金や事務手数料を企業が負担してくれるので、支出を最小限に押さえられるのも利点です。
また、iDeCoのように自分で確定申告や年末調整をする必要がないため、税金関係の手続きを負担に感じることもありません。
掛け金を増やしたいなら併用がおすすめ

企業型確定拠出年金とiDeCoを併用すると、会社にほかの企業年金がなかった場合は、iDeCoで最大月額2万円の積み立てができます。
iDeCoの掛け金は、全額を所得から差し引いて税金を減らせる所得控除の対象になるのもメリット。税金で払うはずだったお金を掛け金に充てれば、掛け金の支払い負担を減らせます。
また、iDeCoのメリットと同じく運用商品の幅が広がるので、企業型確定拠出年金では選べない金融商品をiDeCoで投資して運用することも可能です。

iDeCoでいくら掛金を拠出できるのかは、会社でほかに拠出している企業年金制度の額によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
なお、企業型DCのマッチング拠出を導入している会社の場合、iDeCoとマッチング拠出の併用はできないので、注意が必要です。
iDeCo加入者が転職するときの注意点
続いて、iDeCoの加入者が転職するときの3つの注意点を紹介します。
転職後の職種によっては掛け金の上限が変わることも

iDeCoは、会社員や自営業など職種によって掛け金の上限が違うので、iDeCoを継続する場合でも上限が変わることがあります。
会社員の場合は、企業年金があるかどうかによって上限金額が2パターンに分かれるので、注意してください。
1つ目は、企業型確定拠出年金と確定給付企業年金がない場合で、掛け金の月額上限は2万3千円。2つ目は、企業型確定拠出年金や確定給付企業年金に加入している場合で、どちらか一方、または両方に加入していると月額上限は2万円となります。
会社員以外だと、公務員の上限金額は2万円で、専業主婦は2万3千円です。自営業者の上限が最も高く、6万8千円まで積み立てができます。
転職でiDeCoの加入資格を失っても脱退一時金は受け取れない

例外的に脱退一時金として受け取るなら、以下7つの条件をすべて満たす必要があります。
- 60歳未満であること
- 企業型年金加入者でないこと
- 国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等のiDeCoに加入できない者であること
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 通算拠出期間(※)が1か月以上5年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 最後に企業型確定拠出年金加入者又はiDeCo加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
掛金を拠出していない期間は含みません
(引用:iDeCo公式サイト)
上記の条件すべてに当てはまるケースはなかなかないため、脱退一時金を受け取れる人は少数であることがわかります。
転職で退職金を受け取るとiDeCoの減税措置が使えなくなることも

転職の際に会社から退職金を受け取ると、iDeCoをもらうときに減税措置が使えなくなり、支払う税金が大幅に増える恐れがあるので気をつけてください。iDeCoをもらうときに使える減税措置は、会社からの退職金を受け取るときにも使える退職所得控除です。
退職所得控除とは、会社の退職金やiDeCoの一時金などの収入から、所定の計算を行って一部の金額を差し引くこと。退職所得控除で差し引いた分だけ課税の対象になる退職所得が減少するため、所得税や住民税が少なくなります。会社の退職金とiDeCoの一時金の両方で退職所得控除を適用できれば、支払う税金をそれぞれ大幅に少なくすることが可能です。
ただし、会社からの退職金を先に受け取る場合に、退職所得控除を会社の退職金とiDeCoの一時金の両方に適用するには、退職所得控除の19年ルールを回避する必要があります。
19年ルールは、会社からの退職金を受け取ってから19年以内にiDeCoの一時金を受け取った場合に、退職所得控除が1回しか使えなくなるもの。つまり、iDeCoを受け取るときには退職所得控除が使えず、多額の税金を支払うことになります。
19年ルールを回避するには、遅くとも55歳になるまでに会社からの退職金を受け取っていればOK。iDeCoの受け取りは75歳が上限なので、55歳までに退職金を受け取っておけば75歳でiDeCoをもらえて20年の期間が空き、19年ルールが適用されません。

運用益を大きくできる受け取り方法もありますが、いつまで働くか、そのときの資産状況がどうかなどを総合的に判断することが大切です。
iDeCo加入者が転職の手続きをしないとどうなる?
最後に、iDeCoの加入者が転職時の手続きをしなかったときのリスクを解説します。
転職してもiDeCoを継続する場合

転職後もiDeCoを継続するときに、加入資格に変更があったにもかかわらず手続きをしないと、不要な支出が増える可能性もあるので注意してください。
iDeCoの加入資格になっている国民年金の被保険者種別が変わったり、転職した企業の年金制度に加入したりすると、iDeCoの掛け金上限が変わる場合があります。上限額を超えて預金や投資信託を購入してしまうと、発覚した時点で超過分に相当する預金や投資信託が強制的に売却されるだけでなく、事務手数料が発生して無駄な支払いが増えることに。
加入資格の変更手続きをしないと、掛け金の引き落としが止まって税金面でのデメリットも生じます。
iDeCoの掛け金は追納できないので、引き落としがストップしている間は掛け金を払ったことによる所得控除が利用できません。掛け金を払っていない間はiDeCoの加入期間に数えられないので、iDeCoを一時金でもらうときの退職所得控除も少なくなります。
転職でiDeCoの加入資格を失った場合

転職でiDeCoの加入資格を失ったにも関わらず継続していると、加入者資格の喪失届や掛け金の返金などの手続きが必要になります。
例えば、資格喪失届を出さないまま掛け金が引き落とされてもあとで返還されますが、数千円の手数料を徴収されてしまいます。iDeCoの加入資格を失ったときは、速やかに喪失届を提出しておくのが賢明です。

iDeCoを60歳から受け取る場合には、加入期間は10年以上必要になります。
iDeCoの商品・金融機関のランキングはこちら
以下の記事では、iDeCoにおすすめの金融機関・商品や選び方を紹介しています。iDeCoについて理解が深まったものの、実際にどの金融機関でどの商品を運用したらよいのかわからないという人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
本サイトは情報提供が目的であり、個別の金融商品に関する契約締結の代理や媒介、斡旋、推奨、勧誘を行うものではありません。本サイト掲載の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いません。
人気ideco関連のお役立ちコンテンツ
iDeCoと企業型確定拠出年金の違いは?併用はできる?マッチング拠出とiDeCoの違いについても解説
老後の資産形成をサポートする、私的年金制度iDeCo。勤務先で企業型確定拠出年金に加入しているが、iDeCoも気になっているという人もいるのではないでしょうか。スムーズに資産形成をするためにも、可能であれば併用したいですよね。そこで今回は、iDeCoと企業型確定拠出年金の違いや併用の可否につい...
ideco
企業型確定拠出年金からiDeCoに移換する方法は?金融機関を変更するメリット・デメリットも解説
老後に向けた資産形成のために、加入者が増えているのが私的年金制度iDeCo。積み立てを継続しているものの、転職や退職にあたって、どのような手続きをすればよいかわからず困っている人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、企業型確定拠出年金からiDeCoに移管する方法や、その逆のケースについて解...
ideco
専業主婦(主夫)もiDeCoを始めるべき?加入のメリット・デメリットを解説
老後の資金源を計画的に積み立てられる、個人型確定拠出年金iDeCo。専業主婦(主夫)や無職でも、気になっている人は多いのではないでしょうか?そこで今回は、専業主婦(主夫)や無職の人でもiDeCoに加入できるのかについて詳しく解説します。専業主婦(主夫)や無職の人がiDeCoに加入する条件やメリ...
ideco
iDeCoの年代別おすすめポートフォリオは?資産配分や商品の選び方を解説
iDeCoの運用にはポートフォリオの設定が重要だと聞いたことがあるものの、難しそうだと感じて加入をためらっている人もいるのではないでしょうか。自分に合ったポートフォリオを組まずにiDeCoの運用をはじめると、思ったように資産形成できない可能性があります。そこで今回は、年代別にiDeCoのおすす...
ideco
新着ideco関連のお役立ちコンテンツ
iDeCoと個人年金保険はどっちがおすすめ?違いやメリット・デメリットを解説
将来に向けた資産形成ができる、iDeCoと個人年金保険。老後資金を確保するためにどちらかをはじめたいと考えているものの、どちらがよいかわからず申し込みに踏み切れない人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、iDeCoと個人年金保険の違いやそれぞれのメリット・デメリットについて解説します。どち...
ideco
iDeCoの掛金の上限は?月々の掛金の平均・目安も解説
公的年金にプラスして給付を受けられるiDeCo。加入を検討しているものの、掛金の上限がわからない、掛金の目安を知りたいなど、さまざまな疑問が生じてしまい、申し込みに踏み切れない人も多いはずです。本記事では、iDeCoの掛金の上限を徹底的に解説します。掛金の平均や目安を決める方法なども紹介するの...
ideco
iDeCoは個人事業主・自営業・フリーランスにおすすめ?税制優遇など活用方法を解説
老後に向けた資産形成の重要性が高まるなか、注目が集まるiDeCo。会社員に比べて年金額が少ない個人事業主や自営業者で、加入を検討している人も多いのではないでしょうか。しかしiDeCoのメリットやデメリットがよくわからず、加入まで踏み切れないという人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、iD...
ideco
iDeCoの掛け金は月5000円では意味ない?最低金額でも得する方法や注意点を解説
毎月一定額を積み立てて老後に備える私的年金制度、iDeCo。掛け金は月々5,000円から設定できますが、最低金額で積み立てても意味がないと考えて、始めていない人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、月5,000円だけでもiDeCoに拠出する意味はあるのかについて解説します。5,000円しか...
ideco
iDeCoは元本割れのリスクがある?元本確保型と元本変動型について解説
老後の資産形成に役立つとして注目されている私的年金制度、iDeCo。節税効果の高さや投資への関心の高まりから、加入を検討している人も多いのではないでしょうか。しかしiDeCoには元本割れのリスクがあると聞き、不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、iDeCoは元本割れする可...
ideco
iDeCoは本当にデメリットしかない?入るべき理由やメリット、注意点を解説
長期的に積み立てて老後の生活資金にできる、確定拠出年金のiDeCo(イデコ)。入らないほうがいいなどのウワサを聞いていて、実際のところはどうなのか、入ったほうがいいのか気になっている人も少なくないはずです。そこで今回は、iDeCoのデメリットやメリットについてわかりやすく解説します。iDeCo...
ideco
iDeCoは何歳から何歳まで加入できる?50・60代から始めても遅くないのかも解説
年金制度改正法の改正で、老後の資産形成がよりしやすくなったiDeCo(イデコ)。入る際に年齢制限はあるのか、50・60代で加入しても遅くないのか、気になっている人も少なくないようです。そこで今回は、iDeCoに加入できる年齢の条件についてわかりやすく解説します。何歳からいつまでに加入すればメリ...
ideco
iDeCoは年末調整・確定申告が必要?所得控除でいくら戻るのか解説
必要に応じて年末調整が必要なiDeCo。iDeCoに税制優遇があると知って始めてみたものの、年末調整や確定申告を行う必要はあるのか、どのくらい税金が戻ってくるのかなど、さまざまな疑問を感じている人も多いのではないでしょうか。本記事では、iDeCoの年末調整や確定申告の必要性を解説します。減税額...
ideco
会社員でもiDeCoに加入したい!上限や会社に知られない方法も解説
毎月お金を積み立て、老後のための資産形成ができる私的年金制度iDeCo(イデコ)。フリーランス向けのイメージがありますが、会社員も加入できます。しかし、加入を検討しているものの、会社員が加入するための条件や方法がわからず悩んでいる人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、会社員がiDeCoに...
ideco
iDeCoと国民年金基金はどっちがいい?併用は可能?個人事業主向けの年金について解説
個人事業主が老後資金を貯めるときに、選択肢に挙がるのがiDeCoと国民年金基金。しかし、違いがよくわからず、どちらで積み立てるべきか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、個人事業主の資産形成にあたって、iDeCoと国民年金基金のどちらを選べばよいかについて解説します。それぞれの...
ideco
