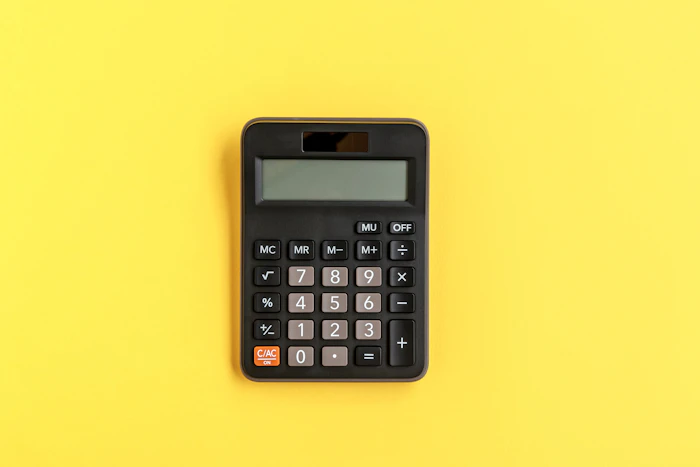
クラウドファンディングに税金はかかる?確定申告はどうする?
インターネットで多くの人から資金を集められるクラウドファンディング。資金調達者や資金提供者としてクラウドファンディングを利用すると、どのような税金がかかるのか気になりますよね。
そこで今回は、クラウドファンディングの税金について疑問を解消したい人に向けて、どのような税金がかかるのか、確定申告はどうするのか、節税するためにはどうすればよいのかなどを紹介します。ぜひ税金に関する疑問を解消したうえでクラウドファンディングを利用しましょう。

大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
クラウドファンディングの利用には税金がかかる?確定申告も必要?

クラウドファンディングを利用すると、購入型や寄付型の資金調達者は税金の課税対象となり、確定申告が必要な場合があります。
一方で資金提供者の場合は支出であって課税対象とならないので、確定申告の必要はありません。ただし、支出が必要経費となったり寄附金控除の対象になったりする場合など、確定申告をしたほうが良い場合があります。
クラウドファンディングにかかる税金の種類
クラウドファンディングにかかる税金の種類を、クラウドファンディングの種類ごとに紹介していきます。ただし紹介するのは一般的な例であり、実際には具体的な取引の内容で課税関係が決まることに注意してください。
寄付型クラウドファンディングの税金
まずは寄付型クラウドファンディングの税金について確認していきましょう。
寄付型クラウドファンディングとは?

寄付型クラウドファンディングとは、経済的な利益がリターンとして設定されていないクラウドファンディングのことです。プロジェクトの活動報告やお礼のメールがリターンとされている場合、経済的利益はないため寄付型クラウドファンディングに分類されます。
名前のとおり、資金提供者は資金調達者に対して寄付または贈与をします。また、寄付型クラウドファンディングの取引は、対価性がないため消費税の課税対象外です。
資金調達者の税金

個人が個人から1年間に110万円を超える寄附(贈与)を受けると、贈与税の課税対象です。課税対象であれば、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納税が必要となります。贈与税の計算方法は国税庁のサイトで確認しましょう。
個人が法人から受けた贈与(寄附)は一時所得の収入となり、クラウドファンディングサイトに支払う手数料などを引いた額が特別控除額の50万円を超えれば所得税や住民税の課税対象です。税金の計算は、一時所得からさらに2分の1にした金額をもとに計算します。
仮に手数料を差し引いた額が100万円の場合、50万円の特別控除額を適用した50万円が一時所得です。税金を計算するときは、一時所得50万円の2分の1である25万円を給与所得や事業所得などと合計して税金を計算します。
なお、給与年収2,000万円以下の給与所得者で寄付型クラウドファンディング以外に所得がなければ、贈与(寄附)を受けた金額から手数料を引いた金額が90万円以下なら所得税の確定申告をする必要はありません。
法人が個人や法人から寄附を受けると、受贈益として法人税の課税対象です。
資金提供者の税金

寄付型クラウドファンディングの資金提供者は、支出をしただけなので税金はかかりません。
確定申告は不要ですが、個人の場合、寄附先によっては確定申告をすると寄附金控除を受けられる場合があります。法人も一定の範囲内で損金に算入できます。
寄附金控除については後ほど詳しく説明しているので、参考にしてください。
購入型クラウドファンディングの税金
続いて購入型クラウドファンディングの税金について確認していきましょう。
購入型クラウドファンディングとは?

購入型クラウドファンディングとは、資金提供者に対して商品やサービスなど経済的利益があるものをリターンとして設定するクラウドファンディングです。
経済的利益があるため、寄付型クラウドファンディングには分類されません。
資金調達者の税金

購入型クラウドファンディングの資金調達者は、商品やサービスの予約販売をしたとして税金を計算することが一般的なので、所得税や住民税、法人税の対象です。
ただし、支援金を受け取った時点ではまだ商品やサービスの提供をしていないので、会計上は受け取った支援金を売上(収益)ではなく前受金(負債)として処理します。商品やサービスを提供していない段階では売上(収益)にはなりません。
実際に商品やサービスの提供をしたとき、前受金(負債)を売上(収益)とします。クラウドファンディングサイトに支払う手数料や商品の発送にかかる送料などは、個人であれば必要経費、法人であれば損金として計上可能です。
実際に商品やサービスの提供をしたとき、支援金から手数料や送料などを差し引いた金額が、所得として所得税や住民税、法人税の課税対象となります。
資金提供者の税金

購入型クラウドファンディングの資金提供者は、支出をしただけなので税金は発生しません。ただし、個人の業務や事業に関係する支出であれば雑所得や事業所得の金額の計算において必要経費にできます。法人は事業に関係する支出であれば損金です。
必要経費に算入できるのは、実際に商品やサービスの提供があった年となります。商品やサービスの提供を受けていないのに支出した金額は必要経費にできません。
投資型クラウドファンディングの税金
投資型クラウドファンディングの税金について紹介します。
投資型クラウドファンディングとは?

投資型クラウドファンディングとは、投資による収益がリターンとなるクラウドファンディングのことです。投資型のなかでも、融資型や株式投資型、ファンド型があります。
資金調達者の税金

投資型クラウドファンディングの資金調達者は、融資型や株式投資型、ファンド型いずれの場合でも調達時に税金は発生しません。
融資型では、返済しなければならない借入金として資金を調達します。所得税や法人税は「経済的な利益」に対して課税するため、利益ではない負債に税金は発生しません。
株式投資型は株式を発行して資金調達をするため資本金、ファンド型は一般的に匿名組合出資を受けて資金調達をするため出資金です。資本金と出資金はいずれも利益ではないため、税金は発生しません。
ただし、借入金や資本金、出資金をもとに利益を出した場合には、利益に対して所得税や法人税がかかります。
資金提供者の税金

投資型クラウドファンディングの資金提供者は、投資したときは支出をしただけであるため、税金は発生しません。投資をして利益を得たときに税金が発生します。
投資型クラウドファンディングのうち、融資型とファンド型は一般的に匿名組合契約を締結して投資をします。匿名組合契約を締結して利益が分配されたときの所得区分は雑所得です。法人の場合も同様に法人税の課税対象となります。
また、分配を受けるときは復興特別所得税や復興特別法人税を含む20.42%の税率で源泉徴収されます。所得によっては、源泉徴収された所得税や法人税を確定申告によって還付を受けることも可能です。
株式投資型の場合も、配当があれば配当所得、譲渡益があれば譲渡所得として所得税や住民税の課税対象です。
配当所得は給与所得や事業所得などと合わせて税金を計算します。譲渡所得は、所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%の合わせて20.315%の税率です。
上場株式では認められていますが、確定申告不要制度の選択や損益通算、繰越控除は原則として認められていないことに注意しましょう。
ただし、エンジェル税制の適用を受けられる場合には投資額について寄附金控除の適用を受けられるなど、各種特例の適用も可能です。クラウドファンディングサイトによっては新株予約権も取扱っており、税金の仕組みは複雑となります。
詳しくは国税庁のサイトを参考にするか、税理士に相談しましょう。
クラウドファンディングで資金調達者が節税する方法
クラウドファンディングで資金調達者が節税する方法を紹介しますので、ぜひ実践してみてください。
基礎控除や特別控除を利用する

贈与税の場合は、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば課税されません。また、法人から寄附や贈与を受けた個人は寄附された金額を一時所得の収入金額としますが、最高50万円の特例控除があります。寄附された金額からクラウドファンディングサイトに支払う手数料を差し引いた額が50万円以下であれば一時所得は0円です。
なお、基礎控除や紹介した特別控除を受けるためにあえて確定申告をする必要はありません。
青色申告をして所得控除を受ける

個人事業者は、一定の要件を満たして青色申告をすると最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。そもそも青色申告とは一定水準の記帳にもとづいて正しく申告をすることによって受けられる優遇制度です。
青色申告をするためには、その年の3月15日までか、新規開業の場合は業務開始日から2か月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。最大65万円の控除を受けるには、複式簿記で記帳して期限内に貸借対照表を添えてe-Taxで確定申告をするなどの要件を満たさなければなりません。
クラウドファンディングに必要な費用を経費として計上する

クラウドファンディングサイトの運営者に支払う手数料のほか、購入型であればリターンの提供にかかった費用なども必要経費として忘れないようにしましょう。
ただし、贈与税には必要経費の概念はありません。
支援金を20万円以下に収める

給与所得者の場合、支援金を20万円以下に収めると所得税の節税ができます。給与年収2,000万円以下の給与所得者の場合、年末調整されなかった給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円以下なら確定申告不要とされているからです。
また、前述のとおり所得は手数料やリターンの提供にかかった費用、青色申告特別控除などを差し引いて計算するため、実際には20万円を超えても直ちに確定申告が必要になるわけではありません。
ただし、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合もあるので注意しましょう。市区町村によって住民税の申告が必要かどうか異なるため、確定申告をしない場合は、市区町村の役所に問い合わせて確認することをおすすめします。
クラウドファンディングで資金提供者が節税する方法
クラウドファンディングで資金提供者が節税する方法も紹介していきます。手続きが必要な場合もあるので、ぜひ支援する前にチェックしてみてください。
寄付金控除を受ける

寄附金控除を受けると、課税される所得を抑えられます。寄附金控除額は、対象となる寄附金の合計額から2,000円を差し引いた額です。控除を受けるためには、寄附金の受領証(領収証)などを添付して確定申告書を提出します。
法人の場合は、個人では控除の対象にならない寄附でも損金に算入可能です。一般の寄附金として、「資本金等の額」の0.25%と「所得」の2.5%を合計した額の4分の1まで損金に算入できます。
源泉徴収済みの分配金を確定申告する

融資型やファンド型の場合、確定申告が不要であっても、確定申告をすると税金の還付を受けられる場合があります。
分配金は雑所得として給与所得や事業所得などと合計して税金を計算しますが、税金の計算をする前に20.42%の税率で源泉徴収されているからです。
各種所得の合計金額から所得控除の合計額を差し引いた課税総所得金額が、目安として1,200万円以下であれば確定申告をすると所得税の還付を受けられます。
確定申告をするときの所得区分は、前述のとおり雑所得(その他)です。確定申告書に収入金額や必要経費、源泉徴収税額の記載が必要となるため、クラウドファンディングサイトから発行される損益報告書などを確認しながら作成しましょう。
なお、税務署に対して特に提出する書類はありません。
クラウドファンディングの税金に関する注意点
クラウドファンディングの税金に関して注意すべき点を紹介します。クラウドファンディングの利用を検討している人はぜひチェックしておいてください。
源泉徴収される分配金でも確定申告が必要なことがある

融資型やファンド型のクラウドファンディングでは分配金が源泉徴収されますが、一部確定申告が必要になる場合があります。
確定申告が必要になるのは、確定申告によって所得税が納税となる場合のほか、納税とならなくても所得税の還付や他控除を受けたい場合などです。所得税が納税となるかどうかは、確定申告書作成コーナーで実際に計算してみましょう。
年末調整を行う給与所得者(会社員)であれば、分配金が20万円を超えても源泉徴収税率が20.42%と高いことから、一般的に税金を納めすぎている状態となるので確定申告をする必要はありません。納めすぎた税金の還付を受けるには確定申告が必要です。
また、医療費控除や寄附金控除、55万円または65万円の青色申告特別控除、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除を受ける場合のほか、不動産や株式の譲渡損失について損益通算や繰越控除をしたい場合にも確定申告をしなければなりません。
所得税の確定申告は不要でも住民税の申告は必要になる場合があるため注意してください。
購入型で得た支援金には消費税も課税されることがある

例えば、個人事業主として活動するデザイナーがイラスト制作をリターンとして設定した場合、その取引は消費税の課税対象となる場合があります。イラスト制作などを事業とするデザイナーが事業として支援金を得て役務の提供(サービス)をしていると認められる可能性があるからです。
消費税の免税事業者であれば消費税の納税義務は免除されていますが、2期前の課税売上高が1,000万円超えなどの場合には納税義務があります。
経費の書類は捨てずに7年間保存しておく

クラウドファンディングサイトに支払った手数料の場合、青色申告者であれば受け取った領収証や振込をした場合の預金通帳などは7年間保存します。白色申告者の場合は5年間です。法人は、書類の種類にかかわらず一律7年間保存しなければなりません。
保存した書類は税務調査の対象であり、書類を捨ててしまった場合には経費として認められない場合があるので注意しましょう。
クラウドファンディングのおすすめサイトもチェック!

クラウドファンディングサイトで資金調達や支援を考えている人は、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください。クラウドファンディングの仕組みやサイトごとの特徴、おすすめのサイトがわかります。
本サイトは情報提供が目的であり、個別の金融商品に関する契約締結の代理や媒介、斡旋、推奨、勧誘を行うものではありません。本サイト掲載の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いません。
人気クラウドファンディング関連のお役立ちコンテンツ
投資型クラウドファンディングの特徴・メリットとは?仕組みや上限金額も解説
比較的新しい投資先として近年注目を集めている、投資型クラウドファンディング。しかし、投資型クラウドファンディングの種類や仕組みはさまざまで、いまいち内容が掴めなかったり、本当に利益を出せるのか不安に感じていたりする人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、投資型クラウドファンディングの特徴や...
クラウドファンディング
寄付型クラウドファンディングとは?特徴や仕組み、メリットを徹底解説!
支援者から集めた資金を寄付金として活用できるのが、寄付型クラウドファンディングです。どのようなサイトで寄付を集められるのか、クラウドファンディングサイトの利用方法がわからないなど、不安に思っている人も少なくないはず。今回は、寄付型クラウドファンディングとは何なのかを解説したうえで、起案者と支援...
クラウドファンディング
クラウドファンディングのメリット・デメリットは?種類ごとに解説!
インターネットで、気軽にプロジェクトの実行に必要な資金を集められるクラウドファンディング。資金調達の方法として、どのようなメリットやデメリットがあるのか気になっているはずです。そこで今回は、資金調達を検討している人に向けてクラウドファンディングのデメリットを紹介します。デメリットもよく理解して...
クラウドファンディング
