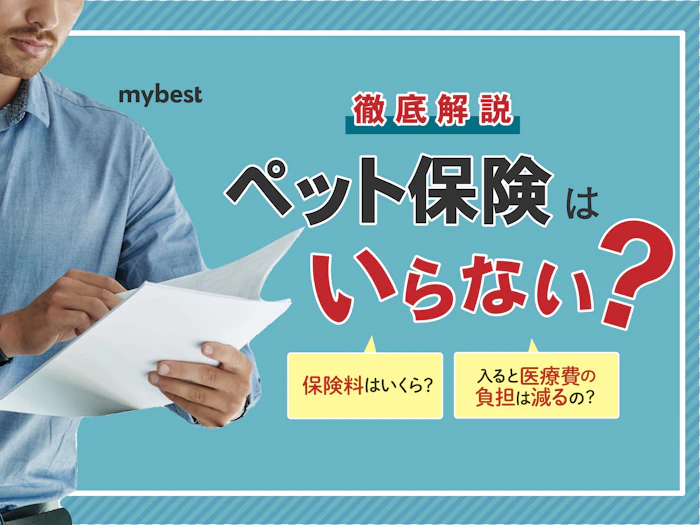
ペット保険はいらない?貯金とどちらが良い?後悔しないための知識を徹底解説
大切な家族の一員であるペットの治療費をサポートするペット保険。しかし、ペット保険はいらない、貯金しておけば大丈夫などという声を耳にして、果たして保険は必要なのか迷う人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、ペット保険の概要や必要性について詳しく解説します。ペット保険が必要な人、不要な人の特徴についても解説するので、大切なペットの健康のためにぜひ最後までチェックしてみてください。

大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
本コンテンツは情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品についての勧誘や契約の推奨を目的としたものではありません。弊社が内容について正確性を含め一切を保証するものではないため、個別商品については各保険会社にお問い合わせください。
ペット保険とは?
まずは、ペット保険の概要について解説します。
犬や猫などペットの治療費の一部をカバーする保険

ペット保険とは、ペットの病気やケガで発生した入院・手術・通院などの医療費の一部を補償する保険です。保険会社や商品により異なりますが、一般的には保険料は掛け捨てで、1年ごとに更新があります。
ペット保険のなかには、特約を付帯できる商品もあるので、必要な場合には検討するとよいでしょう。たとえば、賠償責任保険を付帯しておくとペットが他人にケガを負わせたり物を壊してしまったりしたときに補償を受けられます。そのほか、葬祭保険金特約やペット用車イス作成費用特約など、もしもの時に備えたオプションを付帯することも可能です。
ペット保険の加入者は2020年時点で12.2%に上ると推計されており、現在も加入者が増え続けています(参照:アニコム損害保険株式会社)。ペットの飼育を検討している人や、現在すでに飼育している人は、早めに検討してみましょう。
保険料は補償割合やペットの種類・年齢によって決まる

ペット保険の保険料は、補償割合・免責金額・ペットの種類や年齢・支払い上限額などによって変動するのが一般的です。
ペット保険は全額補填ではなく、補償割合に応じた金額が保険金として支払われます。補償割合は、発生した治療費の50%から70%程度に設定されていることが多く、補償割合が低いほど、支払われる保険料は安くなります。免責金額が設定されている場合も、支払われる保険料は安くなります。
また、高齢のペットは病気のリスクが高いため、毎月の保険料が高く設定されるほか、ペットの種類によってもかかりやすい病気が異なるため、犬種も保険料を左右する要素になります。
ペット保険のなかには支払い上限額が定められているものもあり、治療1回あたりの支払い限度額や、年間での支払い限度額など、規定は保険会社によって異なるため注意しましょう。基本的に、支払い上限額が低く設定されていれば、保険料は安くなります。
補償対象外となる治療もあるので注意

ペット保険には補償が適用されない治療もあるので、気をつけましょう。対象外の治療に関しては全額自己負担に。
補償対象外となる治療の規定は、保険会社ごとに異なりますが、一般にワクチン接種・予防接種などで防げる感染症や、歯石取り・トリミング・健康診断・去勢・妊娠や出産などは補償対象外となる場合が多くなっています。加入前によく確認してください。
ペット保険はいらない?必要性について考えよう
ここからは、あらためてペット保険の必要性について考えてみましょう。
ペットの治療費は自由診療扱い。全額自己負担になる

ペットの治療費は全額自己負担となり、高額になる場合が多いため、不安な場合は保険に加入しておくのがおすすめです。
ペットには人間のような公的医療保険制度はなく治療費は自由診療扱いになるので、各診療施設が自由に設定できます。そのため、費用は高額になりがち。住んでいる地域によっても費用が異なることが多いため、近隣の診療施設の価格設定を事前に確認しておくことも大切です。
ペットの平均寿命は伸びている

犬や猫の平均寿命は伸び続けており、高齢になるほど治療費は高くなる傾向にあるため、ペット保険で備える必要性が高まっています。
医療技術の発展・食環境・飼育環境の変化により、2008年度には犬は13.2歳、猫は13.9歳だった平均寿命が、2019年度には犬は14.1歳、猫は14.3歳に伸びています(参照:アニコム損害保険保険株式会社)。
1か月あたりの診療費は、犬の場合は0〜6歳時は平均7,136円であるのに対し、13歳以上になると平均9,801円に(参照:日本獣医師会家庭飼育動物(犬・猫)の診療料金実態調査及び飼育者意識調査調査結果)。
猫の場合は0〜6歳時は平均6,779円であるのに対し、13歳以上は平均7,991円に上がっており、いずれも13歳以上になると費用が高くなっています(参照:同上)。
年齢が上がるに比例して、診療施設を利用する頻度が高くなったり、診療費が高額になったりするため、ペット保険に加入し対策を講じておくとよいでしょう。
ペットの治療は高額になるケースが多い

ペットの1回あたりの診療費が、数十万円に上るケースも存在。日本獣医師会の調査では、ペットの治療費の最大額として10〜40万円未満という人が、全体の20%以上を占めています(参照:日本獣医師会・家庭飼育動物(犬・猫)の診療料金実態調査及び飼育者意識調査調査結果)。
犬の場合の保険金請求事例でもっとも多い、異物誤飲による消化器疾患の治療費は22万円以上。ほかにも骨折した場合に、88万円以上の治療費が発生した事例があります(参照:楽天ペット保険)。
猫の場合も消化器系疾患がもっとも多く、胃腸炎によって15万円以上の請求が発生する事例がありました。猫がかかりやすい泌尿器系の急性腎不全の場合は、治療費は70万円以上にも上っています(参照:楽天ペット保険)。
ペット保険に加入したほうがいいのはどんな人?
以下では、ペット保険に加入して備えておいたほうがいい人の特徴について解説します。
お金の面を心配せずペットに万全な治療を受けさせたい人

ペットに万が一があったときに、経済的な面を心配せず、万全な治療を受けさせたいならペット保険に加入した方がよいでしょう。何割かでも補償が受けられれば、高度な治療を経済的な理由で諦める必要がなくなります。
また、お金の面を気にせず頻繁に病院に連れて行ければ、早期発見・早期治療の可能性もアップ。ペットの健康を守りやすくなりますよ。
突発的な支払いに不安がある人

ペットの治療費として、まとまったお金を用意しておくのが難しい人は、ペット保険に加入したほうがよいでしょう。ペットの治療には、先述のとおり1回あたり数万円〜数十万円と高額になる可能性もあります。積み重ねれば、一生涯で100万円以上の治療費がかかることもあります。
複数のペットを飼っている場合には、そのぶん治療費がかさむ可能性があるため、それぞれペット保険に加入したほうが安心かもしれません。貯蓄に自信がない人や突然の出費に不安がある人ほど、ペット保険で日ごろから備えておきましょう。
ペット保険に加入しなくてもいい人は?
次に、ペット保険に加入しなくても、治療に備えられる人の特徴について解説します。
十分に貯蓄がある人

貯蓄が十分にあり、ペットに高額な治療費が発生しても痛手にならない人にとってペット保険の必要性は低いと言えます。
1回あたりの治療に数万円〜数十万円のまとまったお金を無理なく支払える人や、高額の出費でも家計を圧迫する心配がない人は、保険料の分を貯蓄に回した方が柔軟な使い方ができるでしょう。
全額補償されないことが割高に感じられる人

支払った保険料の元が取れないと不満に感じる人は、ペット保険のメリットを感じにくいかもしれません。ペット保険では、免責金額が設定されていたり、補償割合が決められていたりすることが多く、支払った治療費全額が補償対象になるとは限りません。
また、たとえば予防接種や避妊・去勢・健康診断など、補償対象外となる治療が決められている場合が多く、その場合の支払いは自己負担になります。
受け取る保険金よりも、支払った保険料のほうが多くなってしまうこともあるため、それでは保険料を支払うメリットが小さいと感じてしまう人は、無理に加入しなくてもよいでしょう。
保険料の支払いと貯金、どっちが良い?

ペットの治療費に備える方法として、保険がいいか貯蓄がいいかは多くの人が悩むところ。家計や貯金の上記を踏まえ、両方のメリット・デメリットを比較して判断しましょう。
保険のメリットは、毎月保険料を支払っておけば急な治療費の出費に備えられることです。ペットが病気やケガをするタイミングは予測できないため、現時点で貯蓄がない場合は、保険に加入するのが無難です。
ただし、保険料の支払いが受け取る保険金を上回る可能性があることも加味しておきましょう。ペットが健康で保険を使う回数が少ない場合や、治療費のすべてが保険でカバーされず、自己負担が発生する場合もあります。
一方、貯金のメリットは、貯めたお金をほかのことにも使えることです。治療費として使わなかった分の使い道は自由で、ペットとは関連しないことにも活用できます。
ただし、貯金が貯まる前に高額な治療費が発生する可能性がある点には注意。必ずしも、貯金のみで治療費が足りるとは限りません。数十万円から百万円以上の金額が必要になることがたびたびあれば、貯金が枯渇する可能性もあるでしょう。
ペット保険に加入する際の注意点
最後に、ペット保険の必要性を判断するうえで考慮すべき注意点について詳しく解説します。
契約更新を断られる場合がある

ペット保険では、保険金の請求状況や保険料の支払い状況などにより、継続できないケースがあるので気をつけましょう。継続的な治療が必要な場合は更新できる可能性が低くなってしまい、更新できたとしても、慢性疾患に関する治療費は補償の対象外となるケースがあります。
また、ペット保険が定める補償額を使い切った場合や、毎月の保険料の支払いに遅滞が生じている場合も、更新できない可能性があるので注意。条件付きの更新となり、補償の対象外の病気が増えるなど不利な条件が付けられるケースもあるでしょう。
更新するたびに保険料が高くなる

ペット保険は一定期間ごとに保険料が高くなる仕組みになっているので、更新時には注意しましょう。たとえばペットの年齢が上がる1年ごとに更新するタイプのほか、年齢に区切りを付けて一定年数で更新するタイプがあります。
年齢が上がるタイミングは、3歳ごとや5歳ごとなど各保険会社によって異なるので、加入前にチェックしておくことが大切です。
健康状態によっては加入できないことがある

ペットの健康状態によっては審査に通過できず、保険に加入できないことがあります。審査基準は公表されていないものの、保険金を支払う可能性が高いと判断されると、加入を断られる可能性が高まります。
ただし、ペット保険に加入したいばかりに傷病歴を虚偽申告をすると、保険金が支払われない可能性があるので注意。申し込み時には、ペットの健康状態を正確に告知しましょう。
うさぎのような小動物を補償対象としているペット保険は少ない

犬や猫以外の小動物を対象としているペット保険は少ないのが現状です。たとえば、小動物のなかでも環境の変化に弱く、骨折しやすいといわれているうさぎの場合、保険の必要性が高いにもかかわらず入れる保険の種類は限られます。
うさぎを飼っている人やこれから飼う予定がある人は、うさぎに対応しているペット保険を探す必要があります。以下の記事を、ぜひ参考にしてください。
ペット保険のランキングはこちら!
以下の記事では、ペット保険の選び方を紹介しています。ペット保険について理解が深まったものの、実際にどの保険に加入すればよいのかわからないという人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
本サイトは情報提供が目的であり、個別の金融商品に関する契約締結の代理や媒介、斡旋、推奨、勧誘を行うものではありません。本サイト掲載の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いません。
