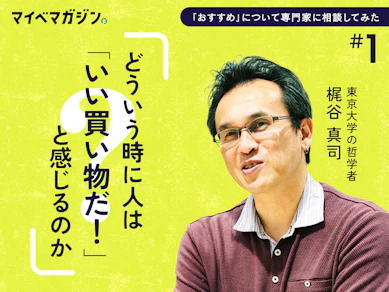
おすすめ雑誌からおすすめサービスへ転職した編集長が、哲学者と「おすすめとは何なのか」を悩んでみた(第1回)
情報も商品もあふれるなかで、一人ひとりのベストな選択をサポートするサービス「マイベスト」。
マイべマガジン編集部では「どの商品がおすすめか」だけでなく「どのようにおすすめするか」がモノを選択するユーザーの満足度につながるのでは? ただ、そもそも人っておすすめされたいの?など、めんどくさいことを考えつつ、日々コンテンツを製作中です。
なかでも特に悩みとして持っているのが「SNSふくめて情報源もユーザーのライフスタイルも多様化するなかで、おすすめメディアはどうあるべきか?必要なのか?」ということ。
そこで、編集部の浅沼がさまざまな専門家に相談して「おすすめ」の深遠なる答えを探し、その過程もコンテンツ化しよう! 面白くなかったら怒られよう!というのがこのシリーズ。実験企画です。
そして、記念すべき初回のゲストは東京大学教授・梶谷真司さんです!

2012年に雑誌や書籍の出版を行う晋遊舎に入社。2019年にテストするモノ批評誌『MONOQLO』編集長、2020年にホンモノがわかる家電情報誌『家電批評』編集長に就任。 2021年5月よりマイベストに入社。コンテンツ制作部長を経て、新規に創設されたクオリティーコントロール部長に就任。様々なジャンルの企画書作成からコンテンツ編集までを取り仕切る。2025年8月にマイベストを退社。人生サバティカル期間として、商品レビュー、コンテンツ制作・編集からゲームやAIプロダクトの企画まで、なんでも経験中。
早速ですが、今回は「哲学対話」をやってみました。

今回のゲスト・梶谷真司さんは、日本における「哲学対話」の第一人者。現在では、株式会社ShiruBe(サービス名「哲学クラウド」)において企業向けの哲学対話の監修もされています。
その哲学対話の方法に則って、マイべマガジン編集部の疑問であり悩みである「買う・選ぶ・すすめる」ということについて考えていこう!というのが今回の趣旨です。
ただ、そもそも担当の浅沼自身も「哲学対話」って何なのよ? なんか難しそうで、怖い。という思いが。そこで一旦梶谷さんを知るキッカケとなったサービスを紹介しつつ、哲学対話についても本を読んでまとめてみました。
哲学対話を知ったきっかけは、マネジメントサービス「哲学クラウド」

哲学対話と聞いて「難しそう!」と言ったことからもお分かりいただけると思いますが、僕は哲学に詳しいわけではありません。では、なぜ新たに立ち上げた企画の第1回目で哲学対話を取り上げよう!と思ったのか?
それは、冒頭で紹介したように日々モヤモヤ・悩み・迷いを抱えながら仕事と向き合っているなかで「哲学クラウド」というサービスが目に留まったから。
株式会社ShiruBeが提供する「哲学クラウド」は、簡単にいえば哲学的ファシリテーションによって集団内に生まれる摩擦を推進力へ昇華していこう!というサービス。
ビジネス関係のサービスで、効率よく数値化して分析するのでなく人文系の哲学を活用しようというのがそもそも面白そう!
しかも、悩みやモヤモヤを「問い」によって分析・可視化して「考える力」を重視するという部分も良い!
ということで「これって今の僕たちにぴったりなサービスなのでは?マイベストもだけど、新しいメディアで試してみたい!というか個人的にも話してみたい!」と感じ相談したところ、今回のゲストであり東京大学 大学院教授の梶谷さんと哲学対話することになった、というわけです。
▼哲学クラウドに興味をもったらこちら!
会社名:株式会社ShiruBe
サービス名:哲学クラウド
※お金も一切もらってなく、純粋な紹介です!(浅沼)
哲学対話は「誰にでもできる哲学の実践」? ふむ、難しい

正直「哲学」というとなんだか小難しくて、人生の迷路に迷い込みそうなイメージがある学問。答えが出ない命題を、難しい理論をもって考え続けるような「実生活と結びつかない」もの感がありますよね。僕はあります。
ただ、梶谷さんによると、哲学とは行動の基礎となる「思考力」を育てるもの。つまり、誰にでも必要なものだし、怖くないとのこと。
哲学対話は、もともと子どものための哲学(Philosophy for Children)から来ていて、これは 広い意味での思考力を育てるために1970年代アメリカの教育現場で始まったものです。それは、問う・考える・語るというというサイクルを対話のなかで繰り返し、自分が知らず知らずのうちに“前提”としていたことを問い直し気付いていなかった側面に気付いていく。
これこそが、哲学対話で味わえる哲学的な体験なのだそうです。
梶谷さんは2012年にハワイで哲学対話に出会い、帰国後に日本でワークショップを開催。現在に至るまで、学内外を問わず哲学対話の場を広げている筋金入りの哲学対話er。
本コンテンツでは実際に哲学対話を通して色々な悩みを深堀りしていこうと思いますが、「なんだか気になる」「おもしろそう!やってみたい!」という方は、ぜひ梶谷さんの著作であり、めちゃくちゃわかりやすかったこちらもチェックしてください。
この3人で哲学対話、やってみました

今回は「買うということ」について哲学対話を通して、掘り下げてみるというのがメインテーマ。
そもそも「買う」という行為は人やモノによって大きく動機や重視するポイントが違うもの。
そこで対話を始める前に、今回のゲストである梶谷さん、巻き込んでしまったマイベストコンテンツ部 部長・佐藤、マイべマガジン編集長でありマイベストのCCOでもある僕・浅沼のプロフィールと、あわせて買い物観をまとめてみました。
梶谷 真司:「物から呼ばれるか」が一番重要

愛着を持って長く使うものが多いという梶谷さん。大事なものを買うときには「物から呼ばれる感覚」を大切にしているそうです。
たしかに、商品を見た瞬間に理由も分からないまま強く惹かれたという経験はわかります。
ただ梶谷さんは基本的に「一度“惚れた”ら、ほかの商品について利点を並べ立てられても納得できない」のだとか。
もちろん、必要だから買う・機能面を見て買うこともあるとのことですが、大切なもの・高価なものに関しては、一度“惚れる”経験をしてからは、呼ばれる感覚がないと購入に踏み切れないそうです。
佐藤 柚果(コンテンツ部 部長):「効率」を買い物では最も重視

普段から、効率やコスパを重視するという佐藤さん。現代ではスタンダードな買い物観かもしれません。
そもそも日常生活のプラスαになるようなものはあまり買わず、生活必需品の中でコスパの良い商品を買うとのこと。
例えば人気の珪藻土マットも、管理しないといけないから効率良くないと思い買わなかったそう。また、新しいモノが出ると効率が良ければドンドン買い替えていくそう。
浅沼 伊織(編集長):基本的に「新しい」と思ったら何でも買ってしまう。貯金ゼロ円

今までモノをおすすめする雑誌を10年以上作り続けてきた僕、浅沼。買い物をするときの動機は常に「暮らしの悩みを解決してくれそうか」「暮らしがもっと良くなりそうか」です。
もともと性根がズボラなので、生きるの辛い。とにかく楽して生きていきたい。そのためには自分が変わるよりもモノやサービスに頼ったほうが早いと思って買い物を続けています。
僕の基準では、そうして購入したモノのなかで、1週間以上使い続けられて生活の一部になるものが「良いモノ」。
そのため人におすすめする際も「実際に使って良かったモノ」をモットー(もとい言い訳)として、「貯金0円」で生活中です。
哲学対話、初手「なぜ買うことは楽しいのか?」

上記のようにユーザーにモノを勧める仕事を続けながら、私生活でも絶えず買い続けていますが、繰り返される買い物とおすすめのサイクルのなかで、よく「人はなんで“買い物”を続けるんだろうか?」という疑問が浮かびます。
モノは確かに便利で、買うことによるベネフィット(得られるもの)がある……けど、それだけなのか?
買うためには働いてお金を稼がないといけない。労働と消費の堂々巡り。ベネフィットだけでは説明がつかないのでは?
みんなの買い物に感じる楽しさは、どんな楽しさなのか?
その結果登場したのが「ミニマリスト」なのか?
最初のトピックスとして、このあたりを梶谷さんと話してみたいと思います。
梶谷さんがパリで気付いた「迷いこそが買う楽しみでは?」という視点

浅沼:哲学とかまったくわからないですが、悩みだけはたくさんあるので本日は先生、よろしくお願いします。
梶谷:よろしくお願いします。さっそく個人的なことですけど、去年の秋にヨーロッパへ行ったときに「消費ってすごい良いな、楽しいな」って思うことがあったんです。
浅沼:え!? 突然!?
梶谷:「何を言ってもいい」それが哲学対話のルールですから。あと「人の言うことに対して否定的な態度をとらない」「お互いに問いかけるようにする」などを守っていただければ。
浅沼:承知しました!
梶谷:で、まずドイツへ行ったんですよ。ドイツって良く言えば堅実なんだけど、生活しててつまらなかったんですよね。何を見ても全然感激できなくて、でも当時は原因がわからないから自分で「年取ったかな」と思ったりして。
浅沼:なんかドイツってそういうイメージはありますよね……。質実剛健といいますか。
梶谷:でも、その後でパリに行ったら、すごく楽しくて。クロワッサン一つ取ってもめちゃくちゃ美味しくて、そういう美味しい店がたくさんあって「生きてるのって楽しいな」って思ったんですよね。
浅沼:食事が旨かったってことですか?
梶谷:いや、気付いたきっかけは食事ですけど、消費全般に関してパリには選択肢がたくさんあったんですよね。どれにしようって迷いながら選択する体験って気持ちを豊かにしませんか?
浅沼:逆にドイツはそれが少なかったと。
佐藤:選択肢があること自体も大事だけど、期待があるから楽しいというのもありそうですよね? パリの場合は「パンが美味しい」と知ってるから選ぶのも楽しいと感じるとか。
梶谷:ドイツは選択肢も少ないし、期待値も低かった、というのは確かにあるかもしれません。
浅沼:ドイツにひどいっすね……。
梶谷:ちょっと期待できる選択肢がいくつかあるなかで悩んだり、目移りしたりする楽しみというか。たしかに、期待がなければ選ぶことって苦行みたいなものですからね。
マイベストのような比較サービスは「迷って買う楽しみ」をなくすもの?

浅沼:ちなみになんですけど、今「消費の楽しみがない」ってすごく言われてたドイツ。たしかに、商品比較サービスがとても成功している国なんですよ。Stiftung Warentestという非営利の消費者団体が、1966年から出している「test」っていうテスト誌があって。
梶谷:それは、浅沼さんがやってきたような、日本の商品比較と同じ感じなんですか?
浅沼:日本の「おすすめ」とは少し違うんです。比較して一番を決めて、読者の選択肢を狭めていくっていう感覚で。店舗でも「テスト誌で1位の商品ですよ」というふうにtestのロゴが貼られていて、それが正解みたいな。
梶谷:なるほど。だからこそ、そういう環境のドイツで楽しみがないと感じたあと、パリで「迷う余地がある」って大事だなって感じたのもしれないですね。
浅沼:そう考えると、買うことをサポートする、要は比較するサービスとかメディアって、買い物を楽しくするどころか、買い物をつまらなくする存在説ありません?
佐藤:買うの楽しい!っていうのと、買うことのサポートが両立できないということですよね。たしかに……。
浅沼:マイベストは「自分にとっての最適解に効率的にたどり着くか」がメインの機能。なので「選ぶ楽しみ」とはちょっと距離があるというか。そこに自分で選ぶときみたいな楽しさもどうにか組み込めないか? っていう試みとして「マイベマガジン」を作ってみたんです。
(詳しくは第3回へ)
佐藤:そうすると、今回みたいに「そもそも自分で選ぶときはなんで楽しい?」とか、買い物するっていうこと自体を分析?というか自分たちが分かっていかないといけないという。
浅沼:そう。だから、買い物自体もそうだし、買うに至るまでの悩みみたいなところもコンテンツ化できないかって考えて試行錯誤してるんです。
で、結局人はなぜ「買い続ける」のか?

「買い物の楽しさ、それはたくさんの選択肢のなかから、自分にとってのベストを探し出すことでは?」という話が出ました。
しかし、現代社会では使い捨てと言って良いほど短いスパンで買い替えるものや、スマホのように1年単位で新モデルが出て欲しくなるものもあります。
ちなみに、こうした背景のなかでベストなモノをおすすめし続ける行為(編集)を続けてきた僕自身、おすすめし続けることに対する虚無感が湧いてくることがあります。
だって、ベストなモノなら買い替える必要がないはずだから。
そこで、人が買い物を繰り返すのはなぜなのか?というところも梶谷さんと一緒に考えてみたいと思います。
買う楽しさは「入手すること」でなく「入手する過程」にある?

梶谷:たしかに“消費し続ける”って言葉を聞くと、良くないイメージもあるじゃないですか。大していらないものを作って買っての繰り返しみたいな。
浅沼:そう。なんか、たぶん買わなくていいものもあるんです。買ってるなかには。
梶谷:ただ、商品から得られるものが必要なのではなく「買うという行為が楽しいから、また買いたくなる」っていうのは、シンプルだけど人が買い続ける一番の理由かもしれないですね。
浅沼:ここまでで言うと「これは良かった」みたいな成功体験があれば次に買うときの期待値が上がってさらに楽しいみたいなのもあるけど、それだけじゃないってことですか?
梶谷:そうそう。最終的に買う・買わないは別としても見てるだけで楽しいっていう場合とか。あとは、どれが良いかって迷ってるときの楽しさとか。そういう入手する過程での楽しさを繰り返し体験したければ、結果として買い物をし続けることになりますよね。
人生は少し先の未来の積み重ね。だから少し先の幸福(買い物)に投資する?

梶谷:たとえば、さっきお話したパンが美味しいとかって、すごく些細なことですよね。画期的な商品でもないし、生活の利便性も向上しない。でも、それがあることによって、日常の些細なことに興味を持てるっていう所が大事だと思うんですよ。
浅沼:どうでもいい、あまり重要ではないものから、自分でも予期し得ぬ影響を受けるってことですかね?
梶谷:うん。世の中って「本当に大事なもの」ってあんまり無くて。でも、どうでもいいことが多いとたぶん、つまらないじゃないですか。
浅沼:究極、すべてがどうでもいいっていう状況になりますよね。その考え方だと。
梶谷:そこで、何か小さなことに興味を持つと、どうでも良かったことが少し楽しくなる。で、その興味が湧いてくるきっかけの一つが「買う」という行為かなと思いますね。
浅沼:なんか、別にそのスポンジじゃなくてもよかったけど、ちょっと良い食器用スポンジ買ったら食器洗うときのテンション結構上がるみたいなことですかね。どうでもいいことがちょっとだけ楽しくなるみたいな。
梶谷:そう、なんかね、買うこととは少し離れますけど太宰治っていますよね?あの人、最後は自殺するじゃないですか。日頃から死にたい死にたいと思ってて。
浅沼:はいはい。
梶谷:でも、あるときに着物をもらって「夏が来たら、これを着るのが楽しみだ」って思うんですよね。あんなに死にたくても。
浅沼:モノを手に入れたことで、少し先の未来は生きている前提になる瞬間があったってことですね。
梶谷:そう。だから「何のために生きるか」とか、そういう大上段(高い視点からの大きな問い)とかは、本当はどうでもよくて。多分生きていく上では、小さなことの楽しみとか、少しだけ先の未来への期待って大事なんですよね。
浅沼:人は実は、それにどこかで気づいているから物を買い続けるのかもしれない説ありますね。
どうしたら買って満足できる「マイベスト」なモノに出会えるのか?

マイベストは、特定のジャンルのなかで「どれを買うのが良いのか」と迷っている人をターゲットに、モノのマッチングを目指すサービスです。
しかし、ここまでの対話でも、狭められてしまうつまらなさ・自分で迷う楽しみというキーワードは何度か出てきました。
多くの“おすすめ”をしてきた僕自身も「これがデータ的に1位だよ、おすすめだよ」という文脈では、すすめられる側としてはしっくり来ないのではないかと感じることがあるそうです。
そこで、この悩みを解決する糸口として、自分にとって良いモノに出会う難しさ・巡り合う醍醐味について哲学対話ってみようと思います。
ベストなモノとの出会いは「本気の恋」に似ている?

梶谷:浅沼さんは、こういうのが欲しい!こういう部分を重視したい!って思って買うんだけど、結果いまいちみたいなことないですか?僕は結構あるんですよね。
浅沼:僕もあります!例えば初めて買うジャンルのものって平均値がどれくらいで、どこからが「いいもの」なのかとか、どこがどうだと自分に合うのかとか分からないじゃないですか。
梶谷:そうなんだよね。こういうのが自分に合ってるんじゃないかと予測して買うけど、実際はそうでもないみたいな。
浅沼:結局、買い物に限らず人って、何を求めてて、何が課題なのか、どうだと好きになれるのか自分自身よく分かってないみたいな所ありますよね。
梶谷:あるある。僕は哲学の研究で、ハイデガーという思想家をやってたんですよね。でも最終的に、6年やって好きじゃないことがわかったという経験があって(笑)
浅沼:6年、結構長いですね(笑)しかも、先生は哲学が専門なのに、それでも哲学分野で選び間違えることがあるっていう…。
梶谷:最初の頃は好きだと思い込んでたんですよ。で、途中からつらいなとは思ってたんだけど「研究だし、つらいこともあるよな」とかいろいろ理由を付けて。でも、最終的に確信を持って「あ、これは好きではなかったな」って。
佐藤:研究もそうですけど、物とか付き合う人とかも、なんか合理化・正当化しようとしません?今あるものや、自分で選んだものを。
梶谷:たしかにね。で、最終的に「面白くなかった」と気付いたきっかけは何かっていうと、本当に面白いと感じるものに出会ったことなんです。恋と一緒で、本当に好きな人に出会うと「あの人は、いい人だと思ってたけど好きとは違った」みたいな。結局、自分のことなんだけど外から気付かされるんですよね。
「どうでもいい」と思えなくなった瞬間が恋

佐藤:本当に良いモノに出会うことで変わった!っていうつながりで、モノの話していいですか?
浅沼:買い物でそういう経験があったってこと?
佐藤:そう。私はマイベストに入るまで、大学の1年生のときに買った超安いドライヤーを6年間使い続けてたんですよ。ガスみたいな臭いがしてたんですけど乾けばなんでもいいやみたいなレベルで使っていて。
梶谷:ガス!?なんか燃えてたんじゃないのソレ(笑)
佐藤:たしかに(笑)でも、ランキング1位になった商品に替えたら、髪の毛の質も、乾かすのにかかる時間も、全てが劇的に変わって。そのとき初めて「買うことで人生変わった」と感じたんです。
浅沼:すごいっすね。底辺から最先端へ一気に行ったってことでしょ?でもたしかに、僕もそういう「こんなに良いモノあるなら、みんなもっと早く教えてよー」っていう現象の積み重ねが楽しくてこの仕事やってるんですよね。
梶谷:買い続ける浅沼さんでも、そういう体験はあるんですね。
浅沼:例えば毛玉取りとか。セーターって汚くなって駄目になっていくのが当たり前だと思ってたのに、毛玉取り使ってみたら復活して「こんな文明の利器があったの!?」って。で、そういうのに出会うと「もっといいものないのかな」って探していくようになる。
梶谷:もともと「どうにもならない」と思っていたことが変わったとか、面倒だと思っていた作業で良い結果が得られたとか、そういう偶発性が大事というのもあるかもしれないですね。
浅沼:そうですね。僕も髪乾かすの面倒くさいと思いますけど、嫌なことがモノによって思いがけず「少しいい体験」に変わったときに、買って良かったって思いますよね。
佐藤:ただ、やっぱり出会いって難しいじゃないですか。別に最初から「それがいい」って知ってて買うわけじゃないし。ドライヤーに関しては、そもそも欲しいと思って探してたジャンルですらなかったから。
浅沼:さっき梶谷先生も本当に良いものとの出会いを「恋と一緒」って言いましたけど、恋って「恋しよう!」と思って始めるわけではないじゃないですか。だから、めちゃくちゃ価値観変わった!って思える買い物も、探そうと思ってないときに唐突に向こうから来て、結果として良かったみたいなことってありますよね。
梶谷:そうそう。恋は「落ちるもの」ですからね。
拡散しまくったけど、一旦、まとめです

哲学対話、という名の問いの連想会話であらためて考えた「買う楽しみ」について、みなさんいかがでしたか?
といっても、なんだかめんどくさい話が続いたな……と思った人も多いと思いますが、「自分はどういう買い物観なのか」を考えるきっかけになれたのであれば嬉しいです。
哲学対話という名の「問いの連想ゲーム」をしてみて思ったのは、梶谷さんのヌルっとした達人のような問いの流れに話が永遠に続いたということ。そして、一言に買うことの楽しさといっても、店舗や商品の選択肢が多いこと・商品に期待が持てること・モノによって未来を想像すること…など、無数の動機があるということ。
また、点数化された中での「ベスト」だけを伝えるという合理的な方法では、多くのユーザーが質の良いものにたどり着けるものの、選択する楽しさは排除されてしまうというマイベストの特色にも気づけました。そして、そこをカバーするために「楽しい買い物」に寄せたオウンドメディア(マイベマガジン)を作りたいという謎の決意も生まれました。
ここから選択などについて掘り下げれば、今後のマイべマガジンが進む方向もまぶたの裏側にかすかに見えてくるのでは…ということで、シリーズ2回目となる次回は「選択すること」を中心に哲学対話ってみようと思います。

